教師という夢を抱いて教育実習に臨んだ学生が、わずか2週間でその夢を諦めてしまう――。このような衝撃的な声が、昨今、SNSを中心に大きな波紋を広げています。教育現場で語られた学生の本音は、現役教師や実習経験者からも多くの共感を集め、「教職離れ」という社会問題の根深さを改めて浮き彫りにしています。本記事では、SNSで話題となった教育実習生の言葉を皮切りに、教職を志す若者が直面する現実と、教師という職業の多忙な実態に迫ります。
教育実習生の本音「私には無理です」がSNSで波紋
「教師を目指してきたけれど、たった2週間で自信をなくしてしまった」。この痛切な言葉は、小学校教員として働く「すみれ@小学校教員」さん(@suMiremon_sense)が、実際に教育実習に来ていた学生から聞かされたものとしてSNSに投稿されました。その学生は、「教師になる気でここに来ましたが、きっと1年も続けられないと思います。今働かれている先生方には尊敬しかありません」と語ったといいます。
この投稿は瞬く間に拡散され、「諦めた側だからよくわかる」「“楽しいところだけ”をやらせてもらっているのを感じた」といった、共感の声がリプライ欄に相次ぎました。教職を志す若者がなぜ、わずかな期間の実習で「教師をあきらめる」決断に至るのか。教職離れが社会問題としてたびたび指摘される現代において、この現象は教育現場の厳しい現実を物語っています。
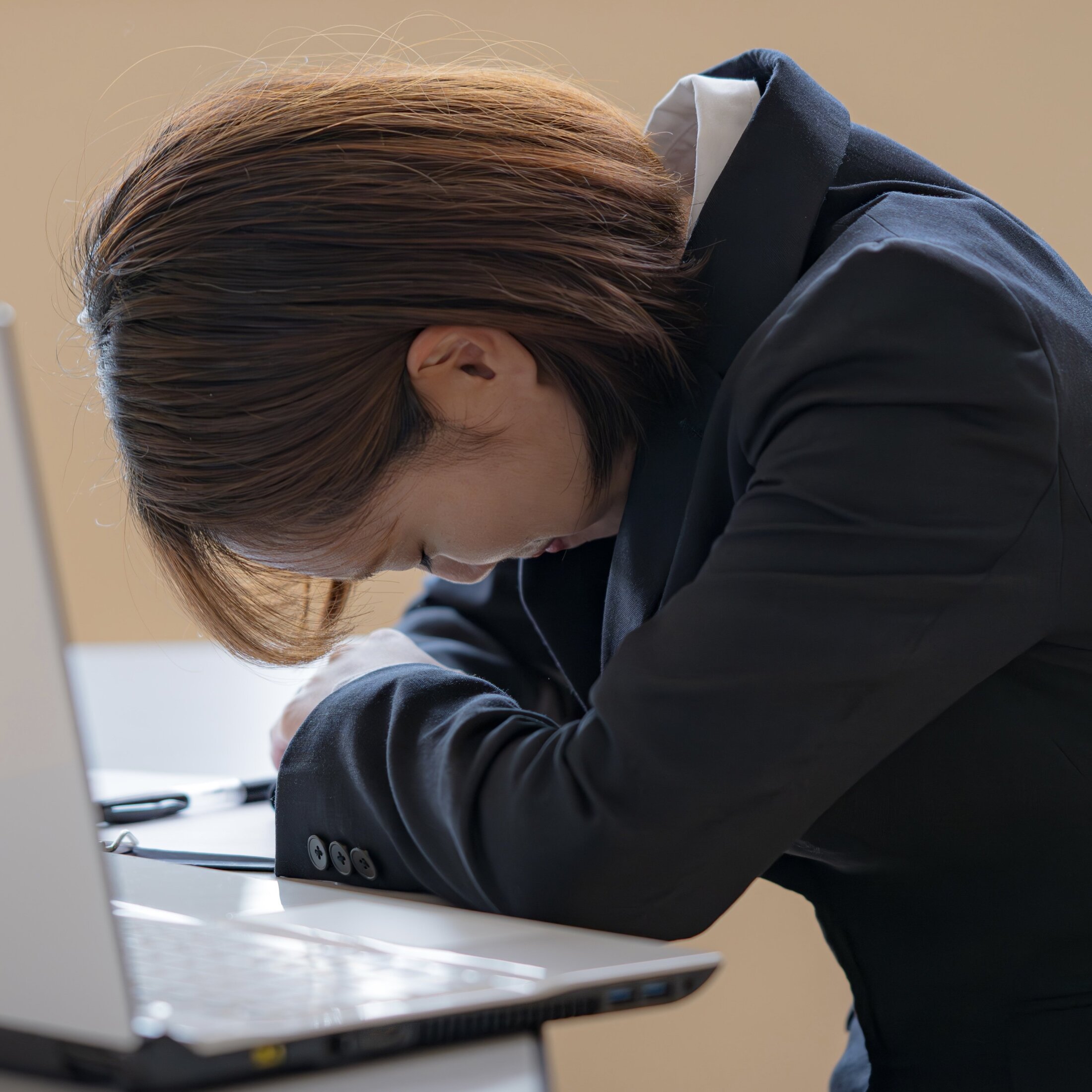 教師の多忙さに直面し、自信を失った教育実習生の言葉が話題となったSNS投稿のスクリーンショット
教師の多忙さに直面し、自信を失った教育実習生の言葉が話題となったSNS投稿のスクリーンショット
現場が語る「心が折れる」実習生の傾向と背景
福島県の公立中学校に勤務する教職歴15年の女性教師は、教育実習生の受け入れについて語ります。実習生の半数程度が実際に教職の道に進む印象がある一方で、「教師になるつもりで来たけれど、1年も続けられないと思いました」という直接の言葉を聞くことはないものの、実際に心が折れてしまう学生は少なくないと言います。
昨年、音楽科の実習に来た学生の一人は、3週目に入ったあたりで限界を迎え、「もう無理です、授業なんてできません」と控室に閉じこもってしまったことがありました。その学生は、同じ教科の別の実習生と比べて自分の実力に自信が持てなかったようです。
この女性教師は、教科に限らず近年は「打たれ弱い子」が増えていると感じており、特に真面目で完璧主義なタイプが精神的にしんどくなりやすい傾向があると指摘します。自分に厳しく、反省しすぎてしまうことで、気持ちがいっぱいいっぱいになってしまうというのです。教育実習では2~3週目に入ると、教材研究、授業実践、反省、再準備というサイクルが本格化し、この業務量の多さが学生の心理的負担を増大させている現状が浮き彫りになっています。
「先生ってこんなに忙しいんですね」:実習生が直面する教師の多忙な現実
教育実習生が現場で最も強く抱く印象の一つは、「先生ってこんなに忙しいんですね」という声です。指導教員を中心に分担したり、実習生の様子に応じて任せる量を調整したりと、受け入れ側も工夫を凝らしていますが、時期的な厳しさも相まって、教師の多忙さは隠しきれない現実として実習生に突きつけられます。
クラス替え直後の4~5月や、受験を控えた3年生への対応、さらには1・2年生のトラブルも多く、教員側も余裕がない中で実習生を迎えることになります。この現場の多忙さが、教職という仕事の「リアル」として、学生たちの目には非常に重く映るのです。
受け入れ側教員の苦悩:指導と業務の板挟み
教育実習生の指導は、受け入れる側の教員にとっても大きな負担となり、消耗してしまう現実があります。大学からの要請内容は大学によってバラバラで、指導案の細かさや提出物の量にも大きな差があると言います。「やらせたくないけど、やらせざるを得ない」という場面や、「任せた分、結局フォローも必要」となるケースも多く、実習生の指導と自身の通常業務とのバランスを取ることは非常に難しいと教師は語ります。
このように、教育実習は、教職を志す学生にとって理想と現実のギャップを痛感する場であると同時に、受け入れ側の教員にとっても多くの課題を抱える期間となっています。
結び
教育実習の現場で、学生がわずか2週間で教職の夢を諦めるという現象は、日本の教育現場が抱える根深い問題、特に教師の過重労働とそれに伴う「教職離れ」の深刻さを明確に示しています。多忙な教師の現実、そして繊細な学生の傾向が重なり合うことで、次世代の教師が育ちにくい環境が生まれています。この問題は、単なる個人の適性の問題ではなく、教育システム全体の課題として、社会全体で向き合うべき喫緊のテーマと言えるでしょう。教育現場の持続可能性と、未来を担う子どもたちへの影響を考えると、教員の働き方改革や、教育実習のあり方を含めた抜本的な見直しが求められています。






