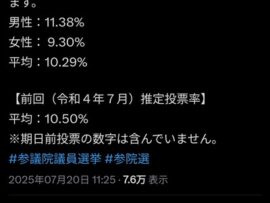2023年のOECD統計によると、日本の1人当たり労働生産性は主要先進国の中でも34位と低迷しており、その原因は多岐にわたるとされています。この状況を打破し、国際競争力を高めるため、ドイツの労働文化から学ぶべき点が数多く指摘されています。幼少期を含めドイツ在住通算17年の経験を持ち、著書『9割捨てて成果と自由を手に入れる ドイツ人の時間の使い方』で知られる松居温子氏は、ドイツの高い労働生産性の根源として「上司に忖度する必要がない」という点を強調しています。本記事では、ドイツのユニークな職場環境、人材育成、評価システムが、いかに効率的な働き方と高い生産性を支えているのかを深掘りし、日本への示唆を探ります。
「忖度不要」なドイツの評価と昇進システムが生産性を高める
日本企業の職場では、上司への忖度が企業文化に深く根付いており、自身の評価や出世を気にするあまり、不必要なサービス残業をしたり、会議の場で上司と異なる意見を述べることを避けたりしがちです。このような行動は、個人の創造性や建設的な提案を抑圧し、結果として会議に出席しても何も発言しなければ、その時間の生産性は実質ゼロに等しい状態となることが少なくありません。これが日本の労働生産性を低下させる大きな一因であると考えられます。
しかし、ドイツの職場環境では、松居氏が指摘するように上司への「忖度」がほとんど存在しません。その最大の理由は、従業員の評価や昇進が上司の主観的な判断や人間関係に依存せず、客観的で透明性の高いシステムに基づいているためです。例えば、ドイツでマネジャークラスへの昇進を望む場合、単に勤続年数を重ねるのではなく、特定の専門研修を受け、厳格な試験に合格することが必須とされます。これにより、マネジャーとしての正式な資格が認定され、その職務と責任に見合った給与が支払われる仕組みが確立されています。
 ドイツでの昇進は人間関係に左右されず、研修と試験で決まる様子。フランクフルト近郊のカール湖にて。
ドイツでの昇進は人間関係に左右されず、研修と試験で決まる様子。フランクフルト近郊のカール湖にて。
具体的には、「専門性+リーダーシップ研修」といった専門プログラムを通じて、従業員は自身の専門知識を深めるとともに、チームを効果的に率いるためのリーダーシップスキルを体系的に習得します。これらのスキルと実務における実績が直接的に個人の評価に繋がり、仕事内容、責任範囲、そして給与の向上へと直結するのです。大規模な企業には社内研修制度が設けられていることもありますが、多くの場合、社外の専門機関で研修を受け、国家資格として認定されるケースも多く、人間関係や出身大学の学閥といった要素がキャリアパスに影響することは基本的にありません。
このような徹底した実力主義と透明性の高い評価システムは、ハラスメントの発生を抑制する効果も持ちます。もし部下が上司からの不当な圧力を感じた場合でも、相談できる独立した仕組みや部署が整備されており、安心して声を上げられる環境が整っています。そのため、ドイツ人が日本のパワハラやアカハラといった問題を聞くと、彼らの職場文化では考えられないこととして非常に驚くのは当然と言えるでしょう。このシステムこそが、従業員の自律性と高い生産性を支える基盤となっています。
「即戦力」を重視するドイツの採用とデュアルシステム
最近の日本では、「この会社に入ったら何を学ばせてくれますか?」と企業に問う就職活動生もいると聞きますが、これはドイツでは考えられない問いかけです。ドイツの企業が求めるのは、入社後すぐに貢献できる「即戦力」だからです。
そのため、ドイツの大学生は、在学中から積極的にインターンシップに参加し、企業での実務経験を積みます。単に学業成績を追求するだけでなく、「こんな会社でインターンシップを経験した」「こんな技術や専門スキルを持っている」といった具体的な実績と経験をアピールすることが、就職を成功させるための重要な鍵となります。
日本では新入社員を時間をかけて育成する文化が根強く、新卒者はゼロから教育されることが一般的ですが、その育成期間中は当然ながら生産性が低いという課題を抱えています。対照的にドイツでは、大学教育に通わずとも、高校卒業後に企業に就職し、研修生として働きながら並行して職業学校で学ぶ「デュアルシステム」という独自の教育制度が社会を支えています。
このシステムを通じて、若者は特定の職種における実践的なスキルと理論を同時に習得し、プロフェッショナルとして社会に出るため、ドイツの企業は各分野の専門性を持ったスペシャリスト集団によって構成されていると言っても過言ではありません。何らかの専門スキルを身につけた上で管理職を目指す場合には、そのためのマネジメントスキルやリーダーシップスキルを習得し、マネジャーとしての職務を得るといった、非常に明確で段階的なキャリアパスが描かれています。
ドイツの少子化対策と柔軟なキャリア形成
日本と同様に、ドイツも少子化による労働力不足に直面しており、ドイツ連邦統計庁によると2023年6月現在の人口は約8500万人と日本より少ない状況です。しかし、ドイツはこれに対し、多角的なアプローチで対応しています。その一つが、海外からの優秀な人材を積極的に受け入れるための制度構築です。
さらに、技術革新、特にIT化の進展により、多くの分野で人手が不要になる傾向が見られます。例えば、製造業では製品の組み立てや検査工程がロボットに任されるようになり、ロボットを扱う専門家は必要ですが、直接製品を作る労働者の数は減少しています。
ドイツでは、このような技術革新によって職務が不要となるであろう人材に対しては、早期に解雇するという決断が下されることがあります。しかし、これは単なる人員削減に留まりません。解雇された労働者には最長2年間の失業保険が給付されるほか、「再訓練制度(ヴァイタービルトゥング)」などにより、これまでの経験とは全く異なる新たな職種で働けるようになるための集中的な職業訓練が提供されます。
実際に、自動車製造工場で働いていた方がITエンジニアにキャリアチェンジするなど、全く異なる分野への方向転換は珍しいことではありません。このような柔軟な労働市場と手厚い再教育・再就職支援システムが、ドイツ社会の活力と労働生産性を維持する上で重要な役割を果たしています。
結論
ドイツの労働生産性の高さを支えているのは、「上司への忖度不要な実力主義に基づく評価制度」と、「即戦力を育成し、社会の変化に柔軟に対応できるキャリア形成の仕組み」であると言えます。専門性を追求し、人間関係ではなく個人の能力と実績が公正に評価される文化、そして、技術革新や市場の変化に応じて労働者が新たなスキルを習得し、必要であれば大胆なキャリア転換も可能にする手厚いサポート体制は、日本の持続的な労働生産性向上を考える上で、非常に重要な示唆を与えてくれるでしょう。
出典: Yahoo!ニュース (FRIDAYデジタル)