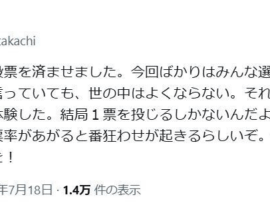韓国を中心に急速に広まった「習近平失脚説」は、2025年の中国理解に不可欠な現象だ。国外の「反中・反共産党」系YouTubeで始まり、今年に入ると韓国主要メディアでも注目されるようになった。その内容は、中国軍トップの張又侠中央軍事委員会副主席がクーデターを起こし、習近平国家主席から軍の統帥権を奪取、さらには胡錦濤前主席や温家宝元首相ら党長老が政治権力を掌握し、習主席は既に実権を失った「操り人形の指導者」になったという。5月には秘密拡大会議が開かれ、来月開催の共産党四中全会で習近平主席の退陣が公式決定されるとまで主張されている。
「習近平失脚説」の根拠と専門家の見解
中国最高指導部の内部動向は外部からはブラックボックスだ。しかし、中国の権力闘争を劇的に描く「習近平失脚説」は、好奇心を刺激しアクセス数を増やす一方で、多くの専門家が「根拠不明で、一部現象の誇張によるもの」と指摘している。
長年中国政治を研究するソウル大学国際大学院のチョ・ヨンナム教授は、「パシフィック・リポート」寄稿で、習近平主席が党の強力な整風運動や第15次五カ年計画策定を総括し、ドナルド・トランプ前米国大統領との電話会談を指揮、関税や先端技術交渉を統率していると分析。東南アジアや中央アジア訪問で首脳外交を行うなど、その権力は依然として堅固だと述べている。
中国政治評論家、鄧聿文氏も7日付「ドイチェ・ベレ」への寄稿で、もし習近平主席が権力闘争で失脚したならば、党の公式宣伝に必ず変化が見られるはずだが、そのような兆候はないと指摘。同氏によれば、権力弱化説の証拠とされる主張には説得力がない。例えば、娘の習明沢氏がベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領との面会に同行したことについて、反習近平勢力は「権力を失った習近平が娘の後事をルカシェンコに託した」と主張するが、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領ではなくベラルーシ大統領に託す理由はなく不合理だ。また、習主席の父親、習仲勲氏を顕彰する記念館が「関中革命記念館」として開館した件も、習仲勲氏の23周忌に合わせて墓近くに建てられたことを考慮すれば、権力弱体化の痕跡は全くないと分析している。
軍部人事と政策決定機構を巡る誤解
様々な解釈の余地がある状況が「習近平失脚説」に無理やり組み立てられ、陰謀論は拡大している。中国軍部から習近平主席が抜擢した苗華政治工作部主任や何衛東中央軍事委員会副主席らが相次ぎ失脚し、中央軍事委員会7人中3人が空席であることは、権力異常説の最大の根拠とされる。しかし、これは「(米国と)戦って勝てる軍隊」を作るため、軍内部の腐敗や派閥を徹底的に清算しようとする習近平主席の断固たる決意とも解釈できる。今後、四中全会での中央軍事委員会人事に注視が必要だ。
先月末の中国共産党政治局会議で「党中央意思決定議事調整機構業務条例」が審議されたという発表を、退任した元老指導者が政策決定に関与できる新機構設立と断定する主張も乱舞するが、その解釈は限定的であるべきだ。
「反習近平クーデター説」や「習近平失脚説」は今回が初めてではない。2022年9月末、第20回党大会直前にも同様の噂が広まったが、実際には党大会で習主席の3期目が確定し、最高指導部は習主席の忠誠派で構成され、習主席の権力は歴代最高に強化された経緯がある。
陰謀論の背景:政治的目的と拡散経路
2022年、2024~2025年に繰り返された「習近平失脚説」と「反習近平クーデター説」のフェイクニュースは、明らかに政治的目的を持って作成・拡散されたとみられる。「反中国共産党」指向の強い法輪功関連メディアであるエポック・タイムズやNDTで発生し、米国や台湾の反中YouTubeチャンネル、一部の「専門家」を経て拡散した。
特に、今年の「習近平失脚説」が米国と韓国だけで猛威を振るっている点は注目に値する。ゴードン・チャンやマイケル・フリンなど、失脚説を主導する米国内の著名人の中には、中国崩壊論や「韓国選挙介入説」を主張し、尹錫悦前大統領を支持した者も含まれる。彼ら米国の反中論客が「習近平権力異常説」を主張すると、韓国内の極右YouTubeチャンネルがそれを引用・増幅させる「無限循環ループ」が機能しているのだ。これは、「中国選挙介入説」に代表される極右嫌中陰謀論の土壌とYouTubeチャンネルが韓国社会に深く浸透し、「尹錫悦戒厳令」を機に米韓の極右勢力がさらに緊密化した結果と見られている。対照的に、日本では関連報道や世論の関心がほとんどない。
習近平政権における実際の変化の兆候
長期政権を続ける習近平主席の権力行使に「変化」のシグナルがないわけではない。昨年9月を境に、中国指導部は経済と改革開放を以前よりはるかに強調する「柔和路線」に舵を切っている。直前の7月の第20期三中全会と8月の北戴河会議を経て、この変化が始まったとみられる。習主席主導の厳格なゼロコロナ封鎖政策で打撃を受けた中国民間経済は、いまだ回復途上にある。先端技術分野での躍進は明確な現実だが、失業、民間消費の低迷、デフレ、生産過剰、不動産停滞などへの不満と不安も高まっている。民間経済の困難を背景に、習主席も安全保障一辺倒ではなく、成長を重視する方向へ政策調整をせざるを得なくなったと読み取れる。
2つ目の変化は「李強首相の浮上」だ。前任者の李克強首相に比べ存在感が薄かった李強首相だが、最近その存在感が注目されている。今月初めにはブラジルで開催されたBRICS首脳会議に習近平主席の代理で参加した。米シンクタンク「アジア・ソサエティー」の中国政治アナリスト、ニル・トーマス氏は先月、「フォーリン・ポリシー」で「李強の静かな浮上」と題し、習近平主席が最近経済セクターを李強首相に委任していると分析。最終意思決定権は習主席が掌握するものの、日常的な政策決定は信頼する李強首相に任せる方向へ変化しているという。72歳の習主席がこれまでのように経済・外交・安全保障の全ての実務に直接関わるのは困難であり、負担軽減や問題発生時の責任分担も考えられる。しかし、李強首相の権限は徹底して習主席に従属している。
BRICS首脳会議に李強首相が参加した7日付の人民日報1面には、李強首相とブラジルのルーラ大統領が手を取り合って笑む写真と記事が掲載されたが、トップ記事は「習近平生態文明選集」出版のニュースだった。習近平思想の学習と習主席を核心とする党の団結を強調する内容が、1面トップと2面全面にわたって扱われており、習主席の第一人者の地位が揺るぎないことを示している。
 人民日報の一面に掲載された李強首相と習近平生態文明選集の記事
人民日報の一面に掲載された李強首相と習近平生態文明選集の記事
今後の注目点:健康と後継問題
習主席の健康は注目すべき変数となりうる。13年間にわたり党・政・軍の絶対権力を掌握し、多くの委員会を管轄してきた習主席は激務をこなし、高齢化が進むにつれ、習主席の健康と後継問題が中国政局の主要課題として浮上するだろう。今年初めてBRICS首脳会議に習主席が参加せず李強首相を代理参加させたことで、健康不安説が再浮上した。米国や台湾では習主席が心臓病や脳卒中などを患っているという主張が広まっている。2027年の第21回党大会で習主席が4期目に就任するのか、どのような後継の構図を反映した最高指導部を構成するのかなどが、熱い問題になるだろうが、現在の噂のような突然の権力喪失の形には、おそらくならないだろう。
韓国社会全体が「習近平失脚説」に過度に没頭するのは危険なシグナルだ。見たくない中国の現実を避け、「望みのままの中国」に逃避する人々が非常に多い。不安定な中国、間もなく退く指導者との外交に注力する必要がないという意図も陰謀論の背景にある。もし習近平主席が「操り人形の指導者」になったとすれば、なぜ米国のトランプ前大統領は、習主席との首脳電話会談や首脳会談を成功させようと奔走しているのだろうか。今こそ、慎重かつ冷徹な中国観察が急がれる時期だ。
参考文献
- ハンギョレ (Hankyoreh)
- パシフィック・レポート (Pacific Report)
- ドイチェ・ベレ (Deutsche Welle)
- フォーリン・ポリシー (Foreign Policy)
- アジア・ソサエティー (Asia Society)