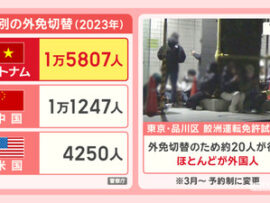教育サービス大手のベネッセコーポレーション(岡山市)が、35歳以上の社員を対象とした希望退職の募集を開始しました。しかし、この動きに対し、現役社員からは「企業理念とはおよそかけ離れた陰湿なリストラだ」との悲痛な声が上がっています。一見すると自主的な退職支援に見えるこの制度の背後には、社員が精神的・経済的な圧力を受ける実態があると言います。本記事では、このベネッセの希望退職募集の背景と、社員が経験する退職勧奨の具体的な手口に迫ります。
募集の概要と対象者
今回の希望退職募集は、管理職を除く一般社員およそ450人、これは全社員約3500人の13%に相当する規模で行われています。対象は35歳以上の社員に限定されており、割増退職金が支給される条件が提示されています。具体的な金額は勤続年数などによって変動しますが、社員が基本利用している退職金の前払い制度の加算分を含め、500万円から800万円が相場だとされています。この早期退職優遇制度は、一見すると魅力的にも見えますが、その実態は大きく異なるようです。
 ベネッセコーポレーションの企業ロゴと本社ビル外観。希望退職募集と関連する労使問題の背景を示す。
ベネッセコーポレーションの企業ロゴと本社ビル外観。希望退職募集と関連する労使問題の背景を示す。
社員の証言:心理的圧力と“いばらの道”
同社社員の須山聡志氏(40代・仮名)は、憔悴した面持ちで今回の退職勧奨の実態を語ります。須山氏によると、6月初旬に行われた最初の面談で、自身が希望退職の対象者であることが告げられ、割増退職金の条件が提示されたといいます。年収約700万円の須山氏は、早期退職後の将来設計が描けず、募集に応じない意向を伝えました。
しかし、須山氏が応募を拒否した途端、状況は一変します。以降、毎週のように直属の上司と1対1で30分にわたる面談がセッティングされるようになりました。面談の席では、上司から「残ってもいばらの道だと思いますよ」や「今後は人が減る半面、仕事量は増える。要求ハードルも高くなり、その結果、評価が下がって年収は減る可能性がある」といった、心理的なプレッシャーをかける発言が繰り返されたといいます。須山氏は、面談が終わるたびにひどく気分が落ち込んだと明かします。さらに、最初の面談直前のオンライン朝礼で、創業者である故・福武哲彦の「人・金・物・時間のムダを省く」という金言が紹介されたことが、多くの社員にとって退職勧奨の始まりを予感させるきっかけとなったそうです。
子会社への転籍と繰り返される質問
希望退職に応じない意思を示し続けた須山氏に対し、会社側はさらなる手を打ってきました。「介護事業のほうで人が足りていないから、そちら(関連子会社)に転籍になる可能性がある」と告げられたのです。子会社への転籍となれば、給料は現在の3割ほど下がるとされ、経済的な負担増は避けられません。それでも須山氏が首を縦に振らないでいると、その後の面談では「1週間経ちましたが、気持ちに変化はありませんか?」と同じ質問が繰り返し浴びせられるようになりました。この執拗な「圧迫面談」を通じて、須山氏は会社が本気で自分を辞めさせたいのだとようやく理解したと言います。同僚の中には、この延々と続く面談に音を上げ、会社が募集と同時に発表した再就職支援制度を利用して転職を決意した者が少なくなかったと報じられています。
まとめ
ベネッセコーポレーションの希望退職募集は、表面上は社員の新たなキャリアを支援する制度として提示されていますが、実態としては特定の社員に対する執拗な退職勧奨が行われていることが、現役社員の証言から浮き彫りになりました。特に35歳以上の一般社員が直面しているのは、心理的圧力と経済的損失を示唆する言動による「いばらの道」の提示です。創業者の企業理念と乖離したかのようなこれらの行為は、企業の社会的責任や労働環境のあり方を問うものです。今回の報道は、希望退職という名のリストラの闇を示しており、今後の日本企業の労使関係にも警鐘を鳴らす事例と言えるでしょう。
参考文献
- ベネッセ、35歳以上社員に「陰湿なリストラ」の悲痛な叫び – Yahoo!ニュース / デイリー新潮 (2025年8月8日)