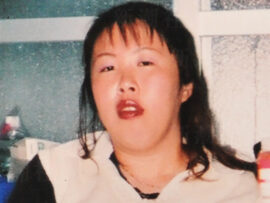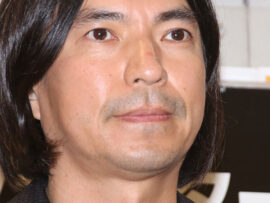「住みたい街ランキング」では決して上位に名を連ねないものの、実際に住む人々からは絶大な支持を得ている「住み心地抜群」の街が東京には存在します。本連載では、そうした知られざる魅力を持つ街を訪れ、その実態と住人の声、そして各種データを基にリポートしています。今回焦点を当てるのは、典型的な「住宅街型商店街」の代表格である「砂町銀座商店街」。駅から遠いという一見「不便」な立地が、いかに独自の魅力と活気を生み出しているのか、その理由を探ります。
日本の商店街を形成する三つの「型」
街歩きを通じて日本の商店街を観察すると、大きく三つの「型」に分類できることが分かります。一つ目は、駅に直結し、交通の要衝としての利便性を最大限に活かした「駅直結型」商店街。通勤・通学客が日常的に利用しやすく、常に賑わいを見せます。二つ目は、浅草の仲見世商店街に代表されるような、特定の観光地と結びついた「観光地型」商店街です。これらの商店街の集客力は、隣接する観光地の魅力に大きく左右され、季節やイベントによってその活気が変化します。そして三つ目が、今回取り上げる砂町銀座商店街のような、駅から少し離れた住宅街に形成された「住宅街型」商店街です。
 活気あふれる平日の昼間の砂町銀座商店街の風景。江東区の地域密着型商店街の魅力
活気あふれる平日の昼間の砂町銀座商店街の風景。江東区の地域密着型商店街の魅力
戦後復興と東京の商店街発展の背景
日本の首都・東京は、戦後の復興期から高度経済成長にかけて、全国から集まる労働者を受け入れるために急速な都市化を経験しました。1920年の国勢調査で約370万人だった東京の人口は、第二次世界大戦終結の1945年には349万人まで減少したものの、戦後の復興とベビーブームにより、わずか5年後の1950年には628万人へと急増します。そして、経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言された1956年には、その人口は約835万人に達しました。
このような急激な人口増加に対応するため、焼け野原となった東京の住宅地には、限られた土地に多くの住宅が密集して建てられました。その結果、多くの住宅街では、向かいの店舗に声が届くほど道幅の狭い、親密な雰囲気の商店街が自然発生的に形成されていきました。砂町銀座商店街も、まさにこうした背景の中で発展を遂げた典型的な商店街の一つと言えます。
「駅徒歩20分」が育む砂町銀座商店街の独自魅力
砂町銀座商店街の周辺には、東京メトロ東西線の「南砂町駅(江東区新砂)」「東陽町駅(江東区東陽)」、都営新宿線の「西大島駅(江東区大島)」「大島駅(江東区大島)」といった複数の駅が存在します。しかし、どの駅からも商店街までは徒歩で約20分を要します。一見すると「駅からの距離」という不便さが目立ちますが、この「駅遠」という特徴こそが、砂町銀座商店街に独自のコミュニティと活気をもたらしているのです。
駅の近くに大型商業施設が発達しにくい立地だからこそ、地域住民は日々の買い物や交流の場として、この商店街に強く依存します。これにより、商店街の各店舗は地域密着型のサービスを展開し、店主と客との間に温かい人間関係が築かれています。この「不便さ」が逆説的に、住民の生活に深く根ざした、活気あふれる商店街を育む要因となっているのです。
結論
砂町銀座商店街は、「住みたい街ランキング」の指標とは異なる、地域に密着した温かさと利便性を提供しています。駅から遠いという立地が、かえって住民の生活に不可欠な存在となり、地域コミュニティの中心として機能する独自の魅力を生み出しています。日本の都市が均質化する中で、このような「駅遠」ながら「住み心地抜群」な住宅街型商店街は、真に豊かな暮らしのヒントを与えてくれるでしょう。