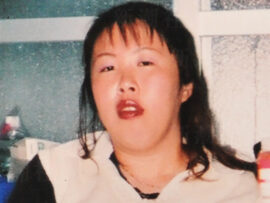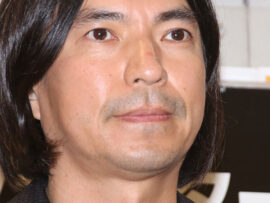近年、日本各地で深刻化するクマ被害。中でも、冬ごもりをしない「穴持たず」と呼ばれる個体は、その極めて凶暴な性質から特に注意が必要です。専門家は、通常のクマとは一線を画すその凶暴性を指摘。歴史を紐解けば、明治時代の北海道で発生した「札幌丘珠事件」は、この「穴持たず」ヒグマがいかに恐ろしい存在であるかを現代に伝える、痛ましい教訓です。
冬ごもりをしない「穴持たず」ヒグマの特異な危険性
クマは通常、遅くとも12月中旬までに冬ごもりに入り、翌春まで活動を休止します。しかし、十分なエサの確保ができなかったり、適切な冬ごもり場所の喪失、あるいは一度入った穴を何らかの理由で放棄せざるを得ないなど、様々な要因で冬季間も山野を徘徊する個体が稀に存在します。これらが「穴持たず」と呼ばれるヒグマで、常に飢餓状態にあるため、通常のクマよりはるかに凶暴で攻撃的です。空腹感は彼らの行動を予測不能にし、人間への接近や襲撃のリスクを大幅に高める、極めて危険な存在とされています。
 雪山を徘徊するヒグマのイメージ写真。冬ごもりしない「穴持たず」ヒグマの危険性を暗示している。
雪山を徘徊するヒグマのイメージ写真。冬ごもりしない「穴持たず」ヒグマの危険性を暗示している。
明治期の惨劇「札幌丘珠ヒグマ事件」の概要
「穴持たず」ヒグマによる凶悪事件の代表例が、明治11年(1878年)12月に北海道で起きた「札幌丘珠ヒグマ事件」(以下、丘珠事件)です。北海道開拓使が置かれていた札幌府近郊で発生したこの事件は、当時の入植者を震撼させ、北海道の過酷な自然の脅威を象徴する出来事となりました。この惨劇により、幼児を含む4名が命を落とし、1名が重傷を負うという甚大な被害が出ています。事件の詳細な記録は少ないものの、犠牲者の遺体の一部が札幌農学校(現在の北海道大学)付属植物園に長らく陳列された経緯もあり、道民の間では長く記憶されることになりました。ノンフィクション作家で人喰い熊評論家の中山茂大氏も、自身の著書『神々の復讐』(講談社)でこの異常な事件を取り上げています。
八田三郎『熊』が描く真冬の夜の襲撃
丘珠事件に関する貴重な資料の一つが、北海道帝国大学教授の八田三郎が明治44年(1911年)に著した『熊』です。八田氏の記述からは、事件発生当夜、明治11年12月25日の状況が鮮明に浮かび上がります。激しい雪が降りしきる真冬の深夜、師走の忙しさから人々が安らかな眠りについていた丑の刻(午前1時から3時頃)。暗闇の室内で響く物音に気づいた倉吉は「誰だッ」と声を上げた途端、悲鳴を上げて襲われました。その悲鳴に夢うつつの妻女が目覚めると、日も経たぬ赤子を抱えた裸体の背中に「針の刷毛で撫でたようなザラッとした」感触が走ったと証言しています。この描写は、凶暴なヒグマの接近とその極限の恐怖を克明に伝えています。
結論
「穴持たず」ヒグマの脅威は現代も続いています。近年、環境変化や食糧不足が指摘される中、冬ごもりをしないクマの増加が懸念されます。札幌丘珠事件の教訓は、こうした特異な状況にあるヒグマの予測不能な凶暴性を忘れず、常に警戒を怠らないことの重要性を私たちに示唆しています。過去の惨劇から学び、適切な知識と対策を持つことが、今後の人身被害防止に不可欠です。
参考資料
- 中山茂大. (2020). 『神々の復讐』. 講談社.
- 八田三郎. (1911). 『熊』. (北海道帝国大学教授).
- 環境省. (2023). クマによる人身被害状況について.