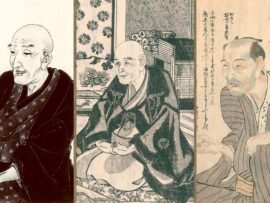1987年の正月、日本を代表する高峰の一つである北アルプス・槍ヶ岳の登頂を目指した3人の男性登山家が、猛吹雪の中、忽然と姿を消しました。彼らの行方は杳として知れず、山仲間や家族は、他のパーティーからの証言を基にその足跡を追い、推測を重ねる中で、やがて巨大な謎に直面することになります。本稿では、この未曾有の冬季遭難事故とその後の捜索活動に深く関わった当事者である泉康子氏の著書『いまだ下山せず! 増補改訂版』(宝島社文庫)から一部を抜粋し、その緊迫した始まりを紹介します。
捜索開始:木村小屋での緊迫したやり取り
1987年1月5日の午後、北アルプス南部遭難対策協議会の副会長を務める木村勝男が、自身の木村小屋の戸口に腕を組み、立ち尽くしていました。その日の朝、彼は槍ヶ岳、穂高岳、常念岳山域の山岳遭難対策を担当する豊科警察署から、槍ヶ岳を目指した3人組のパーティーが下山してこないため、仲間の捜索隊4名が上高地へ向かうので指導してほしい、という連絡を受けていたのです。
木村は、捜索隊がもうやって来る頃だろうと予想していましたが、登山者の多くが午前中に立ち寄り、入山届や下山届を提出するのに対し、午後2時半を過ぎてようやく登山姿の男たちが登ってきました。木村勝男は、この4人こそが捜索隊であると直感し、彼らに向かって厳しく問いかけました。「なんなんだ、なんなんだ!遅かったじゃないか。いったいどうしたっていうんだ」。最初から事情を優しく尋ねないのが、木村の常でした。
 1987年槍ヶ岳冬季遭難、捜索が開始された北アルプスの厳しい雪山のイメージ
1987年槍ヶ岳冬季遭難、捜索が開始された北アルプスの厳しい雪山のイメージ
「のらくろ岳友会」3名の行方不明者と第一捜索隊
木村の問いに、4人の男たちは身を固くしながら、「どうも、のらくろ岳友会です。お騒がせしますが、どうかご指導ください」と、次々と頭を下げました。行方不明となっていたのは、「のらくろ岳友会」に所属する三枝悦男氏(仮名・当時30歳)、宮崎聡司氏(同28歳)、橋本正法氏(同25歳)の3名でした。彼らは1986年12月28日に槍ヶ岳を目指し縦走に出発しましたが、予備日を過ぎても下山連絡がなく、遭難が強く懸念されたのです。
のらくろ岳友会冬季合宿の留守本部を引き受けていた杉本茂氏は、最終予備日である1月4日になっても3人からの下山連絡がないことを受け、会員に招集をかけました。その結果、第一捜索隊として現場に急行したのは、会の古参メンバーである前代表の宮下真史氏、杉本茂氏自身、近澤亘氏、片山光広氏の4名です。彼らは予備日が切れる1月4日の夜に東京を出発し、翌5日の早朝には杉本茂氏の名で豊科警察署に正式な捜索願を提出。警察の指示に従い、行方不明の3人が下山予定としていた上高地へと転進してきたのでした。
この日、木村小屋で交わされた緊迫のやり取りは、北アルプスを舞台とした大規模な捜索活動の幕開けを告げるものでした。冬の槍ヶ岳で消息を絶った3人の登山家を巡る物語は、ここから本格的に動き出すことになります。
参考文献:
泉康子『いまだ下山せず! 増補改訂版』(宝島社文庫)