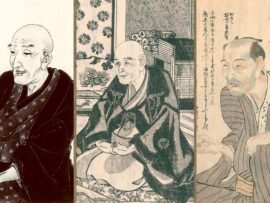2026年のNHK大河ドラマが豊臣秀吉・秀長兄弟の立身出世を描くことが決定し、再び歴史ファンの注目を集めています。しかし、秀吉の名前が信頼できる史料に現れるのは29歳になってからで、それまでの人生は多くの謎に包まれています。一体、天下人となる前の秀吉はどのような青年期を過ごしていたのでしょうか。本稿では、一般に語られる彼の若き日の逸話と史実の狭間を探ります。
父を失い、流浪の身へ:伝承と史実の狭間
豊臣秀吉が織田家に仕えるまでの活動については、確たる史料が不足しています。秀吉の死後、約半世紀を経て書かれた『太閤素生記』には、彼の放浪時代の詳細が記されていますが、これは創作の要素が多く、史実として鵜呑みにすることはできません。
伝承によれば、天文12年(1543年)に父を亡くした秀吉は、幼くして寺の小僧に出されますが、その生活に馴染めずすぐに家に戻ったとされます。その後、遠江、三河、尾張、美濃の四カ国を渡り歩き、様々な職を転々とする流浪の身となりました。天文20年(1551年)、15歳で実家に戻ると、母から亡父の遺産である1貫文(現在の価値で約10万円)を受け取り、再び家を出て清須の町で針を買い、それを売りながら東海道を東へ旅したと言われています。また、三河の矢作川の橋の上で野盗の親分とされた蜂須賀小六(正勝)と出会ったという有名な伝説もこの時期のこととされますが、これは江戸時代になってからの創作と考えられています。
 豊臣秀吉の肖像画、京都高台寺所蔵の重要文化財の一部
豊臣秀吉の肖像画、京都高台寺所蔵の重要文化財の一部
松下家への仕官と”恩返し”の真実
東海道を下り、遠江に辿り着いた秀吉は、駿河今川家の家臣で遠江頭陀寺城主であった松下家に仕えることになります。このとき仕えたのは「松下加兵衛(之綱)」とされていますが、秀吉と同年齢であるため、実際にはその父である「松下長則」であった可能性が高いとされています。
秀吉は松下家で草履取りとして雇われた後、その才気が認められ、主人の身の回りの世話をする側近である納戸役へと出世しました。しかし、秀吉の異例の出世を快く思わない他の奉公人たちからのいじめを受け、17歳(または天文5年生まれの場合は18歳)のときに松下家を出奔し、故郷の尾張へと帰ったと伝えられています。後年、秀吉は天下人となってから、かつての主人である松下之綱を召し抱え、1万6千石もの所領を与えました。この行為は、青年期に世話になった松下家への「恩返し」の意味合いが強かったと考えられています。
結論
豊臣秀吉が織田信長に仕える前の青年期は、確たる史料が少ないために多くの謎に包まれています。後世に記された『太閤素生記』のような伝記は、彼の波乱に満ちた人生を劇的に彩る一方で、創作の要素も含まれており、史実との峻別が求められます。しかし、松下家での「草履取り」から始まったとされる彼の奉公と、後の「恩返し」の逸話は、たとえ脚色が含まれていたとしても、貧しい出自から天下人へと駆け上がった秀吉の人間性と、彼が大切にした人との繋がりを示す象徴的なエピソードとして、今なお多くの人々に語り継がれています。
参考文献
- 黒田基樹監修『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』(宝島社新書)