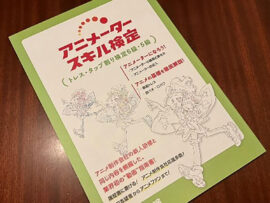今年、日本全国でクマによる人的被害が深刻化しており、11月12日時点で死者数は過去最悪だった昨年度の2倍を超える13人に達しました。なぜこれほどまでに人を襲うクマが急増しているのでしょうか。新潟県村上市の山熊田というマタギ集落で暮らす大滝ジュンコさんの証言から、この異常事態の背景を探ります。彼女の夫であるベテランマタギは、「50年近くクマ狩りを続けているが、もはやマタギの常識が通用しないクマが増えた」と語っています。
なぜ市街地にクマが出没するようになったのか
新潟県村上市では、近年、クマの目撃情報が住民アプリを通じて頻繁に報告されており、その件数は過去最多を記録しています。昨年までは1日に1件でも話題になるほどでしたが、最近では10件もの情報が寄せられる日も珍しくありません。
食料不足がクマを市街地へ駆り立てる
この秋、山ではクマの主要な食料となるブナの実が大凶作に見舞われています。エサが極めて乏しい状況が、クマたちを山から人里へと押し出している大きな要因です。村上市の中心部を流れる三面川は、クマがエサを求めて河川敷を歩き、山から町中へ下りてくる経路となっています。このため、山間部から離れた海に近い町や集落でも、クマの出没が頻繁に確認されています。
縄張り争いとクマの生態変化
村上市は、海に近い浜側と内陸の山間部の二つの地域に分けられます。以前は、浜側に出没するクマは体長1メートルに満たない小型の個体が多かったといいます。これは、縄張り争いに敗れた若いクマが、エサの豊富な山から追い出され、町に現れるケースが多いと考えられていました。
しかし、近年ではその傾向にも変化が見られます。数年前の夏には、町に出没して罠にかかったクマをマタギたちが仕留め、解体したところ、胃の中には葉っぱしか入っていませんでした。これは、食べるものがなく、飢餓状態にあったことを示しています。通常、猟期に捕獲されるクマの胃はキノコ類、果物、木の実、昆虫などで満たされており、身体も大きく健康な状態であることが一般的です。この事例は、山林での食料不足がいかに深刻であるかを物語っています。
 2025年4月27日、長野県飯田市で撮影されたツキノワグマ
2025年4月27日、長野県飯田市で撮影されたツキノワグマ
異常なクマの行動と共存への課題
クマの生態系が大きく変化し、食料不足から市街地への出没が増える現状は、これまでの「マタギの常識」が通用しない新たな局面を迎えています。人身被害を防ぐためには、クマの出没地域での警戒強化はもちろんのこと、彼らの生息環境の変化を理解し、人間と野生動物が安全に共存できる方策を模索していくことが急務となっています。
参考文献:
Source link