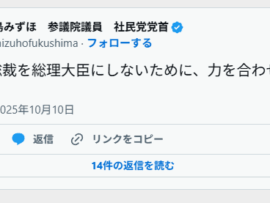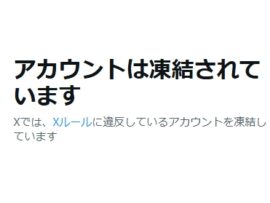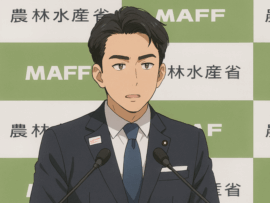江戸時代に「メディア王」と呼ばれた蔦屋重三郎。吉原で生まれ育った彼は、類まれなるプロデュース力で浮世絵師や戯作者たちを支え、数々の名作を生み出しました。本記事では、重三郎の足跡を辿りながら、彼がプロデュースした奇書『娼妃地理記』と、その作者である朋誠堂喜三二の悲劇的な最期に迫ります。
吉原を舞台にした、重三郎の挑戦
吉原で書店を営んでいた重三郎は、集客のために様々な工夫を凝らしていました。安永3年(1774年)、彼は初めての本『一目千本』を出版。人気絵師・北尾重政に絵を依頼し、花魁たちを花に見立てて紹介したこの本は、大きな話題を呼びました。
 一目千本のような遊女評判記は、当時の吉原の様子を今に伝える貴重な資料となっています。(イメージ)
一目千本のような遊女評判記は、当時の吉原の様子を今に伝える貴重な資料となっています。(イメージ)
翌年には『急戯花之名寄』を刊行。遊女の紋が入った提灯と桜を組み合わせ、それぞれの魅力を伝える短い評を加えました。これらの本は、掲載を希望する遊女や馴染み客からの出資によって作られたと考えられています。
朋誠堂喜三二との出会い、そして『娼妃地理記』の誕生
2冊の遊女評判記を経て、重三郎は読者をさらに楽しませたいという思いを強くします。そして安永6年(1777年)、戯作者・朋誠堂喜三二との運命的な出会いを果たします。
彼らが生み出した最初の作品が、『娼妃地理記』です。吉原の各町を国、遊女屋を郡、遊女を名所に見立て、まるで地理書のように吉原を紹介するという奇抜な発想で、読者を驚かせました。

喜三二は本書で「道蛇楼麻阿(どうだろうまあ)」というふざけた筆名を使用。そのユーモラスな作風は、多くの読者から支持を集めました。 江戸文化研究家の小林先生は、「『娼妃地理記』は、当時の吉原の文化や風俗を知る上で貴重な資料と言えるでしょう」と語っています。
老中・松平定信の怒りを買い、悲劇的な最期を迎える
しかし、この人気作は、幕府の改革を進めていた老中・松平定信の怒りを買ってしまうことになります。風紀の乱れを厳しく取り締まっていた定信は、『娼妃地理記』を風俗を乱すものとみなし、喜三二を厳しく処罰。喜三二は悲劇的な最期を迎えることとなりました。
まとめ:重三郎と喜三二、光と影
蔦屋重三郎は、数々の才能を発掘し、江戸の文化を大きく発展させた人物です。しかし、その輝かしい功績の裏には、朋誠堂喜三二のように、時代の波に翻弄された人々の存在がありました。重三郎と喜三二、二人の物語は、江戸文化の光と影を象徴していると言えるかもしれません。