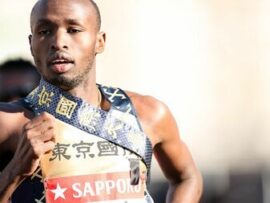PFAS(有機フッ素化合物)による環境汚染。長らく解決困難な問題とされてきましたが、実は解決策は存在します。本記事では、PFAS技術対策コンソーシアム会長であり、産業技術総合研究所の上級主任研究員である山下信義氏へのインタビューを基に、日本のPFAS汚染問題の現状と解決への展望を探ります。
日本のPFAS対策における「失われた15年」とは?
2009年、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)が規制対象に追加され、生産・使用が禁止されました。日本では2010年に化審法の対象となり、環境中の濃度は劇的に低下。一見、問題は解決したかに見えましたが、これは大きな誤解でした。
 PFAS汚染の現状を示すグラフ
PFAS汚染の現状を示すグラフ
海外ではPFOS規制を皮切りに、関連するPFASの規制検討が進んでいました。しかし、日本では2020年に沖縄の米軍基地から泡消火剤が流出する事件が起こるまで、対策は停滞。この「失われた15年」の間、日本は世界の流れから取り残されてしまったのです。
PFAS汚染解決への取り組み
山下氏は、この現状を打破すべく、産業技術総合研究所内に「PFAS対策技術コンソーシアム」を設立。PFAS対策に取り組む企業、行政、研究機関に対し、測定・分析から汚染浄化まで、環境修復に関する相談や情報提供を行っています。
コンソーシアムの会員数は現在80団体に達し、その活動は大きな反響を呼んでいます。当初、PFOS汚染の環境修復は不可能と考えられていましたが、山下氏らが海外の成功事例を紹介したことで、状況は大きく変わりつつあります。
なぜ「解決策はない」と思い込んでいたのか?
日本では長らく、PFAS汚染の解決策はないという思い込みが蔓延していました。なぜこのような誤解が生じたのでしょうか?山下氏は、その理由を問いかけます。
実は、PFAS汚染の浄化技術は既に存在し、海外では実際に活用されています。日本の停滞は、情報不足と意識の低さが原因と言えるでしょう。
未来への展望
PFAS汚染問題は、決して解決不可能な課題ではありません。コンソーシアムの活動を通じ、情報共有と技術開発が進めば、日本でもPFAS汚染のない未来を実現できるはずです。重要なのは、問題意識を持ち、積極的に解決策を探ることです。
まとめ:PFAS汚染問題解決への一歩を踏み出そう
本記事では、日本のPFAS汚染問題の現状と、解決に向けた取り組みについて解説しました。「失われた15年」を取り戻し、クリーンな環境を取り戻すために、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。