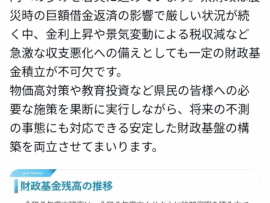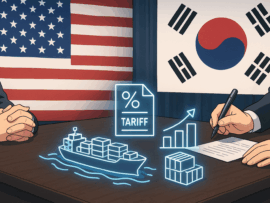サウナブームの熱狂が冷め始め、業界に暗い影が落ちているようです。新規出店が続く一方で、閉店を余儀なくされる施設も増加。ブームの波に乗り開業したものの、短期間で撤退するケースや、老舗店でも新規客と古参客の摩擦が生じ、経営難に陥る事例も見られます。今回は、サウナブーム終焉の兆候と、その背景にある問題点を探ります。
閉店続出の現状
好立地でありながら閉店に追い込まれるサウナ施設も少なくありません。例えば、東京・浅草の中心地にあった個室サウナ「SAUNA RESET Pint」は、2022年の開業からわずか2年半で閉店。巨大施設でありながら集客に苦戦したようです。利用客からは、価格設定や施設の使い勝手、立地条件など、様々な点で改善の余地があったとの声が聞かれました。個室サウナは初期投資を抑えられるメリットがあるものの、一般的なサウナより高額になりがちで、原宿や大井町でも短期間で閉店するケースが報告されています。
 alt
alt
サウナ人口の減少
サウナブームの陰で閉店が相次ぐ背景には、サウナ人口の減少という深刻な問題があります。一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所の調査によると、2023年度のサウナ人口は1779万人。最多だった2019年度の2824万人から37%も減少しています。コロナ禍からの回復傾向は見られるものの、サウナブームのピークは過ぎたと言えるでしょう。
古参客離れの深刻な影響
新規顧客の増加が見られる一方で、古参客の離反も大きな問題となっています。サウナブームによってマナーの悪い利用客が増え、かつての常連客が足繁く通っていたサウナから離れていくケースも。古参客はサウナ文化を支える重要な存在であり、彼らの離反はサウナ業界にとって大きな痛手となります。「サウナ評論家の山田太郎氏」は、「古参客のサウナ愛は深く、施設への loyalty も高い。彼らを失うことは、サウナ文化の衰退に繋がる」と警鐘を鳴らしています。
サウナ業界の未来
サウナ業界が生き残るためには、新規顧客の獲得だけでなく、古参客の維持も重要です。快適なサウナ環境の提供、マナー啓発活動、顧客ニーズに合わせたサービス展開など、様々な取り組みが必要となるでしょう。また、過当競争を避けるため、地域特性を活かした差別化戦略も重要です。「温浴施設コンサルタントの佐藤花子氏」は、「地域密着型のサービスや、独自のイベント開催など、他店との差別化が成功の鍵となる」と指摘しています。
サウナブームの終焉は、業界にとって大きな転換期となるでしょう。この危機を乗り越え、持続可能なサウナ文化を築き上げていくためには、関係者全体の努力が不可欠です。