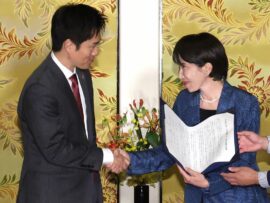美容医療の人気が高まる一方で、トラブルも増加傾向にあります。その背景には、経験の浅い若手医師が美容外科に就職する「直美」と呼ばれる現象が関係していると言われています。一体何が若手医師たちを美容外科へと駆り立てているのでしょうか?本記事では、この「直美」急増の背景にある医療界の課題を深掘りしていきます。
美容医療トラブル増加の謎
美容医療は通常の医療に比べてトラブルが生じやすい傾向があります。技術の進歩や需要の増加に伴い、美容医療全体の市場は拡大していますが、残念ながらトラブルも比例して増加しています。なぜこのような状況が改善されないのでしょうか?美容医療業界の自浄作用は機能していないのでしょうか?
若手美容外科医「直美」とは?
この状況を理解する上で重要なキーワードが「直美」です。直美とは、初期臨床研修を終えてすぐに、他の診療科や勤務先を経由せずに、直接美容外科に入職する若手医師のことを指します。近年、この直美が増加していることが大きな問題となっています。
美容外科医の年齢構成の変化
 20代美容外科医の増加を示すグラフ
20代美容外科医の増加を示すグラフ
2010年には20代の美容外科医はわずか5人でしたが、2022年には155人にまで急増しています。医学部を卒業後、初期臨床研修を終えると20代後半になるため、20代の美容外科医は、研修後すぐに美容外科に入職した医師ということになります。
従来のキャリアパスとの違い
従来、美容外科医になるには、初期臨床研修後に大学病院などで形成外科医としての経験を積み、一定の技術を習得した上で開業または入職するのが一般的でした。また、外科医など、過酷な労働環境から離れるために美容外科に転職するケースもありました。
美容外科への偏見
かつて美容外科はマイナーな存在であり、自由診療であることから、大学などではタブーとされる風潮がありました。2015年に医学部を卒業した救急医の中村龍太郎氏(仮名)は、「初期研修医の頃、美容医療に進むというと、『お金が欲しいの?』『何か特別な事情があるの?』といった見方をされることが多かった」と語っています。
なぜ「直美」が増えているのか?
では、なぜ近年「直美」が増加しているのでしょうか? 労働環境の改善や高収入といった魅力ももちろんありますが、それだけが理由でしょうか? 日本の医療制度、若手医師のキャリアプランの変化、美容医療業界の構造など、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。 例えば、医療ジャーナリストの佐藤美咲氏(仮名)は、「長時間労働や医師不足といった医療現場の厳しい現状が、若手医師を美容外科へと向かわせる一因となっている」と指摘しています。
今後の展望
「直美」の増加は、美容医療の質の低下やトラブルの増加につながる可能性も懸念されます。美容医療業界全体で、若手医師への適切な教育や研修制度の充実、再発防止対策の強化など、早急な対策が必要とされています。 患者側も、医師の経歴や経験、所属学会などを確認するなど、慎重にクリニックを選ぶことが重要です。
まとめ
「直美」の増加は、美容医療業界だけでなく、日本の医療界全体が抱える構造的な問題を反映していると言えるでしょう。より良い医療を提供するためには、医療関係者だけでなく、社会全体でこの問題について真剣に考え、解決策を探っていく必要があります。