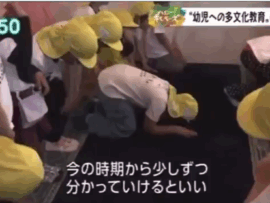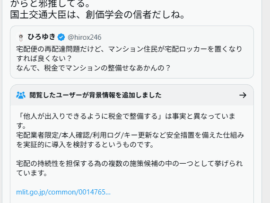神社のSNSアイコンに生成AIが使用されたことがきっかけで、大きな炎上騒動が発生しました。この出来事は、伝統と最新技術の衝突という現代社会の課題を浮き彫りにしています。今回は、車折神社の事例を通して、生成AIをめぐる問題点や今後の展望について考えてみましょう。
車折神社の炎上騒動:事の発端
京都の嵯峨野に位置する由緒ある車折神社。芸能の神様としても知られるこの神社が、2025年3月18日、SNSのアイコンに生成AIで作成された巫女のイラストを使用しました。これが、大炎上騒動の引き金となりました。
 車折神社の公式ウェブサイト
車折神社の公式ウェブサイト
生成AIは、既存の画像データを学習して新たな画像を生成する技術です。しかし、その学習過程で著作権や著作者人格権の侵害が懸念されており、クリエイターを中心に批判的な意見も少なくありません。
生成AIをめぐる賛否両論:クリエイターの声
生成AIについては、クリエイターの間でも意見が分かれています。否定的な意見を持つクリエイターは、生成AIによる著作権侵害や、人間の創造性の低下を懸念しています。一方、肯定的な意見を持つクリエイターは、生成AIを新たな創作ツールとして捉え、その可能性に期待を寄せています。
例えば、手描きのイラストレーターの中には、生成AIの普及によってアナログ技術への注目が高まっていると感じる人もいます。生成AIを脅威と捉えるのではなく、新たなチャンスと捉える視点も存在するのです。
炎上騒動の余波:過激化する批判と神社への脅迫
車折神社の炎上騒動は、SNS上で過激な批判へと発展しました。「芸術を冒涜している」といった非難の声が上がり、神社はSNSの運用停止に追い込まれました。さらに、一部の芸能人は、奉納した玉垣の取り下げを表明するなど、波紋は広がっています。
事態はさらに深刻化し、神社には殺害予告や放火予告を含む脅迫メールが殺到していることが明らかになりました。「死ね」「殺す」といった言葉に加え、炎の写真や凶器の写真が送られるなど、その内容は凄惨を極めています。
生成AIと社会の未来:冷静な議論の必要性
生成AIは、社会のあり方を変える可能性を秘めた技術です。だからこそ、感情的な批判ではなく、冷静な議論に基づいたルール作りが必要です。
著名な文化人類学者である山田太郎教授(仮名)は、「生成AIはあくまでもツールであり、使い方次第で大きな可能性を秘めている。重要なのは、技術の進歩と倫理的な観点をバランスさせ、健全な発展を促すことだ」と述べています。
生成AIの未来を考える上で、車折神社の炎上騒動は大きな教訓となるでしょう。私たちは、技術の進歩と伝統、そして人間の創造性との調和を図りながら、未来社会を築いていく必要があるのです。