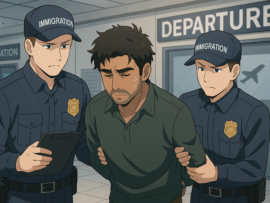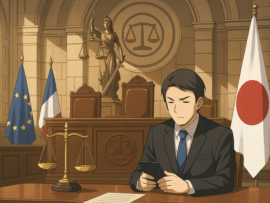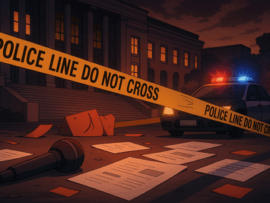「言語化力」は、目の前で起きている複雑な事象を瞬時に捉え、誰にでも分かりやすい言葉で表現する能力です。このスキルが高い人は、ビジネスシーンでのプレゼンテーションはもちろん、日常生活における人間関係の構築においても、円滑なコミュニケーションを実現できます。本記事では、教育学者の齋藤 孝氏が提唱する、言語化力を高めるための具体的なメソッドと、その実例をご紹介します。本内容は、齋藤 孝氏の著書『最強の言語化力』(祥伝社)の一部を基に構成しています。
 言語化力を磨くビジネスパーソンのイメージ
言語化力を磨くビジネスパーソンのイメージ
言語化力トレーニングの基本
言語化力を向上させる効果的なトレーニングの一つに、写真や絵などの視覚情報を言葉で表現する練習があります。これは、齋藤氏が小学生向けの授業やテレビ番組でも実践してきた方法です。
具体的なやり方は、まず一枚の絵や写真、または実物を5秒から10秒間じっくり見ます。次に、その対象を隠し、見た情報を基に30秒以内でどのようなものだったかを説明します。制限時間を設けることで、時間的制約の中で必要な情報を効率よく言語化する能力が鍛えられます。説明後、元の絵や写真と照らし合わせることで、自分の言語表現がどの程度正確に相手にイメージを伝えられたかを確認できます。視覚情報をゼロから言葉に変換するこのプロセスは、純粋な言語化スキルが問われる優れた訓練となります。
文豪・谷崎潤一郎に見る奥深い表現力
言語化力の豊かさを示す例として、文豪・谷崎潤一郎の表現が挙げられます。彼は「日本の料理は食うものではなく瞑想するものである」という言葉を残しており、その著書『陰翳礼賛』の中では、日本の和菓子である羊羹についてこのように述べています。
「玉(ぎょく)のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って夢みる如きほの明るさを啣(ふく)んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない」
谷崎は、羊羹という一つの和菓子から、その質感、光の透け具合、色の複雑さといった繊細な美しさを捉え、豊かな感性と卓越した言語化力をもって奥深く表現しています。これは、単に物事を説明するだけでなく、そこに込められたニュアンスや感情をも伝える言語表現の可能性を示しています。
具体的な描写トレーニングの実践
では、より実践的な描写トレーニングとして、ある特定の場面を言葉で説明する練習をしてみましょう。例えば、以下の図(図-5を想定)のような「散らかった部屋にいる男性」の絵を言葉で説明する場合、どのように表現できるでしょうか。会話での説明を想定するため、完璧な文章である必要はありません。
(※ここからは、元の文章にある図-5の説明例を参考に構成しています)
例えば、以下のような説明が考えられます。
「散らかった部屋に若い男性が一人、ソファに寝転がっていますね。寝ぼけたような顔をしていて、テレビはついたままですが『NO SIGNAL』と出ています。たぶん、映画か何かを見ながら寝落ちして、今目が覚めたところみたいです。床には紙ごみやいろんな物が散らかっていて、ビール瓶もいくつか転がっているので、お酒を飲んでそのまま寝てしまったんでしょうか。壁に掛かっている絵も時計も斜めになっていたり、花瓶の花が折れていたり、全体的に荒れています。男性は困ったような表情に見えましたが、片付けようという様子は感じられませんでした。部屋全体が、彼の内面を表しているような感じがしましたね。」
このような説明であれば、20秒から30秒程度で十分に内容を伝えられるでしょう。もし1分間といった長い時間制限がある場合は、「床にはたくさんの本が積み重なっていた」「だらしないけど、アートを飾る気持ちはあるんだな」「クマのぬいぐるみも転がっていたよ」「折れた花は白いガーベラみたいだった」「部屋の中で靴を履いていたから、外国人かもしれないね」といった、より詳細な情報や推測、具体的な物の描写を加えることで、尺に合わせて説明を深めることができます。
まとめ
言語化力は、日々のトレーニングによって確実に向上させることができるスキルです。視覚情報を言葉にする練習や、身の回りの出来事を意識して言葉で表現する訓練を積み重ねることで、思考が整理され、相手に正確かつ魅力的に物事を伝える力が磨かれます。この力は、仕事での成果はもちろん、プライベートでの豊かな人間関係を築く上でも、かけがえのない財産となるでしょう。齋藤孝氏のメソッドを参考に、ぜひ今日から言語化力を鍛える習慣を始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献:
- 齋藤 孝『最強の言語化力』(祥伝社)
- Source link