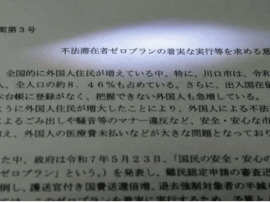2024年の衆議院選挙で与党が過半数を割る異例の事態となったにも関わらず、国民が期待した消費減税や「178万円の壁」実現に向けた所得税・住民税の大幅な人的控除拡大は見送られました。今年1月に逝去された経済アナリスト、森永卓郎氏は生前、「政治家の保身こそが、国民の手取りを増やす最大の阻害要因である」と強く訴えていました。今回は、森永氏の著書『保身の経済学』で指摘された、減税が実現しない背景にある政治力学とその真相に迫ります。
現実の税制改正大綱と評価
2024年12月20日に決定された与党の税制改正大綱では、国民民主党が求めていた「103万円の壁」見直しに関連し、人的控除を20万円引き上げることが盛り込まれました。しかしこれは、国民民主党が当初要求した75万円の引き上げからは大きくかけ離れた小幅なものです。具体的には、基礎控除10万円、給与所得控除の最低保障引き上げ10万円の内訳であり、年収300万円の会社員の場合、年間減税額は地方税を含めてもわずか5000円程度にとどまります。国民民主党の要求通りであれば年間11万3000円程度の減税効果が見込まれていたことと比較すると、その差は歴然としています。
「178万円の壁」合意が崩れた理由
衆院選での与党過半数割れという民意を受けて、自民党、公明党、国民民主党の幹事長間では、「2025年から課税最低ラインを178万円に引き上げることを目標とする」という合意が書面で交わされていました。にもかかわらず、なぜ税制改正大綱に盛り込まれたのは、この合意からかけ離れた小さな数字だったのでしょうか。
その背景には、日本維新の会の動きがあったと指摘されています。維新は与党に接近し、自身らが要求する教育無償化の実現と引き換えに、減税財源としても期待されていた補正予算への賛成を打診したのです。教育無償化に必要な予算は約6000億円程度とされ、年収の壁を178万円に引き上げる場合にかかる財源(年間数兆円規模と試算される)と比べると、はるかに低コストで済みます。財務省は、財源負担のより少ない維新の提案を選んだとみられています。四半世紀ぶりの本格的な所得減税が実現する直前で、維新の会共同代表であった前原誠司氏が減税の道を閉ざした「罪」は、総選挙で与党過半数割れに追い込んだ国民の負託を裏切ったという点で重いと森永氏は論じています。
もう一人の「減税つぶし」犯人?
今回の「年収の壁引き上げ」実現を阻んだもう一人の政治家として、立憲民主党の野田佳彦代表の名前が挙げられています。森永氏によれば、立憲民主党は今回の所得税・住民税の人的控除引き上げの議論に一切賛同することなく、静観の構えを決め込んでいたといいます。もし立憲民主党がこの動きに前向きな姿勢を示し、推進する側に回っていたならば、大型減税が実現していた可能性は十分に考えられる、と森永氏はその著書で指摘しています。
 衆院選後の税制改正議論で注目される立憲民主党・野田佳彦代表が街頭で有権者と交流する様子
衆院選後の税制改正議論で注目される立憲民主党・野田佳彦代表が街頭で有権者と交流する様子
結論
森永卓郎氏が『保身の経済学』で明かしたように、2024年衆院選後の税制改正において、国民が期待した所得税・住民税の本格的な減税や「178万円の壁」実現が見送られた背景には、特定の政党や政治家による「保身」や党利党略が存在した可能性が指摘されています。日本維新の会の教育無償化を優先した動きや、立憲民主党が積極的な賛同姿勢を見せなかったことなどが重なり、結果として国民の手取りを大きく増やす改革は実現しませんでした。森永氏の言葉は、政治の意思決定が国民の経済生活に直接的な影響を与える現実を浮き彫りにしています。