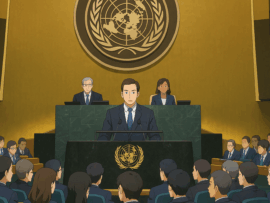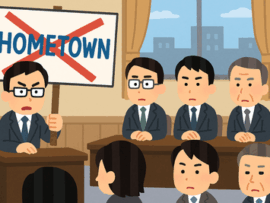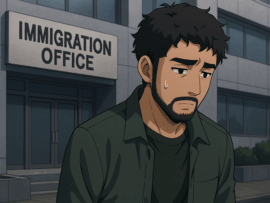皇位継承の安定化に向けた与野党間の議論は再び膠着し、結論は先送りされました。この間、皇族の方々は着実に年齢を重ねられ、インターネット上では心ない誹謗中傷も散見されます。皇室の歴史に詳しい専門家は、この状況を「今そこにある危機」だと指摘しています。本稿では、この皇位継承問題に関する政治議論の現状と、その背景にある課題を詳述します。
 将来の皇位継承に関わる秋篠宮家の悠仁さまと、天皇家の愛子さまの写真。皇室の次代を担う若い世代の姿。
将来の皇位継承に関わる秋篠宮家の悠仁さまと、天皇家の愛子さまの写真。皇室の次代を担う若い世代の姿。
皇位継承安定化に向けた与野党協議の焦点
皇位継承の安定化を図るため、衆参両院の正副議長の主導で与野党は皇室典範改正に関する協議を重ねてきました。当初、通常国会中の成立を目指していましたが、合意に至らず頓挫しました。これまでの議論で中心となったのは、以下の二点です。(1)結婚後の女性皇族が皇室に残る。(2)旧皇族の子孫である男性を皇室に養子として迎える。
合意形成の試みと「棚上げ」の経緯
自民党の麻生太郎最高顧問と立憲民主党の野田佳彦代表は、5月末の段階で一定の歩み寄りを見せていました。(2)の「旧皇族からの養子」案については、憲法上の問題や国民的議論の必要性から異論が多く、これを一時的に棚上げし、(1)の「女性皇族の皇室残留」案を先行させる方向で両者は合意しました。女性皇族の残留を選択制とするか、また残留した場合の配偶者や子の身分をどうするかといった詳細については意見の相違がありましたが、長らく停滞していた議論を少しでも前進させようという意図がありました。
麻生氏の「ちゃぶ台返し」と議論の頓挫
しかし、6月上旬になると状況は一変しました。麻生氏が突如、(2)の棚上げは認められないと主張し始めたのです。これに対し、野田氏は「ちゃぶ台返しだ」と強く反発しました。この結果、通常国会での合意形成は不可能となり、額賀福志郎衆院議長は秋の臨時国会での再協議を目指す意向を示しましたが、実現は極めて困難との見方が支配的です。
自民党の「何もしない」本音と皇室の将来への懸念
過去20年間の政治議論を振り返ると、男系継承を強く主張する一部保守層を背景にした自民党の本音は「何もしない」ことにあると筆者は見ています。現行の、男系継承を明記した皇室典範が彼らにとっての最善であり、改正の必要性を感じていないのです。しかし、男系継承に固執すれば、将来的な皇統断絶の可能性は高まり、皇族減少という現実も喫緊の課題です。世論調査でも女性天皇を容認する声が多いにも関わらずです。政治は何もせずに済ますことはできないため、有識者会議や野党との形式的な議論は行うものの、最終的には結論を先送りするというパターンを繰り返しています。(2)の旧皇族案に言及する割には、具体的な調査や熱意が見られないのは、本気で実現を目指していない証拠と言えるでしょう。では、座して皇統の自然消滅を待つつもりかというと、「現在の自分たちの責任ではない。本当に切羽詰まったときの政治家が考えればいい」というのが大半の政治家の本心ではないか、と専門家は推測します。皇室の将来を真剣に憂慮する向きには嘆息の限りですが、江戸期の武人画家・渡辺崋山の名言「眼前の繰り回しに百年の計を忘する勿(なか)れ」は、まさに今の状況に警鐘を鳴らす言葉と言えるでしょう。
結論:先送りされる「今そこにある危機」
このように、皇位継承を安定させるための政治議論は、重要な局面で再び立ち止まってしまいました。目の前の政治的駆け引きに終始し、皇室の将来という百年の計を忘れているのではないかという懸念が募ります。このまま結論が先送りされ続ければ、皇族減少や皇統断絶といった「今そこにある危機」はより現実味を帯びてくるでしょう。皇室の安定は国家の根幹に関わる問題であり、真剣な議論と迅速な対応が求められています。
参考文献
「皇位継承議論、政治は「何もしない」? 膠着状態の裏にある本音と皇室の危機」(ニッポンドットコム掲載、井上 亮 著)