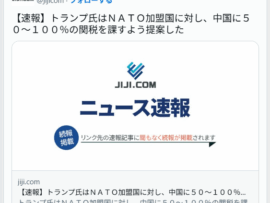7月8日、憲政史上最長の8年8カ月にわたり日本の首相を務めた安倍晋三元首相の没後3年を迎えます。彼の突然の死は日本国内に大きな衝撃を与えましたが、彼が築き上げた外交の軌跡は、今日においてもなお、日本が直面する国際的な課題を考える上で重要な示唆を与え続けています。現在、石破首相率いる新政権は、米国との通商問題、特に自動車への追加関税の可能性や、中国の海洋進出といった、安倍政権時代から続く、あるいは形を変えて現れる「外患」への対応を迫られています。これらの難局に対し、外交を得意とした安倍元首相ならどのように向き合っただろうか。本稿では、安倍元首相に最も食い込んだ記者や、各国に同行した外交スピーチライターらが目撃した数々の「外交秘話」を通じ、彼の驚くべき外交手腕とその「遺産」に迫ります。
安倍元首相の在任中、日本は常に変化し続ける国際情勢の荒波にもまれ、時には主要国との間に深刻な摩擦を抱えることもありました。中でも、ドナルド・トランプ前米大統領が登場して以降の日米関係は、従来の常識が通用しない局面も多く、貿易不均衡や防衛費分担などを巡る厳しい交渉が度々行われました。こうした状況下で、安倍氏が示したのは、首脳間の個人的な信頼関係を徹底的に構築することの重要性です。就任前のトランプ氏との異例の面会に始まり、共にゴルフを楽しむ姿を世界に見せるなど、従来の儀礼的な外交にとどまらない、人間的な繋がりを重視したアプローチは多くの注目を集めました。
![安倍晋三元首相 没後3年:石破政権下の難題に活かせる「外交遺産」とは 安倍晋三元首相の外交手腕:トランプ、習近平両氏との会談、最側近記者やスピーチライターが語る舞台裏 [安倍元首相]](https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20250708-10000349-shinchos-000-1-thumb.jpg) 安倍晋三元首相の外交手腕:トランプ、習近平両氏との会談、最側近記者やスピーチライターが語る舞台裏 [安倍元首相]
安倍晋三元首相の外交手腕:トランプ、習近平両氏との会談、最側近記者やスピーチライターが語る舞台裏 [安倍元首相]
この強固な個人的関係こそが、厳しい交渉において日本の国益を守る上で大きな武器となったと指摘されています。例えば、トランプ政権が日本車に追加関税を課す可能性を示唆した際、安倍氏は首脳会談や電話会談を重ね、粘り強く日本の主張を展開しました。単に論理的に反論するだけでなく、トランプ氏の性格や政治スタイルを深く理解した上で、時にユーモアを交えたり、相手の面子を保つような言葉を選んだりすることで、硬直した交渉の空気を和らげたと伝えられています。最側近記者は、ある緊迫したやり取りの最中に、トランプ氏が最終的に安倍氏の言い分を認めざるを得なくなり、事実上の「降参」という形でその場の主張を取り下げた瞬間を目撃したと証言しており、安倍氏の交渉力の高さを物語っています。
一方、中国との関係においても、東シナ海や南シナ海での活動活発化というデリケートな問題を抱えつつも、対話のチャンネルを維持し続けました。習近平国家主席との首脳会談では、歴史認識や領土問題といった難しい議題に触れつつも、経済協力や人的交流といった共通の利益にも焦点を当て、関係の全面的な悪化を防ぐ努力を続けました。外交スピーチライターは、会談の場の張り詰めた空気の中、安倍氏が発した言葉や態度によって、習主席が思わず笑みをこぼしたり、冗談を言ったりするような瞬間があったと振り返ります。これは、安倍氏が単なる公式声明にとどまらず、言葉の裏に隠された戦略や、相手の感情に働きかける計算されたコミュニケーションを行っていた証左と言えるでしょう。
安倍氏の外交手腕は、主要国首脳との二国間関係に限りません。多国間会議の場においても、彼はその存在感を示しました。G7やG20といった枠組みの中で、日本の立場を明確に発信するだけでなく、各国首脳間の意見の隔たりを埋める調整役を担うこともありました。特に、保護主義の台頭が懸念された時期には、自由貿易の旗手として国際協調の重要性を粘り強く訴え続けました。その演説や発言は、単に政策を説明するだけでなく、聞き手の感情に訴えかけるような言葉選びがなされていたと、スピーチライターは分析しています。綿密な準備と、聴衆に響く言葉の力を理解していたことが、彼の国際社会における発言力を高めた要因の一つでしょう。
現在、日本が直面する国際環境は、安倍政権時代にも劣らず、あるいはさらに厳しさを増しているとも言えます。米国との経済関係は再編の時期を迎えており、中国の地域覇権への野心は隠そうともしません。北朝鮮の核・ミサイル開発も依然として脅威であり、ロシアのウクライナ侵攻は世界の分断を深めています。こうした複雑な状況下で、石破政権をはじめとする日本のリーダーたちには、安倍氏が示したような、個人的な信頼関係構築の重要性、相手国の文化やリーダーの性格への深い理解、そして粘り強く対話を続けながらも、譲れない国益は守り抜くというバランス感覚が求められるでしょう。
最側近記者や外交スピーチライターたちの証言は、安倍外交が単なる華やかな舞台装置ではなく、その舞台裏で徹底的な準備と緻密な計算に基づいて行われていたことを示唆しています。彼が遺したこれらの経験と知恵は、「外交遺産」として、今の日本のリーダーたちが国際社会の難題に立ち向かう上で、貴重な指針となり得るはずです。没後3年という節目にあたり、安倍氏の外交スタイルを改めて検証し、そこから何を学び、どのように現在の日本外交に活かしていくのかを考えることは、極めて今日的な意義を持つと言えるでしょう。
【参考】
週刊新潮 2025年7月10日号掲載特集記事「銃撃事件から3年 安倍晋三元首相が存命なら日本外交はどうなっていたか」
Source link