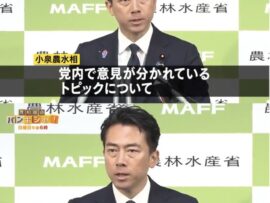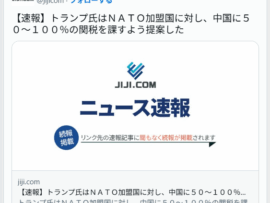中国の習近平政権が推進する過度な「倹約令」が、国内消費の低迷をさらに加速させ、特に飲食業界に深刻な打撃を与えています。その結果、政府は早期に政策の軌道修正を迫られる事態に陥っています。
ことの発端は今年5月中旬に改正された「節約励行・浪費反対条例」です。2013年に共産党関係者の腐敗防止を目的として施行されたこの条例が、今回、公務での会食において「高級料理やたばこ、酒類を提供してはならない」といった具体的な禁止事項を盛り込み、その内容を厳格化したことにあります。この厳格化の背景には、春頃から地方の党幹部らの宴席で飲酒による死亡事故が相次ぎ、特に河南省では綱紀粛正に関する学習会の翌日に公安・検察関係者も参加した集まりで高アルコール度数の白酒を飲んだ人物が死亡するという、習政権の面目を汚す不祥事が発生したことが挙げられます。
厳格化された「節約励行・浪費反対条例」とその波紋
条例改正後、地方政府や公的機関は、連座制による処罰を恐れ、過度な自主規制へと走り始めました。報道やSNSの投稿によると、安徽省では一部の公務員に対して連日アルコール検査が実施され、武漢の国有企業では同僚同士のランチまで禁止される異例の事態が生じました。さらに6月には、顧客からわずか6元(約120円)の麺をご馳走になった銀行員が3000元の罰金を科されるという事例が物議を醸し、国民の間で「3人以上での食事を避ける」という風潮が全国的に広がるきっかけとなりました。これにより、中国のビジネス接待で定番とされてきた高級白酒「茅台(マオタイ)酒」も深刻な価格下落に直面するなど、その影響は多岐にわたっています。
 中国の酒店に並べられた高級白酒「茅台酒」。習近平政権の倹約令により、その価格は深刻な下落に直面している。
中国の酒店に並べられた高級白酒「茅台酒」。習近平政権の倹約令により、その価格は深刻な下落に直面している。
政権の「火消し」と続く「自粛ムード」
こうした社会の過剰反応を受け、習近平政権も沈静化に乗り出しました。6月中旬には、党機関紙である人民日報の電子版が「規定違反の飲食は禁止だが、全ての飲食が違反というわけではない」と題する論評を配信。「形式主義的」な規制を批判し、外食産業が中国の景気や雇用に貢献している点を強調することで、過度な自粛を抑制しようと試みました。
しかし、政府の「火消し」にもかかわらず、社会全体の「自粛」ムードは依然として続いています。香港紙・星島日報が7月に報じたところによると、広東省広州の飲食業界では「閉店の波」が起きており、一部のレストランでは条例改正直後に個室予約が8割も減少したとされます。夏以降もこの減少傾向は3割減の状態で継続しており、一人当たりの消費額も大幅に落ち込むなど、飲食業界の厳しい状況が浮き彫りになっています。
まとめと今後の展望
習近平政権が腐敗防止と綱紀粛正のために導入した「倹約令」の厳格化は、当初の目的を超えて消費意欲のさらなる冷え込みを招き、中国経済の重要な一部である飲食業に甚大な影響を与えています。政府は方針転換を試みていますが、一度根付いた社会の「自粛ムード」を払拭するには時間を要すると見られ、この政策迷走が中国の消費経済に与える長期的な影響が懸念されます。
参考資料
- 時事通信社 (Jiji Press) – 中国「倹約令」が迷走、飲食業に大打撃-習政権、消費冷え込みで軌道修正:https://news.yahoo.co.jp/articles/10454cc11f100ef77d0fae9f34454cb4c4300bf0