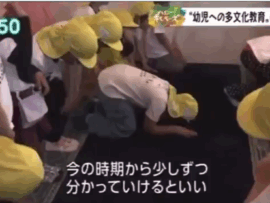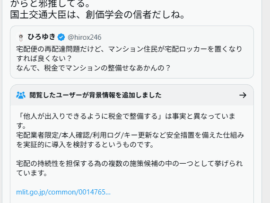姫路城、その白亜の美しさは、世界遺産として、また日本のシンボルとして多くの人々を魅了しています。しかし、その輝きの裏には、幾度もの危機を乗り越えてきた、まさに奇跡ともいえる歴史が隠されているのです。今回は、姫路城が歩んできた苦難の道のりと、現在まで保存されてきた背景を探っていきます。
明治維新後の姫路城:放置と荒廃の危機
明治維新後、全国の城郭は陸軍省の管理下に置かれ、多くの城が取り壊される運命にありました。姫路城も例外ではなく、軍用地として利用されることになり、三の丸にあった御殿群は兵舎建設のために取り壊されてしまいました。さらに、大手門や櫓なども売却の対象となり、城郭としての姿は失われつつありました。
 明治時代の姫路城。屋根には雑草が生い茂り、壁は崩落している。
明治時代の姫路城。屋根には雑草が生い茂り、壁は崩落している。
明治中期には、陸軍の中村重遠大佐の尽力により、名古屋城とともに保存が決定されましたが、十分な予算は配分されず、城は放置状態に。その結果、天守の屋根には雑草が生い茂り、壁は崩落するなど、荒廃が進みました。明治時代の姫路城の写真を見ると、現在の美しい姿からは想像もできないほどの荒廃ぶりです。「まるで廃墟のようだった」と当時の記録にも残されています。
地元民の熱意と豪雨災害:保存への転機
日露戦争後、姫路城の惨状を憂慮した地元住民たちは、「白鷺城保存期成同盟会」を結成し、政府への働きかけを開始しました。同時に、姫路藩士の息子である石本新六陸軍中将の尽力もあり、明治43年にはようやく大規模な修理が行われることとなりました。
しかし、修理は部分的なものであり、西の丸は依然として危険な状態でした。大正、昭和初期にも応急処置的な修理は行われましたが、根本的な解決には至りませんでした。そんな中、昭和9年の豪雨災害によって西の丸の一部が崩落。この事態を受けて、文部省はようやく姫路城全体の保存に乗り出すことになりました。
専門家の視点:危機一髪からの保存
歴史評論家の香原斗志氏は、「姫路城が現在まで残っているのは奇跡に近い」と述べています。「度重なる危機を乗り越え、地元の人々の熱意と、関係者の尽力によって、現在の美しい姿が保たれているのです。まさに、先人たちの努力の賜物と言えるでしょう。」
平成の大修理:白鷺の輝きを取り戻す
その後も、姫路城は定期的な修理を行いながら、その美しい姿を維持してきました。特に、2009年から2015年にかけて行われた「平成の大修理」では、大天守の屋根瓦の葺き替えや壁面の塗り直しなど、大規模な改修工事が行われ、白鷺城の輝きがさらに増しました。
未来へ繋ぐ:姫路城の保存と継承
姫路城は、幾多の困難を乗り越え、現在までその美しい姿を保ってきました。私たちはその歴史を学び、未来へと繋いでいく必要があります。姫路城を訪れる際には、その美しさだけでなく、その背後にある歴史にも思いを馳せてみてください。
まとめ:姫路城、未来へ輝く白鷺
姫路城の歴史は、まさに苦難の歴史でした。しかし、人々の熱意と努力によって、その美しさは守られ、現在に至っています。これからも、世界遺産として、そして日本のシンボルとして、姫路城は輝き続けることでしょう。