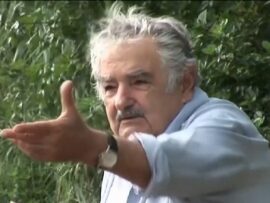近年のAI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活を豊かにする一方で、偽情報の拡散という新たな課題も生み出しています。2022年9月の台風15号による静岡水害の際、AI生成によるフェイク画像がSNSで拡散された事件は、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。本記事では、この事件を教訓に、AI生成画像の見分け方や情報リテラシーの向上について考えていきます。
AI生成画像の拡散:何が起きたのか?
2022年9月、台風15号による豪雨で静岡県に甚大な被害が発生しました。その最中、街全体が泥水に飲み込まれたようなショッキングな画像が「ドローン撮影の静岡水害。マジで悲惨すぎる…」というコメントと共にSNS上に拡散されました。しかし、後にこの画像はAIによって生成されたフェイク画像であることが判明しました。投稿者は「黒咲くろん」と名乗る人物で、インプレッション数が1000を超えた時点で、画像がAI生成であることを明かし謝罪しました。
 alt ドローン撮影と偽り拡散された静岡水害のフェイク画像。街全体が泥水に覆われているように見える加工が施されている。
alt ドローン撮影と偽り拡散された静岡水害のフェイク画像。街全体が泥水に覆われているように見える加工が施されている。
投稿者の動機:好奇心と警鐘
NHK元アナウンサーの堀潤氏は、著書『災害とデマ』(集英社インターナショナル)の中で、この事件の当事者である「黒咲くろん」氏へのインタビューを掲載しています。氏によると、画像を作成・投稿した動機は「水害の状況を知りたい」という純粋な好奇心だったといいます。当時、水害の状況を伝える写真や映像が少なかったため、AIを使って画像を生成してみたとのこと。氏はAI生成画像の作成にハマっており、その一環として軽い気持ちで投稿した画像が、予想外に拡散してしまったと語っています。
情報リテラシーの重要性
この事件は、AI技術の急速な発展に伴い、誰もが簡単にリアルなフェイク画像を作成・拡散できるようになった現実を突きつけました。情報を受け取る側も、情報源の信頼性や情報の真偽を批判的に判断する情報リテラシーがこれまで以上に重要になっています。
AI生成画像を見破るには?
では、AI生成画像を見破るためにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?専門家によると、不自然な影やテクスチャの繰り返し、画像の周辺部の歪みなどに注目することが重要だと言います。また、複数の情報源と照合したり、ファクトチェックサイトを活用するのも有効な手段です。
メディアリテラシー教育の必要性
「情報教育評論家A氏」は、「現代社会において、メディアリテラシー教育は必須です。特に、子どもたちは幼い頃から情報と接する機会が多いため、学校や家庭で情報の見方、扱い方を学ぶ必要があります。」と述べています。
私たちにできること
AI生成画像によるデマ拡散を防ぐためには、私たち一人ひとりの意識改革が必要です。情報の発信者には、AI技術の倫理的な使用と責任ある情報発信が求められます。また、情報を受け取る側も、情報リテラシーを高め、デマに惑わされないように注意する必要があります。
本記事を通して、AI生成画像と情報リテラシーについて改めて考えるきっかけになれば幸いです。
まとめ:情報社会を賢く生きるために
AI技術は急速に進化しており、今後も私たちの生活に大きな影響を与えていくでしょう。AIの恩恵を受けつつ、そのリスクにも適切に対処していくためには、情報リテラシーの向上が不可欠です。