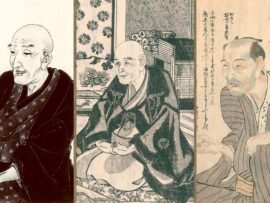昭和恐慌の時代、都市だけでなく農村も深刻な不況に喘いでいました。革命の夢破れ、格差が広がる中、人々はどのように希望を見出していたのでしょうか?本記事では、1925年創刊の農村雑誌『家の光』を中心に、当時の農民たちの格差是正への取り組みと、その根底に流れる「共存同栄」の精神を探ります。
疲弊する農村と『家の光』の創刊
第一次世界大戦後の反動不況は、都市部以上に農村を直撃しました。1925年(大正14年)、そんな時代背景の中で農村雑誌『家の光』が産声をあげました。創刊号の表紙は菖蒲の花や鯉のぼりなど、のどかな田園風景を描いていましたが、誌面には農村の厳しい現実と未来への危機感が綴られていました。
 alt 創刊号の表紙にはのどかな田園風景が描かれている
alt 創刊号の表紙にはのどかな田園風景が描かれている
「本誌記者」は、かつて社会問題の中心だった農村問題が軽視されている現状を嘆き、これまでの農村振興策を「空鉄砲」「不渡手形」と痛烈に批判。農民の実生活からの根本的な改革を訴えました。別の論考でも、急速な人口流出と農業生産性の低下により、地主も小作人も苦境に立たされていると指摘しています。
デンマークに見る理想の農業と生活
『家の光』が日本の農業再興のモデルとして掲げたのが、北欧の農業国デンマークでした。デンマークの近代的な農業経営、特に産業組合によるバターやチーズなどの輸出成功例は、日本の農村にとって大きな希望となりました。
また、『家の光』はデンマークの質素ながらも教養高く、農作業にも励む女性たちの姿に理想の生活様式を見出しました。彼らは近代的な農業経営と新しい生活様式を両立させることで、真の幸福を掴んでいると考えたのです。
「共存同栄」の精神と体制批判
『家の光』の表紙には「家の光」の文字と共に「共存同栄」の理念が掲げられています。発行母体である産業組合中央会は官製組合でしたが、『家の光』は政党政治、資本主義、都市中心主義といった当時の体制に対し、独自の共同主義に基づいた批判的な視点を持ち合わせていました。

彼らは金権政治に堕した政党政治を批判しつつ、欧米のような公明正大な複数政党制への期待も表明。同時に、国民一人ひとりの政治的自覚の重要性を訴えました。1925年に公布された普通選挙法により新たに選挙権を得た約1000万人の「青年と新有権者」に対し、『家の光』は困難な時代だからこそ、与えられた権利を正しく行使するよう呼びかけました。
農民の自立と未来への希望
『家の光』は、単なる農業技術誌にとどまらず、農民の自立と社会改革への意識を高めるための重要な役割を担っていました。「共存同栄」の精神は、厳しい現実の中でも希望を失わず、より良い未来を築こうとする農民たちの強い意志の表れだったと言えるでしょう。
井上寿一氏の著書『戦前昭和の社会 1926-1945』(講談社現代新書)では、当時の社会状況や人々の暮らしがより詳しく描かれています。ご興味のある方はぜひ手に取ってみてください。