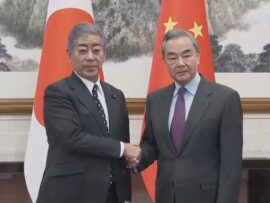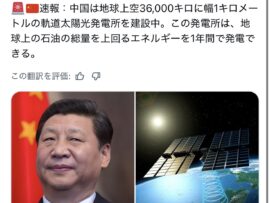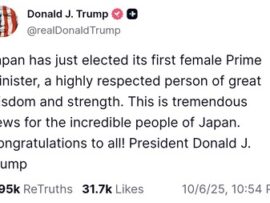アメリカ経済を支える屋台骨である家計の消費行動に変化が現れています。これまで旺盛な消費で知られたアメリカ国民ですが、ここにきて支出を抑え、貯蓄に励む傾向が強まっているのです。本記事では、この消費低迷の兆候とその背景にある要因、そして今後のアメリカ経済への影響について詳しく解説します。
アメリカ家計の貯蓄率が8ヶ月ぶりの高水準に
米国商務省の発表によると、2025年3月の家計貯蓄率(可処分所得比の貯蓄額)は4.6%と、2024年6月以来、8ヶ月ぶりの高水準となりました。 2~3%台で推移してきた貯蓄率の低いアメリカとしては異例の事態です。
 alt
alt
経済の先行き不透明感や金融資産価格の下落を受け、家計は財布の紐を締め始めたと考えられます。直近で貯蓄率が上昇したのは、新型コロナウイルス感染拡大初期の2020年でした。経済不安と政府からの支援金支給により、貯蓄率は一時32%まで急騰しましたが、パンデミック収束とともに低下。昨年末には3%台まで落ち込みました。しかし、今年1月には4.3%に上昇し、3月には5%近くまで達しています。
政策リスクが消費心理を冷やす
貯蓄率上昇の背景には、トランプ政権の政策リスクが大きく影響しています。相互関税などによる経済の先行き不透明感が、消費意欲を減退させているのです。米経済調査団体カンファレンスボード(CB)が発表した2025年3月の消費者信頼感指数は92.9(1985年=100基準)と、前月から7.2ポイントも下落。2021年1月以来の低水準となりました。消費者信頼感指数が100を下回ると、景気見通しへの悲観的な見方が優勢であることを示しています。
特に、トランプ大統領就任直後の2024年12月から4ヶ月連続で下落している点は懸念材料です。CBの消費者期待指数も同期間に9.6ポイント下落し、2013年以来の最低水準となりました。短期景気見通しを示す消費者期待指数が80を下回ると、景気後退の兆候とされます。「未来の所得に対する消費者の楽観論がほぼ消滅した」とCBのシニアエコノミスト、ステファニー・ギシャール氏は指摘。経済と労働市場への不安が、消費者の個人状況への評価に影響を及ぼし始めていると分析しています。
株価下落が「富の効果」を消失させる
関税政策の影響で主要株価指数が下落したことも、消費不振に拍車をかけています。金融資産の保有比率が高いアメリカの家計は、株価下落時に消費を減らす傾向があります。DS証券のエコノミスト、キム・ジュンヨン氏は、「消費者心理の悪化と株式市場の調整が重なれば、米国の消費は鈍化する」と予測。「富の効果(資産価格の上昇に伴う消費の増加)が消え、貯蓄率はさらに上昇するだろう」と述べています。
消費低迷が景気鈍化につながる可能性
家計が支出を抑え貯蓄に走れば、消費関連指標の鈍化は避けられません。問題は、トランプ政権の政策の不確実性が短期的に解消される見込みが薄く、景気刺激策としての金融政策(利下げ)も高インフレのため制限されている点です。梨花女子大経済学科のソク・ビョンフン教授は、「経済の先行きが不透明な場合、消費が減退するのは経済学の常識」と指摘。消費が米国経済全体の3分の2近くを占めるため、現状の不確実性が解消されなければ、米国経済が減速する可能性が高いと警告しています。
専門家の見解
フードライターの山田花子氏は、「食費は家計支出の中でも大きな割合を占めるため、消費低迷の影響を大きく受ける」と指摘しています。食のトレンドにも変化が現れ、外食を控え、家庭で手軽に作れる料理への需要が高まっているといいます。
今後の展望
アメリカ経済の行方は、家計の消費動向に大きく左右されます。政策リスクの解消、株価の回復、そしてインフレの抑制が、消費意欲の回復には不可欠です。今後の動向を注視していく必要があるでしょう。