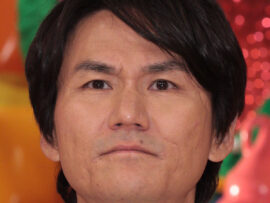昭和から100年。近頃、昭和を振り返る番組や記事をよく目にします。池上彰氏の番組で、養老孟司氏が昭和の「ゆるさ」について興味深い発言をされていました。現代社会の多様性への疑問を投げかけるその内容に、共感と反発の声が上がっているようです。今回は、養老氏の著書『人生の壁』も参考に、真の多様性について考えてみましょう。
養老孟司氏が語る「昭和のゆるさ」
養老氏は、昭和の時代には酒、タバコ、立ち小便など、現代では問題視されるような行為にも寛容な一面があったと指摘します。これは、人々の多様な生き方を許容する社会だったと言えるのではないでしょうか。SDGsなど、多様性を謳う現代社会ですが、本当に多様性に向かっているのか、もっと「ゆるさ」が必要なのではないか、と養老氏は問いかけます。
 昭和の街並み
昭和の街並み
現代社会の息苦しさ:立派な標語の落とし穴
養老氏は、西洋思想に基づくグローバリゼーションが現代社会の息苦しさの一因だと指摘しています。一つの思想、一つのルールで世界を縛ろうとする傾向が強まっているのではないでしょうか。環境問題や生物多様性についても、西洋中心的な視点で語られることが多いと養老氏は述べています。
 ラオスの昆虫食文化
ラオスの昆虫食文化
例えば、生物多様性条約を例に挙げ、ラオスのような国での昆虫採集規制について言及しています。ラオスでは、古くから昆虫を食糧としてきました。食文化、生活に根付いた昆虫採集を制限することは、真の多様性を理解していると言えるのでしょうか?
多様性を尊重する社会とは?
著名な文化人類学者、A博士(仮名)は、「真の多様性とは、異なる文化や価値観を認め合い、共存していくこと」だと述べています。画一的な基準を押し付けるのではなく、それぞれの文化、歴史、生活様式を尊重することが重要です。
養老氏の指摘は、現代社会における多様性のあり方について、深く考えさせるものです。「立派な標語」の裏側にある真意を見極め、多様性を尊重する社会の実現に向けて、一人ひとりが意識を高めていく必要があると言えるでしょう。