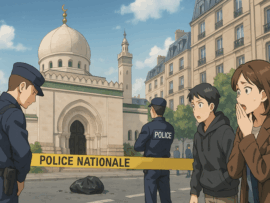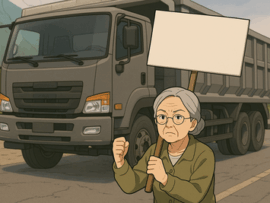食卓の主役、コメの価格高騰が続いています。政府は備蓄米放出を決定しましたが、価格が落ち着くまでにはまだ時間がかかりそう。今回は、コメ不足の現状、その原因、そして賢く乗り切る方法まで徹底解説します!
なぜコメは高い?3つの原因を紐解く
コメ価格高騰の背景には、複雑な要因が絡み合っています。主な原因を3つに絞って見ていきましょう。
業者間の転売で価格が吊り上げ?
2024年産のコメは豊作だったにもかかわらず、集荷量は前年より大幅に減少。「消えたコメ」はどこへ行ったのでしょうか?米流通評論家で米穀店を営む常本泰志氏(仮名)は、業者間の投機的な動きを指摘します。卸売業者が年間契約ではなく、スポット取引で安いコメを買い占め、高値で転売しているというのです。JAの相対取引価格とスポット取引価格の差額は、実に2倍近く。米穀店に販売するより、業者間取引の方が儲かるため、このような動きが加速していると考えられます。さらに、生産者による在庫のストックも、供給不足に拍車をかけています。この状況に最も苦しんでいるのは、スーパーなどの小売業者。仕入れ値の高騰で資金繰りが厳しく、自転車操業を強いられているところも少なくありません。
 alt
alt
農水省の需給予測ミス?
コメ高騰の背景には、農水省の需給管理の甘さもあると、宮城大学名誉教授の大泉一貫氏(仮名)は指摘します。長年の減反政策で需給をタイトに管理してきた結果、わずかな需要増加でも価格が乱高下しやすくなっているというのです。さらに、農水省が発表する作況指数にも疑問符がつきます。気候変動や病害虫の影響で、実際の生産量は想定より少ない可能性も。農水省のデータへの不信感が、業者によるコメの買い占めを助長している側面もあるでしょう。
生産調整の見直しが必要?
大泉氏は、供給安定化のためには生産調整のあり方を変えるべきだと提言します。主食用米と加工用米、輸出用米を区別して生産調整するのではなく、一律に自由に生産させ、余剰分を輸出に回すべきだというのです。これにより、国内の供給量を確保しつつ、海外市場への展開も可能になります。
賢く乗り切る!コメ不足時代の節約術
コメ価格高騰時代、家計を守るためには工夫が必要です。例えば、麦ごはんや雑穀米を取り入れる、パスタやパンなどの代替食を活用する、外食の回数を減らすなど、様々な方法があります。
専門家のアドバイス
食生活アドバイザーの佐藤恵氏(仮名)は、「様々な穀物をバランスよく摂取することで、健康にも経済的にもメリットがあります。コメだけにこだわらず、柔軟に食生活を見直してみましょう」とアドバイスしています。
まとめ:コメを取り巻く状況を理解し、賢く行動しよう
コメの価格高騰は、様々な要因が複雑に絡み合った結果です。現状を正しく理解し、賢い選択をすることで、家計への負担を軽減することができます。ぜひ、今回の情報を参考に、食卓を守りましょう。