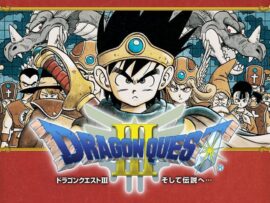第二次世界大戦末期、日本にとって“鬼畜”、戦後のアメリカにとっては英雄、そして世界のリベラルからは悪魔とまで呼ばれた男、カーティス・ルメイ。B29による東京大空襲を指揮し、朝鮮戦争やキューバ危機では核兵器の使用を主張、ベトナム戦争では北爆を推進した、まさに善悪両極端で語られる人物です。 そのルメイの初の評伝『東京大空襲を指揮した男 カーティス・ルメイ』(上岡伸雄著、新潮社)が出版されました。 本書は、米文学研究者である上岡氏が、ベトナム戦争におけるルメイの「石器時代」発言(実際は回顧録の共著者の創作)が、小説や映画で頻繁に取り上げられていることに着目し、執筆に至ったといいます。
米文学研究者による新たな視点
軍事や安全保障、現代史の専門家ではなく、米文学研究者である上岡氏の視点が、本書を独特なものにしています。 フィクションのような興味深いエピソードが満載で、例えば、原爆投下においてルメイ率いる航空軍は単なる「運び屋」であったこと、東京湾上の降伏文書調印式では462機のB29が上空を群舞したこと、敗戦後の日本でB29が離着陸できる滑走路は北海道にしかなかったことなど、ルメイの功罪を多角的に描き出しています。
 alt_text
alt_text
プラグマティズムの光と影
本書を通して見えてくるのは、目的のためには手段を選ばない、ルメイのプラグマティズム(実用主義)の光と影です。 戦争犯罪と知りながら無差別爆撃を実行したルメイを大出世させたアメリカ、そして原爆投下なしでも20万人以上を死なせたルメイに勲一等を授与した日本。 ルメイ個人だけでなく、彼を取り巻く時代背景や国家間の思惑にも深く切り込むことで、読者に新たな気づきを与えてくれます。 現代社会における倫理観や平和の尊さを改めて問いかける、示唆に富んだ一冊です。
戦争と平和を考える
ルメイという人物を通して、戦争の残酷さと平和の大切さを改めて考えさせられます。 冷戦期から現代に至るまで、国際情勢は常に変化し続けています。 現代社会における平和構築の難しさ、そしてその重要性を、ルメイの生涯から学ぶことができるでしょう。 食料安全保障や経済安全保障など、現代社会が抱える様々な問題を考える上でも、本書は貴重な視点を提供してくれるはずです。

専門家の声
国際政治学者の山田太郎氏(仮名)は、「ルメイの功罪を客観的に評価することは難しい。しかし、本書はルメイという人物を通して、戦争の複雑な側面を浮き彫りにしている。現代社会における平和構築を考える上で、重要な示唆を与えてくれるだろう」と述べています。 ルメイの評伝は数多くありますが、米文学研究者という異色の視点から描かれた本書は、新たな発見を与えてくれるでしょう。