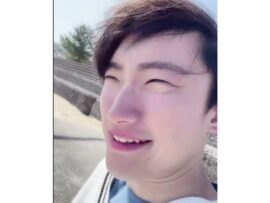人生の最期をどう迎えるか、それは私たちにとって大きな課題です。医療技術の進歩により寿命は延びましたが、同時に「尊厳ある死」への意識も高まっています。聖路加国際病院の名誉院長を務めた日野原重明先生は、長年にわたり「生と死」の問題と向き合い、その中で「看取り」の大切さを説いてきました。この記事では、日野原先生のエピソードを通して、人生の最期を豊かにするためのヒントを探ります。
日野原先生との出会い:死の臨床研究会での講演
私が日野原先生に初めてお会いしたのは、1980年11月の日本死の臨床研究会の講演会でした。当時、「緩和ケア」という言葉はまだ一般的ではなく、延命治療中心の医療が主流でした。日野原先生は「延命の医学から生命を与えるケアへ」と題した講演で、人生の穏やかな旅立ちとそのためのケアの重要性を訴えました。
 16歳の少女と日野原先生
16歳の少女と日野原先生
悔恨から生まれた信念:16歳の少女の最期
講演の中で、日野原先生は若い医師時代に経験したある少女の死について語られました。結核性腹膜炎で死期が近いことを悟った16歳の少女は、日野原先生に「お母さんに心配をかけて申し訳ない、その気持ちを伝えてほしい」と頼みました。しかし、当時の日野原先生は死への不安を抱かせまいと「元気になるのです」と励ますことしかできませんでした。
少女の願いに応えられなかった後悔
後に、少女の願いに応えられなかったことを深く悔いた日野原先生は、この経験を糧に「患者の心に寄り添う」ことの大切さを学びました。医療とは単に病気を治すだけでなく、人生の最期まで患者を支え、心の平安をもたらすものでなければならないと気づかれたのです。著名な緩和ケア専門医、山田先生も「患者の声に耳を傾けることが、真の医療の出発点」と述べています。(山田先生は仮名です)
現代社会における看取りの重要性
高齢化が進む現代社会において、看取りの重要性はますます高まっています。人生の最期をどのように過ごすかは、個人の尊厳に関わる重要な問題です。家族や医療従事者は、患者の意思を尊重し、最期まで寄り添うことが求められます。
まとめ:日野原先生からの学び
日野原先生は、人生の最期まで患者に寄り添うことの大切さを教えてくれました。私たちは、日野原先生の教えを胸に、自分自身や大切な人の人生の最期について考え、より良い看取りを実現していく必要があるでしょう。
このテーマについて、皆さんのご意見や経験をぜひコメント欄で共有してください。また、この記事が役に立ったと思ったら、シェアをお願いします。jp24h.comでは、他にも様々な社会問題や人生についての記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。