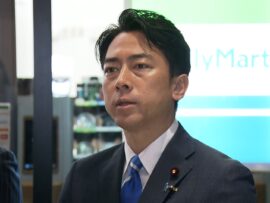日本にいながらにして海外の音楽フェスティバルの熱気を体感できると話題の「Snow Machine(スノーマシーン)」。スキーやスノーボードといったウィンタースポーツと音楽の融合イベントとして人気を集めていますが、その華やかな舞台の裏には、光と影が存在します。本記事では、Snow Machineの魅力と課題、そして今後の展望について深く掘り下げていきます。
Snow Machineとは?:ニュージーランド発、世界へ
Snow Machineは、ニュージーランドのクィーンズタウンで生まれたアルパイン・ミュージック&スキーフェスティバル。日本では2020年3月に長野県白馬村で初開催され、「日本人がいない日本のフェス」としてSNSで話題を呼びました。その後も白馬村、そして北海道ニセコ町と開催地を広げ、国内外から多くの参加者を集めています。
 白馬村で開催されたSnow Machineの様子
白馬村で開催されたSnow Machineの様子
インバウンド効果:地域経済への大きな貢献
主催者によると、Snow Machineは白馬村で約15億円、ニセコ町で約9億円もの経済効果を生み出しているとのこと。参加者の約8割が海外からの旅行者で、オーストラリアやニュージーランドをはじめ、世界30カ国以上から来日しています。「世界最高峰の雪と音楽、そして日本の食文化を楽しめた」という声も多く、インバウンド誘致の成功事例として注目されています。
地域住民の声:騒音問題やマナー違反
一方で、イベント開催に伴う課題も浮き彫りになっています。白馬村の住民からは、騒音問題や一部参加者のマナー違反に関する苦情が寄せられています。過去の開催時には、器物破損やゴミのポイ捨てなどのトラブルも発生し、地元住民との摩擦も生じています。
ニセコ町での課題:運営の不透明性
ニセコ町でも、騒音に関する苦情が警察に寄せられたとのこと。また、倶知安観光協会は、イベント準備の経過共有が不足していた点や、必要手続きが期日ギリギリになった点などを指摘し、主催者側に改善を申し入れています。

主催者の対応と今後の展望
主催者は、騒音苦情に対しては音量調整などの対策を講じていると説明。また、セキュリティガードの配置や清掃チームの運営など、イベントの円滑な運営に努めていると強調しています。さらに、地元コミュニティとの連携を強化し、地域住民との共存を目指していく姿勢を示しています。
イベント運営コンサルタントの山田一郎氏は、「地域住民との対話と相互理解が不可欠」と指摘。「イベントの経済効果を最大化しつつ、地域社会への影響を最小限に抑えるためには、丁寧なコミュニケーションと事前の合意形成が重要」と述べています。
まとめ:持続可能なイベント運営に向けて
Snow Machineは、地域経済の活性化に大きく貢献する一方で、騒音問題やマナー違反といった課題も抱えています。今後の更なる発展のためには、主催者と地域住民、そして自治体が協力し、問題解決に取り組むことが不可欠です。より良い形でイベントが継続されるよう、関係者間の対話と相互理解が求められています。