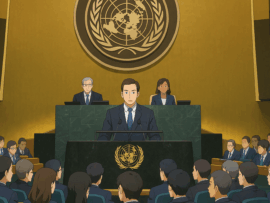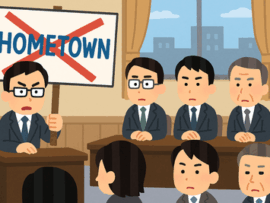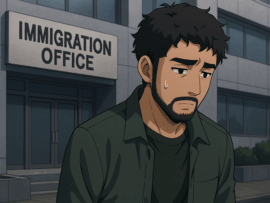[ad_1]
なぜコメの値段が上がり続けているのか。経済評論家の加谷珪一さんは「そもそもの発端は、日本人の食生活が欧米化し、コメを消費しなくなったことにある。値段を下げるなら2つの方法しかない」という――。
■再び5kg2000円台に戻ることはない
農林水産省が5月7日に発表した、スーパーで販売されるコメの平均価格。5kgあたり4233円と、17週連続で最高値を更新した。その後12日には19円下落し、5kgあたり4214円となったが、長い間コメの価格は上昇し続け、去年と同時期の2倍近い高水準だ。政府は3月に21万トンもの備蓄米を放出したものの、コメの価格高騰は収まる気配がない。
石破首相は党としてさらなる対策をまとめるよう指示したようだが、それで本当にコメの価格は下がるのだろうか。結論から申し上げると、再び2000円台に戻ることはない、と考えている。
「令和のコメ騒動」が起きた背景には、複雑に絡まったいくつもの問題が横たわっている。それを放置してきた過去30年分にわたる農業政策のツケが、今になって回ってきたのだ。
■コメの生産量が足りていない
農林水産省はこれまで、一部の業者が投機目的でコメを抱え込み、あるはずの21万トンが流通から“消えた”ことが価格高騰の原因だと説明してきた。
しかし、コメが“消えた”わけではない、というのが私の一貫した主張である。コメの価格がこれだけ高騰しているのは、単純に「コメの生産量が需要に足りていないから」だ。そもそもの発端は、日本人の食生活が欧米化し、コメを消費しなくなったことにある。朝はコーヒーとパン、昼はパスタといった食生活が当たり前になり、国民一人当たりのコメの消費量は約50年前と比べるとほぼ半減、約20年前と比べても2割以上減っているのだ。
コメの市場は昭和の時代に比べて、極端に小さくなった。コメを生産しすぎれば当然、価格も下がってしまうため、コメ農家はこれまで生産量を減らして調整してきた。小さい市場になったことで、わずかな需給変動で価格が大きく上下してしまう状況ができあがった。
そこに大打撃を与えたのが、インバウンド需要の増加だ。コロナ後に訪日外国人客が増え、飲食店を中心にコメの消費が激増した。けれども、これまでギリギリの需給で生産してきたコメ農家は、急に生産量を増やせと言われても対応できない。休耕田を元の状態に戻すには2年ほどの月日がかかるため、結果として需要に対して供給が追いつかないのが現状なのである。
[ad_2]
Source link