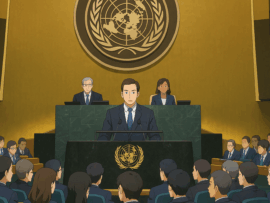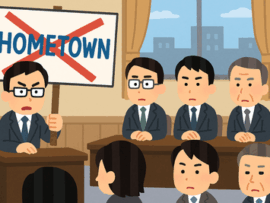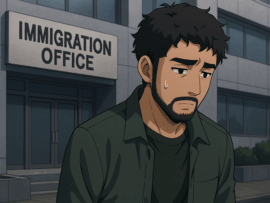[ad_1]
「軍事力のランキングはあまり意味がない」と語るのは、軍事研究者の小泉悠氏。例えば、北朝鮮軍のほうがロシア軍より兵士の数は多いが、両者が戦ったとしても北朝鮮軍が勝つとは誰も思わない。では、「軍事力」における兵隊や兵器の数以外の重要な要素とはなんなのか。気鋭の軍事研究者2人が対談形式で解説する。※本稿は、小泉悠・山口亮『2030年の戦争』(日経BP 日本経済新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
● 軍事力のランキングは あてにならない
小泉悠(以下、小泉) 各国別の軍事力調査というものがあります。メディアでよく紹介されるのはグローバルファイヤーパワー(Global Firepower)の調査です。なぜよく引用されるかといえば、無料であるのと、わかりやすいランキングになっているからです。
しかし、軍事力のランキングというのは、あまり意味がありません。例えばウクライナ戦争前のロシア軍は、定員が101万3628人、実数90万人ぐらいでした。一方、北朝鮮の人民軍は100万人とか110万人でした。単純に数だけ見ると、北朝鮮のほうがロシアより多いということになります(図表4)。
小泉 でも、ロシア軍よりも北朝鮮軍のほうが強いとは誰も思いません。そこでまず、軍事力において兵隊や兵器の数以外の要素は何かという話をしてみたいと思います。山口さんはオーストラリアの大学院で国防計画(ディフェンス・プランニング)を専攻したそうですが、そこでは戦力を測る方法などを学んだのですか?
● 国防計画で一番重要なのは 有事に対する「即応力」
山口亮(以下、山口) 結論からいうと、戦力を正確に測ることはできません。メディアでは兵器や兵隊の数を軍事力として伝えがちですが、量よりも質が大切です。とりわけC4ISR(指揮・統制・通信・コンピューター、情報、監視、偵察)、教育・訓練、そしてロジスティクスを含む運用能力などが重要であり、これらの数値化はほぼ不可能です。
スポーツの場合、各選手の能力や過去の成績などのデータに基づき、ある程度の順位をつけることができますが、実際のところどれくらい強いのかを測るには、試合しかありません。いい選手がそろっていても、戦い方によって結果は違ってきますし、監督、試合会場、選手のコンディションなど、様々な要素が関係してきます。
軍事とスポーツは、戦力やコンディション、戦い方や戦地など、共通点があります。しかし、軍事においてはそれらはスポーツ以上に勝敗を大きく左右しますし、その他にも異なる点が多くあります。スポーツは決まったルールに従って行われるので、ある程度測れる数字がありますが、軍事の場合は様々な面で非対称な部分が多くなります。過去の戦績に関しても、それぞれの戦争や作戦の背景や内容が異なるので、あまり参考になりません。
そもそも私は軍事力という言葉自体、単純化の傾向があるので、あまり好きではありません。国防計画で一番重要なのは「即応力」と言われます。即応力とは、有事に発生した事態に対して直ちに対応できるか、任務や作戦を遂行できるかということに基づくものです。単に装備の性能だけでなく、運用の質が問われます。
● 構造即応力よりも 運用即応力が重要
小泉 スポーツだって、今年どこのチームが優勝するかは誰にも分かりませんよね。チームの強さを完全に客観的な方法で測定することはできないからです。まして軍事力の場合は考慮すべきファクターがはるかに多い。「即応力」を基準にするという考え方は面白いので、もう少し詳しく説明してもらえますか。
山口 即応力は、「構造即応力」と「運用即応力」の2つに分けられます。構造即応力とは、艦船や航空機、戦車の数などの兵器や装置、インフラ、いわゆるハードウエアを含む概念です。一方、運用即応力は、ロジスティクス、修理、メンテナンス、教育、訓練などを意味します。
[ad_2]
Source link