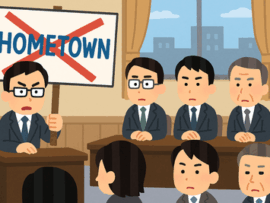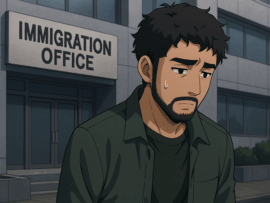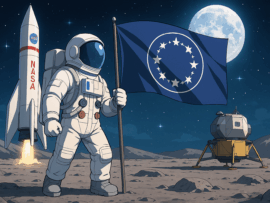新幹線での移動中、仕事や情報収集のために無料Wi-Fiを利用する機会は多い。しかし、「通信速度が遅くて使い物にならない」「すぐに接続が切れる」といった不満の声が頻繁に聞かれるのが現状だ。特に無料で提供されているフリーWi-Fiサービスはセキュリティ面にも注意が必要であり、個人情報やクレジットカード情報など重要な情報を入力するサイトへのアクセスは避けるべきである。
標準新幹線フリーWi-Fiの現状とその理由
JR各社が提供する「Shinkansen Free Wi-Fi」などの無料Wi-Fiサービスは、メールアドレスやSNSアカウントで認証すれば誰でも利用できる手軽さがある。しかし、多くの利用者が感じているように、その通信速度は実用的とは言えないレベルだ。1回の接続時間は30分と短い上に、ページの読み込みに時間がかかるなど、見たい情報にすら満足にアクセスできないことが多い。「新幹線 Wi-Fi」と検索すると、「遅い」「繋がらない」「ゴミ」といったネガティブなキーワードが並ぶほどである。
この通信品質の問題は、主に携帯電話と同じ電波を利用しているため通信量に限りがあること、そして接続している端末数や電波状況(トンネル、山間部など)に大きく左右されることに起因する。電波状況の悪い区間では接続が切れてしまうことも多く、安定した利用は期待しにくい。
 新幹線内で無料Wi-Fiに接続し作業するビジネスパーソン(イメージ)
新幹線内で無料Wi-Fiに接続し作業するビジネスパーソン(イメージ)
ビジネス向け「S Wi-Fi for Biz」でも課題が
東海道・山陽新幹線では、ビジネス利用を想定した「S Work車両」(主に7号車)やグリーン車(8号車)向けに、「S Wi-Fi for Biz」というサービスも提供されている。これは通常の「Shinkansen_Free_Wi-Fi」の約2倍の通信容量を持つとされている。
しかし、容量が2倍になったとしても、多くの利用者が期待するような快適な通信環境とは言い難いのが実情だ。サービス利用上の注意書きにも、利用人数によって通信速度が低下したり接続しづらくなったりする可能性、通信容量には限りがあることなどが明記されている。そのため、OSのアップデートや大容量のアプリダウンロードなどは制限される可能性がある。年間約1億6000万人が利用する日本屈指の交通インフラである東海道新幹線において、特にビジネス利用をうたう車両であっても、Wi-Fiサービスの品質が利用者のニーズに応えきれていない現状がある。
まとめ:新幹線Wi-Fi利用時の心構え
新幹線内の無料Wi-Fiは、メールチェックや軽い情報検索といった用途には役立つ場合もあるが、速度や安定性に課題が多いことを理解しておく必要がある。特に「S Wi-Fi for Biz」であっても、過度な期待は禁物だ。また、繰り返しになるが、無料Wi-Fi利用時にはセキュリティリスクを考慮し、個人情報や金融情報に関わるサイトでの入力は極力控えることが賢明である。快適で安全なオンライン環境が必要な場合は、モバイルルーターやスマートフォンのテザリング利用も検討すべきだろう。