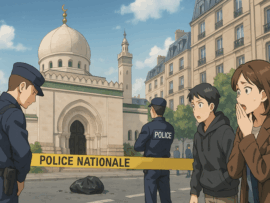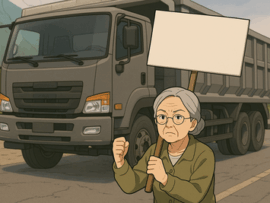丸紅経済研究所の今村卓社長は9日、東京都内での講演で、トランプ前米大統領が示唆する輸入銅および銅製品への50%関税案について、米国の消費者や経済に悪影響を与える可能性があるとの懸念を表明した。今村氏は、たとえ一時的に導入されたとしても、その深刻な影響から関税が撤回に追い込まれる可能性が高いとの持論を展開。これは、米市場で注目されている「TACO(Trump Always Chicken Out)」理論に合致する見方を示唆した。
銅関税案が米国経済に与える影響
今村氏は、丸紅が南米チリで複数の銅鉱山権益を持つ立場から、米国の銅供給状況を分析。米国国内の銅生産は消費全体の約4割にとどまり、残りの約6割をチリなど国外からの輸入に依存している現状を指摘した。このような状況下で大幅な関税を課した場合、米国内での銅価格が急騰し、銅を使用する多様な製品の価格上昇やインフレーション圧力につながるリスクがあるとの見方を示した。
 東京都千代田区での講演で日米関税を語る丸紅経済研究所の今村卓社長
東京都千代田区での講演で日米関税を語る丸紅経済研究所の今村卓社長
対日「相互関税」の行方と専門家の見解
トランプ氏の関税政策に関連して、日本からの輸入品に課される「相互関税」の上乗せ分の停止期限が、当初の7月9日から8月1日に延長された経緯がある。分野別の品目を除き、日本からの輸入品に対する関税率は24%から25%に引き上げられたが、この期限延長自体がTACO理論の表れと解釈する向きもある。
これに対し、トランプ氏は8日、自身のソーシャルメディア上で「再延期はない」と強調した。しかし、今村氏は「トランプ氏は取引(ディール)による合意を好む性質がある。8月1日の期日はそれほど絶対的なものではない」との認識を示し、再度の延長もあり得るとの見通しを述べた。
日米貿易交渉の粘り強さの重要性
日米間の関税交渉は、今年4月以降、赤沢亮正経済再生担当相が7回にわたり訪米し、集中的な協議を重ねてきた。現時点では交渉において目立った具体的な成果は確認されていない。今村氏は、日米間の見解に依然として隔たりがある点を踏まえつつも、粘り強く交渉を継続することの重要性を強調した。また、全面的な関税撤廃が難しい現状では、「一部で妥協点を探りつつ、関税の削減を目指すことが現実的かつ重要だ」と提言した。
結論
丸紅経済研究所の今村社長は、トランプ氏が示唆する銅および対日「相互関税」の強化は米国経済に打撃を与える可能性が高く、結果的に撤回や再度の延期に至る可能性があるとの予測を示した。日米間の貿易交渉は難航しているものの、専門家は粘り強い対話と一部妥協を通じた関税削減の模索が肝要であると訴えている。