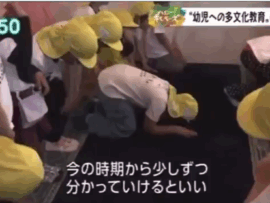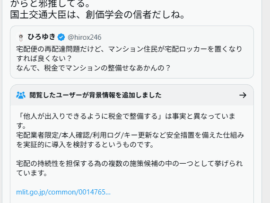日本の10代にとって最大の関心事の一つである大学受験は、その後の人生における選択肢を大きく左右する重要な分岐点です。良い大学に進学することが、希望する職に就く確率を高め、将来のキャリア形成において有利に働くのが現代日本の社会構造と言えるでしょう。このような時代背景の中、「自分らしい大学進学」を考える上で指針となる書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が刊行されました。本書は、表面的な綺麗事を排し、大学受験の本質、ひいては人生との向き合い方を深く考察するための決定版です。今回は、その発刊を記念し、著者であるびーやま氏への特別インタビューをお届けします。
びーやま氏が定義する「高学歴」とは?
「高学歴」という言葉の定義は曖昧で、多くの人が関心を持つ一方で明確な答えを見出しにくいテーマです。びーやま氏はこの問いに対し、誤解を恐れずにその見解を述べています。
びーやま氏によれば、「高学歴」のボーダーラインは、一般的に「MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)以上、かつ国公立大学」であるとされています。この基準には明確な理由があり、それが日本独自の「新卒採用」における現実と深く結びついています。特に、多くの企業が実施する書類選考の段階で、このレベル以上の大学出身者は、学歴によって門前払いされるリスクが低いとびーやま氏は指摘します。
 日本の大学受験と高学歴、将来のキャリア選択肢を考える学生のイメージ
日本の大学受験と高学歴、将来のキャリア選択肢を考える学生のイメージ
「学歴フィルター」の現実と大学名の重要性
「学歴ではなく、その人の能力が重要だ」「学校歴と学歴は違う」といった意見も存在しますが、びーやま氏はこの点について、日本の社会における「大学名」の持つ影響力を無視できないと強調します。例えば、いわゆるFラン大学の出身者が、高偏差値大学出身者と同等のキャリア選択肢を持つかと言えば、現状ではそうではないと彼は断言します。理想的な社会がどうあるべきかという議論は別として、現実社会においては学歴と偏差値は切り離して考えることは困難です。
この現実を前提とした上で、就職活動において最も学歴が重視される新卒採用の現場では、「学歴フィルター」の存在が多くの学生のインタビューを通じて浮き彫りになっています。びーやま氏は、このフィルターを比較的容易に回避できるのが、やはり「MARCH以上、国公立大学」のレベルであると実感しているとのことです。もちろん、これ以下の大学にも素晴らしい教育機会や学生は多数存在しますが、学歴フィルターを楽に突破できるかという点においては、厳しい現実があると言えます。実際に、MARCHや国公立大学の中でも偏差値が比較的低い学部や学科の場合、フィルターに引っかかる可能性もゼロではなく、このボーダーラインがいかに繊細であるかが示唆されています。
まとめ:大学受験の現実と向き合う重要性
びーやま氏の洞察は、大学受験が単なる学力テストではなく、その後の就職活動やキャリアパスに直結する現実的な課題であることを浮き彫りにします。特に「高学歴」の定義と「学歴フィルター」の存在は、理想論だけでは語れない日本の新卒採用市場の厳しさを示しています。学生や保護者は、将来の選択肢を広げるために、びーやま氏が提供するような現実的な情報と向き合い、「自分らしい大学進学」を戦略的に考えることが求められます。
参考文献
- びーやま. (2025). 『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』. (具体的な出版社、ISBN等は記事から読み取れないため一般的に記載)
- Yahoo!ニュース. (2025年7月21日). 「高学歴」はMARCH以上って本当? 受験の専門家・びーやま氏が解説する「学歴フィルター」のリアル. https://news.yahoo.co.jp/articles/c075778152962f0b4f7f80fa60a2f1a32a958b16