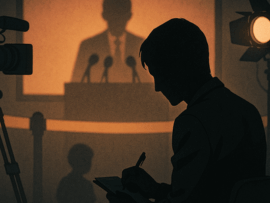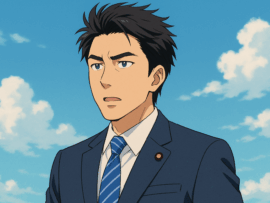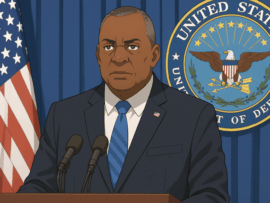公開当初から大きな話題を呼び、その勢いが衰えることのない映画『国宝』。本作では、吉沢亮演じる主人公・喜久雄が、ヤクザの世界から歌舞伎へと足を踏み入れ、芸の道をひたすら突き進む姿が描かれています。歌舞伎界は「血」のつながりが重視される伝統的な世界であり、代々受け継がれる「大名跡」は世襲制が基本です。しかし、現実の歌舞伎界にも、喜久雄のように梨園の生まれではないにも関わらず、その才能と努力でスターダムを駆け上がった歌舞伎役者が存在します。彼らはまさに“リアル喜久雄”と呼ぶにふさわしい存在。ここでは、そんな傑出した“リアル喜久雄”たちの物語を紹介し、歌舞伎の伝統の中で新たな道を切り開いてきた彼らの軌跡を辿ります。
 六代目片岡愛之助のポートレート。映画『国宝』で描かれるような、梨園出身ではないながらも歌舞伎界で成功を収めた“リアル喜久雄”の一人。
六代目片岡愛之助のポートレート。映画『国宝』で描かれるような、梨園出身ではないながらも歌舞伎界で成功を収めた“リアル喜久雄”の一人。
歌舞伎界における血の重みと新たな道
歌舞伎の世界では、古くから血筋、すなわち「血」のつながりが何よりも重んじられてきました。歌舞伎役者の家に生まれた男児は、幼い頃から初舞台を踏み、やがては大名跡を継ぐために芸の道をひたむきに歩むのが通例です。しかし、この厳格な伝統の中にも、外部から飛び込み、その才能と情熱で歌舞伎界に新たな風を吹き込んだ人々がいます。彼らは世襲制の壁を乗り越え、実力と努力でその地位を確立したことで、歌舞伎の多様性と奥深さを証明しています。
六代目片岡愛之助:異例の転身で花開く
歌舞伎の舞台に留まらず、映画やテレビドラマでも幅広く活躍し、歌舞伎ファン以外からも絶大な人気を誇る六代目片岡愛之助もまた、梨園出身ではありません。工場を営む両親のもとに生まれた愛之助は、習い事の一つとして松竹芸能の子役オーディションを受け、子役活動の一環で歌舞伎に出演する機会を得ました。この出会いが彼の運命を大きく変えます。十三代目片岡仁左衛門に見出され、二代目片岡秀太郎からの誘いを受けて、片岡一門の「部屋子」(幹部俳優と楽屋を共にし、作法から芸までを間近で仕込まれる立場)へと転身。この異例のキャリアチェンジにより、彼は歌舞伎界へと本格的に足を踏み入れたのです。愛之助自身も、映画『国宝』の喜久雄に深く感情移入したと語っており、「まさしく“ああいう世界”なんですよね。僕の親は任侠ではないし、100%同じというわけじゃありませんけど、いわゆる“外の世界”から飛び込んできた人間でしたから」(※1)とインタビューで述べています。彼の言葉は、歌舞伎界の閉鎖性と、そこへ飛び込む者の覚悟を物語っています。
五代目坂東玉三郎:逆境を乗り越えし“人間国宝”
喜久雄や、横浜流星が演じた俊介と同様に、女形として数々の当たり役を演じ、その美しさと繊細な演技で観客を魅了し続ける五代目坂東玉三郎もまた、梨園の生まれではありません。料亭を経営する家庭に生まれた玉三郎は、1歳半の時に小児麻痺を患い、左足に麻痺が残りました。そのリハビリのために通い始めた日本舞踊が、彼を歌舞伎の世界へと導く入り口となりました。6歳の時、十四代目守田勘弥の部屋子となった玉三郎は、小児麻痺の影響による左利きであることや、女形としては長身(173cm)であることなど、多くの身体的なハードルを抱えながら芸の道を歩みました。しかし、彼の舞踊の評価は非常に高く、日本舞踊はもちろんのこと、10代半ばに始めたバレエでも高い実力を示しました。その類まれな才能と努力が認められ、2012年には重要無形文化財保持者に各個認定され、現代の「人間国宝」としてその功績が称えられています。彼の存在は、血筋を超えた芸の尊さを象徴しています。
二代目中村鶴松:新世代を担う期待の星
若手歌舞伎役者の中でも、将来を嘱望される“リアル喜久雄”の一人が、現在30歳の二代目中村鶴松です。彼は2021年の八月歌舞伎で、一般家庭出身としては異例の主役に抜擢され、立役(男役)と女形(女役)の双方をこなす若きスターとして注目を集めています。児童劇団でのオーディションを勝ち抜き、5歳で歌舞伎に初参加。特に8歳で演じた『野田版 鼠小僧』の孫さん太の演技が十八世中村勘三郎の目に留まり、その部屋子となりました。鶴松は勘三郎に対し、血のつながり以上の特別な思いをインタビューで語っています。「何より勘三郎さんの人間性。裏表がなく喜怒哀楽がすごい人でした。ただ、怒る時でも、何か1ついいところも指摘する。(中略)僕もいっぱい怒られましたが、頭ごなしに怒るのではなく愛情のある怒り方でした」(※2)。血縁が運命を左右すると言われる歌舞伎界において、この師弟関係は血のつながり以上の固い絆で結ばれていたのかもしれません。鶴松は2022年より、勘三郎の本名「波野哲明」から一文字取った自主公演「鶴明会」を実施するなど、精力的に活動しています。また、バラエティ番組にも出演し、伝統芸能である歌舞伎への敷居が高いと感じる人々にとっての間口を広げる役割も担っています。
結びに
片岡愛之助、坂東玉三郎、そして中村鶴松。彼らは歌舞伎の伝統的な血筋とは異なる出自を持ちながらも、その並外れた才能、飽くなき探求心、そして何よりも歌舞伎への深い愛情と情熱によって、それぞれの時代に輝かしい足跡を残してきました。彼らの物語は、映画『国宝』で描かれる喜久雄の姿と重なり、伝統が息づく歌舞伎界において、「血」だけでなく「芸」の力がどれほど重要であるかを示しています。彼らが切り開いた道は、歌舞伎の未来に多様な可能性をもたらし、次世代の才能が育つ土壌を豊かにしていくことでしょう。
参考資料
- 片岡愛之助 Instagram(@ainosuke_kataoka)
- 中村鶴松 Instagram(@tsurumatsu_nakamura)
- ※1 片岡愛之助「血には勝てないと思っていた」 大ヒット映画『国宝』で重なった“歌舞伎の重圧”と覚悟 ENCOUNT
- ※2 中村鶴松「サラリーマン家庭から5歳で歌舞伎の初舞台を踏んだ。〈孫さん太〉で中村勘三郎さんに見いだされ、褒められたい一心で演じている」 婦人公論.jp