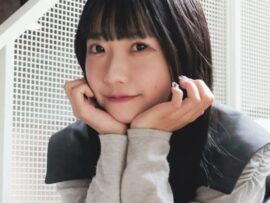交渉期限が迫る中、アメリカとEUが関税協議で合意に至りました。これはEUからの輸入品に15%の関税が適用される内容で、既に合意済みの日本と同じ水準です。この米欧間の動きは、世界の貿易情勢、特に日本企業にどのような影響をもたらすのでしょうか。
米欧間の関税合意と大規模な投資約束
トランプ大統領とEUのフォンデアライエン委員長は、8月1日の交渉期限を前に、当初30%と通告されていたEUからの輸入品に対する関税率を15%に引き下げることで合意しました。トランプ氏はこれを「これまでで一番のディール」と評価。EUは対価として、アメリカから7500億ドル(約110兆円)相当のエネルギー購入と、6000億ドル(約88兆円)を超える大規模な投資を約束しました。フォンデアライエン委員長は「安定と予測可能性をもたらす大きな合意」と述べました。
 トランプ大統領とフォンデアライエン委員長が握手を交わし、米欧間の15%関税合意を象徴する場面
トランプ大統領とフォンデアライエン委員長が握手を交わし、米欧間の15%関税合意を象徴する場面
日本企業への影響と価格転嫁の模索
日米間でも先日、同様の15%関税引き下げが合意され、日本企業では既に動きが出ています。アメリカ向け輸出が多いホタテを扱う「丸イ佐藤海産」の伊勢健代表は、関税決定後、価格に関する問い合わせが増加し、適正な価格転嫁を模索中と語ります。また、インクや化粧品の顔料製造を手掛ける「DIC」は、「関税サーチャージ」制度を導入しました。これは、特定のコスト変動を自動で価格に反映させる仕組みで、個別の価格交渉の手間を省き、透明性を高める効果があるとしています。
結論
今回の米欧間の関税合意は、日米間の合意と並び、国際貿易の新たな局面を示しています。日本企業は、価格転嫁や「関税サーチャージ」といった独自の対策を通じて、不確実な国際経済情勢への適応を模索し続けています。
参考資料
- テレビ朝日「グッド!モーニング」(2025年7月28日放送分)
- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/aa863153f212a4f6eeff75e4414bc2d30a5fdda4)