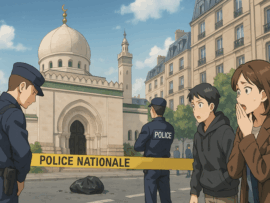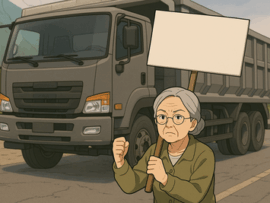日中戦争中、中国において秘密裏に細菌兵器の開発を進めていた旧日本陸軍の「七三一部隊」。彼らが戦場で実際に細菌兵器をどのように使用し、どのような結果をもたらしたのかは、歴史研究の重要な焦点です。特に、初期の試みとそれに続く技術開発の過程は、部隊の活動の実態を理解する上で不可欠な情報と言えるでしょう。
細菌戦の戦略的背景:なぜ「七三一部隊」は中国戦線に関与したのか
ソ連との本格的な戦争を想定し、細菌兵器の開発に注力していた七三一部隊にとって、中国戦線の指揮を執る支那派遣軍と連携し、実際に中国で細菌戦を行うことは、本来の設立目的とは異なるとも言えます。しかし、彼らはなぜ中国戦線での作戦に協力することになったのでしょうか。これは、当時の日本軍全体の戦略的優先順位と、七三一部隊が持つ特殊技術への期待が背景にあったと考えられます。
初めての細菌戦:ノモンハン事件での試みとその結果
七三一部隊が初めて細菌戦に臨んだのは、1939年8月下旬のノモンハン事件でのことです。彼らは満蒙国境線沿いのハルハ河支流ホルステン河にチフス菌を流しました。この試みは、細菌兵器の戦場での効果を検証する目的で行われたものです。
 中国で正式に公開された旧日本軍関東憲兵隊による「七三一部隊」関連の特殊移送公文書。この資料は、部隊の戦時犯罪が国内外に明らかにされた重要な証拠として認識されています。
中国で正式に公開された旧日本軍関東憲兵隊による「七三一部隊」関連の特殊移送公文書。この資料は、部隊の戦時犯罪が国内外に明らかにされた重要な証拠として認識されています。
しかし、この時すでに戦闘は収束しており、兵器としての期待通りの結果を得るには至りませんでした。より大規模に細菌の感染を拡大させ、敵に壊滅的な打撃を与えるにはどうすればよいか、という新たな課題が浮上したのです。この反省から、彼らが次の手段として検討を始めたのが、「雨下(うか)」と称された上空からの細菌散布でした。
空中散布への移行:「雨下」実験の推進
七三一部隊の創設者である石井四郎は、1938年秋には既に、部下の金子順一軍医大尉に対し、航空機を用いた空中からの「雨下」に関する研究を命じていました。これは、広範囲にわたる感染を効率的に引き起こすための画期的な方法として期待されたものです。
金子大尉が後にまとめた「金子順一論文集(昭和十九年)」によると、彼は細菌が混ざった溶液を仮に投下した場合の落下速度、重力、空気抵抗などを詳細に計算しました。そして、1939年3月25日から4月8日の間に、高度100メートルという低空からの落下実験を30回近くも実施しました(具体的な実験場所は不明とされています)。

金子大尉は、これらの30回の「雨下」実験のうち、比較的成果があったとされる3回分のみを実験結果として採用しました。実際の実験は彼にとってほとんど満足のいくものではなかったものの、データを巧みに見せることで成功と報告したのです。しかし、失敗を可能な限り最小限に抑えたいという思いから、金子大尉が新たにその研究対象としたのが、いわゆるPX実験でした。
まとめ
七三一部隊による細菌兵器の開発と使用は、日中戦争における残虐な側面の一つです。ノモンハン事件での初の細菌戦は限定的な効果に終わりましたが、これは彼らが「空中散布」という新たな方法論、すなわち「雨下」実験へと進むきっかけとなりました。金子順一軍医大尉による詳細な実験は、技術的な課題に直面しながらも、部隊が細菌兵器の実用化に向けて試行錯誤を繰り返していた実態を示しています。これらの初期の試みは、その後のより大規模な細菌戦へと繋がっていく重要な段階であったと言えるでしょう。
参考文献
- 広中一成著『七三一部隊の日中戦争』(PHP新書)
- 金子順一論文集(昭和十九年)
- Yahoo!ニュース (元記事: PRESIDENT Online)