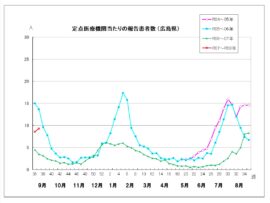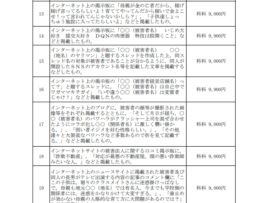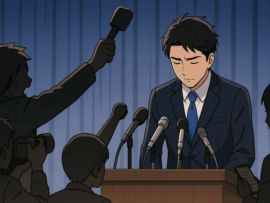日本の独立を目前に控えた1952年、戦後日本のインテリジェンス機関の中核となる内閣情報調査室(以下、内調)の創設を巡り、歴史の証言者たちの間で異なる見解が提示されています。特に、ALSOKを立ち上げたことで知られる村井順氏が「自らが吉田茂元首相に進言した」と語る一方で、アメリカのスパイ組織の関与を示唆する報道も存在し、「内調の生みの親は誰か」という問いは、今なお議論の的となっています。本稿では、これらの異なる証言を紐解きながら、内調創設の真相に迫ります。
「内調の生みの親」を巡る二つの説
内閣情報調査室の設立に関しては、複数の説が錯綜しています。その一つが、初代室長を務めた村井順氏が『政界往来』1970年5月号に発表した手記「内閣調査室の思い出」で語られた内容です。村井氏はその中で、内調の設置は自らが吉田茂首相に進言した結果であると明確に記しています。これは、内調内部の後輩職員から「神格化された創設時代の真相」を書き残してほしいとの依頼に応じたものとされています。
しかし、その翌年の1971年には『週刊文春』が、内調創設の裏側にはアメリカのスパイ組織が関与していたという説を報道しました。これに対し村井氏はすぐさま反論文書を出し、その報道を真っ向から否定。この一連の出来事は、戦後日本のインテリジェンス機関の黎明期における、複雑な背景と権力関係を示唆しています。内調の真の「生みの親」は、一人の人物の功績に帰されるような単純な話ではないことが浮き彫りになります。
村井順と吉田茂首相への「情報機関創設」進言
村井順氏が、内閣直属の情報機関の設置構想を吉田茂首相に進言したのは、サンフランシスコ講和条約の発効によって日本が独立を回復する約20日前の、1952年4月初めのことだったとされています。当時、国家地方警察本部警備部警備課長を務めていた村井氏は、首相官邸に出向き、吉田首相に単刀直入に自身の考えを伝えました。
 情報分析を行うビジネスパーソンのイメージ。内閣情報調査室の役割を象徴する、データ収集と意思決定の重要性を示唆。
情報分析を行うビジネスパーソンのイメージ。内閣情報調査室の役割を象徴する、データ収集と意思決定の重要性を示唆。
村井氏が吉田首相に語ったのは、日本の独立に伴い、情報収集と分析の重要性が格段に増すという認識でした。彼は次のように進言したと記録されています。「近く日本も独立します。今までは占領軍の判断なり方針に従って政治をやってきたが、独立国となった以上は日本が自ら情報を集め、自ら判断し、日本の進路を決めて行かなければなりません」。そして、彼が構想した情報機関の役割を、「内外のあらゆる情報や資料を集め、これを分析し検討して正しい判断を下す。そしてそれを政府の施策に資する」ものと説明しました。
この進言は、GHQの占領下で、日本が自律的な情報活動を行うことができなかった時代が終わりを告げ、独立国家として国際社会で自らの道を切り拓く上で、独自のインテリジェンス能力がいかに不可欠であるかという、村井氏の深い洞察に基づいていたと言えるでしょう。後に綜合警備保障(ALSOK)を創業することになる村井氏の、先見の明と行動力が示されたエピソードです。
結論
内閣情報調査室の創設を巡る村井順氏の証言と、『週刊文春』の報道が示す「アメリカ関与説」の対立は、戦後日本のインテリジェンス機関がいかに複雑な黎明期を過ごしたかを物語っています。この論争は、単一の「生みの親」という単純な物語では語りきれない、多様な国内外の思惑や力が絡み合った歴史の一端を垣間見せます。内調が、独立国家としての日本の情報空白を埋め、政策決定を支える上で不可欠な機関として確立されていく過程は、日本の主権回復と国際社会への復帰という大きな流れの中で、常に重要な位置を占めていました。真の創設経緯は依然として研究の対象であり、今後も新たな史料や証言によって、その全貌が明らかになることが期待されます。
参考文献
- 岸 俊光『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』(筑摩書房)
- 村井順「内閣調査室の思い出」(『政界往来』1970年5月号)
- 『週刊文春』1971年報道 (詳細な日付不明)