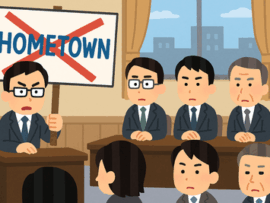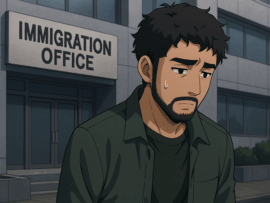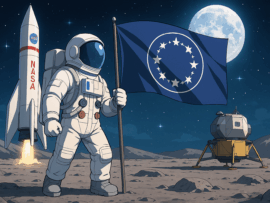7月、米国オリンピック・パラリンピック委員会(USOPC)が、いわゆる「トランス女性」の女子競技参加を禁じる決定を下しました。LGBTQ+の権利拡大が世界の潮流である中、なぜ米国はこの動きに「待った」をかけたのでしょうか。この背景には、生物学的性差と競技の公平性を巡る根深い議論が存在します。ゲイであることを公表している元参議院議員の松浦大悟氏も、近刊『リベラルの敗北 「LGBT活動家」が社会を分断する』の中で、この問題の深層を分析しています。本稿では、米国での最新の動きと、その背景にある競技公平性の問題を掘り下げます。
 LGBTQの権利を求めるパレード参加者がレインボーフラッグを掲げて行進する様子
LGBTQの権利を求めるパレード参加者がレインボーフラッグを掲げて行進する様子
米国におけるトランスジェンダー選手の競技参加規制の動き
USOPCのこの措置は、米紙「ニューヨーク・タイムズ」の電子版が報じたもので、今年2月にドナルド・トランプ前大統領がトランスジェンダー選手の女子競技参加を禁じる大統領令に署名したことを受けた動きと共同通信は伝えています。米国内の各競技団体はUSOPCの規定に従う必要があり、実際、米フェンシング協会は8月1日からこの新規定を適用することを表明しました。
この決定に対する世論の支持も大きく、AP通信が今年5月に行った世論調査では、回答者の52%がトランプ前大統領の対応を支持しています。これに先立ち、全米大学体育協会(NCAA)も2月、トランス女性の女子競技への参加を禁止する決定を下しており、米国全体で競技における公正な競争環境の維持を求める声が高まっていることが伺えます。
公平性を巡る議論と具体例
こうした動きの背景には、トランス女性が女子競技に参加することによって生じるとされる様々な弊害が指摘されていることがあります。松浦大悟氏の著書では、その具体的な問題点が以下のように言及されています。
「思春期を男性として過ごしたトランス女性は、筋肉のつき方や骨格において明らかに生物学的女性と差異がある。アメリカの水泳選手であるリア・トーマス氏は身体男性のトランス女性だが、アメリカの大学選手権では女子の部でメダルを獲りまくっている。男子の部では鳴かず飛ばずだった選手が、一夜にしてメダリストになれるのである。その分、割を食うのは、これまで努力してきた生粋の女子選手だ。奨学金ももらえなくなり、『自分はなんのためにここまで生活を犠牲にしながら頑張ってきたのだろう』と泣くに泣けない状況になっているのだ」
このように、身体能力の差が競技結果に明確な影響を与え、長年にわたり努力を重ねてきた生物学的女性アスリートの機会が不当に奪われるという懸念が、公平性に関する議論の中心となっています。
松浦大悟氏が指摘する背景と社会的分断
松浦氏の分析は、単なるスポーツの問題に留まらず、より広範な社会的な分断とリベラルの理想の敗北という文脈で捉えられています。同氏の著書が示唆するように、トランスジェンダーの権利擁護というリベラルな潮流の中で、既存の規範や生物学的現実との間で摩擦が生じ、社会全体に新たな対立構造を生み出している現状を指摘していると言えるでしょう。特に、スポーツにおける性差の問題は、単なる個人的なアイデンティティの尊重だけでなく、公正な競技環境の確保という、より普遍的な価値との両立が求められる複雑な課題として浮上しています。
結論
米国オリンピック・パラリンピック委員会や全米大学体育協会の今回の決定は、トランス女性選手の競技参加が、女子競技における「公平性」をどのように定義し、維持するかという国際的な議論に大きな一石を投じるものです。生物学的性差と性自認、そして競技の公正性という多岐にわたる視点から議論が深まるにつれて、それぞれの権利と価値観のバランスをいかに取るかが、今後の社会にとって重要な課題となるでしょう。この問題は、スポーツ界のみならず、より広い社会におけるジェンダー論争と多様性の尊重のあり方を考える上で、極めて示唆に富む事例と言えます。
参考文献
- 松浦大悟 (著). 『リベラルの敗北 「LGBT活動家」が社会を分断する』 (書籍に関する情報のため、具体的な出版社名や出版年は仮定)
- ニューヨーク・タイムズ電子版
- 共同通信社 報道
- AP通信 世論調査結果 (2024年5月)