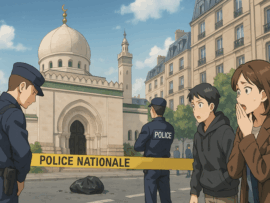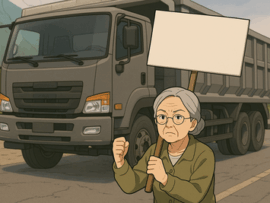「大学受験」は、多くの10代にとって人生における最大の転機の一つです。現在の日本社会では、希望する職業に就く確率を高め、将来の選択肢を広げる上で、大学進学が大きな影響力を持つことは否定できません。このような複雑な時代において、「自分らしい大学進学」を実現するための指南書として、書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売されました。本書は、表面的な美辞麗句を排除し、「大学受験とは何か」「人生とは何か」という根源的な問いに向き合うための決定版とされています。本記事では、発刊を記念し、著者であるびーやま氏への特別インタビューをお届けします。
「日東駒専は低学歴ではない」専門家が語る根拠
学歴に関する議論は常に活発ですが、その中でも特に注目されるのが「どこからが高学歴で、どこからが低学歴なのか」という線引きです。近年、「日東駒専も低学歴である」といった意見が散見され、過熱気味の論調も見られますが、びーやま氏はこれについて明確な見解を示しています。
びーやま氏は、「日東駒専は低学歴ではありません」と断言します。その根拠として、偏差値が50前後である点に触れ、「これは受験する学生の平均的なラインであり、このレベルを低学歴と見なすのは無理がある」と指摘します。さらに、進学校以外の学生にとっては、日東駒専であっても十分な対策なしには合格が難しく、その知名度は全国レベルであることを強調し、「日東駒専が低学歴」という見方は、冗談か根拠のない噂程度に捉えるべきだとしています。
学歴フィルターが「日東駒専は低学歴」という誤解を生む?
では、なぜこのような「日東駒専低学歴説」がまことしやかに語られるのでしょうか。びーやま氏は、その背景に「学歴フィルター」の存在が大きく影響していると分析します。新卒採用において、企業の入社難易度と大学の偏差値をかけ合わせたような「学歴フィルター」が暗黙のうちに存在し、大企業の場合、日東駒専レベルの大学ではこのフィルターに引っかかるケースが少なくないといいます。
 大学受験に悩む学生のイメージ。日東駒専の学歴フィルターや就職への影響を考える
大学受験に悩む学生のイメージ。日東駒専の学歴フィルターや就職への影響を考える
「学歴フィルターに引っかかること」が「低学歴であること」と結びつけられ、このような空気感が生まれているのではないかとびーやま氏は推測します。この意味では、日東駒専の評価は、学生自身ではなく、大人や社会の側が決めてしまっている側面があるのかもしれません。就職活動が学歴の評価に深く関係しているという点は、多くの人が納得するでしょう。
日東駒専の教育レベルと学生の「やる気」の重要性
それでは、教育面において日東駒専は不足があるのでしょうか。びーやま氏の答えは「そうだと思います」と肯定的です。日東駒専やそれに近いレベルの大学には、非常に質の高い教員が数多く在籍しており、特に日東駒専の四校は長い歴史を持つため、学生自身に学ぶ意欲さえあれば、得られるものは計り知れないほど大きいと語ります。
意外と多いのが、「自分たちは所詮日東駒専だから」と学生本人が投げやりになってしまうケースだといいます。しかし、びーやま氏は、「このような姿勢では、どんなに恵まれた環境にいても成長は期待できない」と指摘し、個人の「やる気」が最も重要であることを強調しています。学歴という枠に囚われず、自らの意志で学び、成長しようとする姿勢こそが、真の価値を生み出すのです。
参考文献
- 『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』
- Source link