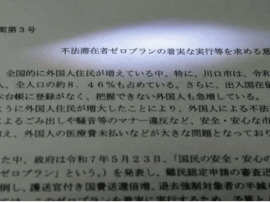日韓両国が国交正常化を果たしてから60年が経過しました。この長きにわたる関係は、幾多の曲折を経て現在に至っています。本稿では、朝鮮戦争の真っただ中であった1951年に始まった両国間の交渉の困難さから、現在までの変遷を詳細に分析し、未来志向の日韓関係構築に向けた課題と展望を探ります。特に、日韓基本条約締結に至るまでの経緯、経済協力の背景、そして度重なる歴史認識の相違がどのように両国関係に影響を与えてきたのかを深く掘り下げていきます。
初期交渉の難航と歴史認識の相違
1951年10月20日、連合国総司令部の仲介のもと、東京で初めて日韓両政府代表団が顔を合わせました。韓国側首席代表の梁裕燦が和解を提案したのに対し、日本側首席代表の井口貞夫は冷笑的な態度で応じ、その後の14年間にわたる険しい交渉の道のりを暗示しました。特に、1953年10月の第3回日韓会談請求権委員会では、大きな論争が勃発し、会談は決裂。韓国側は植民地支配における不当な行為への補償を求め、これに対し日本側は過去の統治が合法であり、むしろ利益をもたらしたと強弁しました。激昂した韓国代表団はテーブルを蹴って席を立ち、「久保田妄言」の撤回がなければ会談再開はないと強く反発し、その後4年半にわたり交渉は中断されました。
会談がこれほど困難を極めた最大の理由は、日帝36年間の植民地支配をめぐる歴史認識の根本的な違いにありました。韓国側は、不法な植民地支配の清算という観点から、日韓間の基本関係と請求権問題の解決を重視しました。一方、日本側は、過去の統治を合法的な条約に基づくものとみなし、歴史清算には消極的で、むしろ平和線の撤廃や在日同胞問題に関心を集中させていました。
国力格差と国際情勢の影響
交渉過程で両国の立場の隔たりが大きかった背景には、他にも複数の要因が存在しました。まず、1951年のサンフランシスコ講和条約に、韓国が戦勝国として参加できず、東南アジア諸国のような賠償権を得られなかったことが挙げられます。また、両国の国力格差も大きく影響しました。1960年代初頭の韓国は貧困国でしたが、日本は朝鮮戦争特需などを通じて大きな経済成長を遂げていました。日韓基本条約が締結された1965年当時、韓国の一人当たり国内総生産(GDP)は108ドル、日本は900ドルと、経済格差は10倍にも達していました。
厳しい対日強硬論を展開していた李承晩政権とは異なり、朴正熙政権が発足すると、対日関係改善への雰囲気が一変しました。米国ケネディ政権は、アジアにおける日本の積極的な役割を求め、また日韓間の経済協力の必要性を強調し、日韓会談が妥結しなければ追加援助は困難であるというメッセージを韓国側に伝えました。ベトナム戦争下で、米国は日韓関係の改善を重視していたのです。朴正熙大統領は、政治的理由に加え、日韓関係を改善しなければ経済成長も不可能であると考えていました。1960年代初頭、一人当たり国民所得が100ドルにも満たない状況下で、経済開発と工業化の達成は急務であり、そのためには日本との関係改善による資本と技術の導入が不可欠でした。
当時、日本は池田政権発足後、過去に対する謝罪や補償の意味合いを排除し、「経済協力」の名目で韓国に接近しました。東南アジア諸国との戦後処理に適用した「経済協力方式」を韓国にも適用し、資本ではなく工業製品やサービスを提供することで、自国の経済進出の足掛かりとしました。朴正熙政権は、開発資金誘致を最優先とする難しい外交戦を強いられました。
日韓基本条約の締結と資金の性格
1965年6月22日、第7回会談を経て、日韓両国は世界外交史上でも稀な14年間の交渉(会議回数1500回)を終え、日韓基本条約(日韓協定)を締結しました。
 1965年日韓基本条約調印式で署名する両国外相
1965年日韓基本条約調印式で署名する両国外相
翌日、朴正熙大統領は国民に向けた特別談話を発表しました。「苛烈な国際社会の競争の中で、過去の感情だけに執着してはいられない。たとえ昨日の仇であっても、今日と明日のために必要であれば手を握るのが賢明な対処ではないか」。
この会談妥結により、日本は無償3億ドル、有償2億ドル、商業借款3億ドルの合計8億ドルを韓国に供与することになりました。当時、日本の外貨保有高が14億ドルであったことを考えれば、決して少なくない金額でした。韓国政府は1960年代初頭から製鉄所建設資金の調達に尽力していましたが、戦争脅威に伴う国家リスクのため、借款の獲得には失敗を重ねていました。このような状況下で、日本からの資金導入は極めて重要でした。問題は、この資金の性格でした。朴正熙政権は、これを植民地支配の実質的な補償であると明確に規定しようとしましたが、日本は経済協力の一環であるという立場を貫きました。この立場の違いは、会談妥結後も両国間に長期的な禍根を残すこととなります。
「漢江の奇跡」と関係の変遷
朴正熙政権は、この資金をどのように活用したのでしょうか。1976年の経済企画院の『請求権白書』によれば、浦項(ポハン)製鉄の建設に最も多くの資金が投入されました。無償・有償資金1億1948万ドルと、鉱工業用に導入された原材料1億3282万ドルが、浦項製鉄の建設と工場稼働に充てられました。故・朴泰俊元ポスコ名誉会長は、「我々の先祖の血の代価で建てられた製鉄所だ」と語ったこともあります。
資金は社会間接資本の拡充にも充てられ、昭陽江(ソヤンガン)多目的ダムや京釜(キョンブ)高速道路の建設、上水道の拡張、漢江鉄橋の復旧、嶺東(ヨンドン)火力発電所の建設、鉄道施設の改善などがこの時期に行われました。韓国はこの資金を経済発展の「種銭」として効果的に活用し、その後、「漢江の奇跡」と呼ばれる高度経済成長を遂げ、両国間の格差は次第に縮小していきました。昨年、韓国の一人当たりGDPは3万6024ドルで、日本(3万2476ドル)を上回りました。経済規模は依然として日本が韓国の2倍を超えますが、かつて垂直的・非対称的だった日韓関係は60年を経て、対等で水平的な関係へと進化を遂げています。
過去60年の波乱と課題
過去60年間、日韓両国は数多くの紆余曲折を経験してきました。国交樹立初期は、冷戦体制下で米国との安保同盟、政治・経済の結束が最優先され、過去の問題は表面化しにくかったといえます。
しかし、脱冷戦が本格化した1980年代後半からは、歴史・領土問題が表面に浮上し始めました。これにより冷え込んでいた日韓関係は、1998年、「過去を乗り越え未来へ」という金大中(キム・デジュン)ー小渕パートナーシップ宣言を通じて新たな協力モデルが提示されました。しかし、両国関係はその後すぐに後退します。2010年代は、米中対立の加速とともに、慰安婦問題、強制徴用問題、日本の輸出規制、ノー・ジャパン運動、さらにはGSOMIA(日韓軍事情報包括保護協定)停止や哨戒機事件など、広範な対立が表面化した「失われた10年」となりました。
その後、2023年以降、ロシア・ウクライナ戦争、米中覇権競争、グローバル経済の分断化、北朝鮮の核ミサイル脅威など、複合的危機状況が登場し、両国は協力の必要性を改めて認識しました。シャトル外交の再開、輸出規制の解除、GSOMIAの正常化、年間1100万人を超える人的往来など、関係改善が進んでいます。
しかし、政治・外交的変化に比べ、相手国への肯定と信頼、共感の形成は依然として不十分です。例えば、2018年、強制動員被害者が日本企業を相手取った損害賠償訴訟で勝訴すると、日本政府は日韓協定で請求権はすべて解決済みと主張しました。一方、韓国大法院(最高裁に相当)は、被害者の個人請求権は消滅していないとの判決を下しました。こうした法的解釈の違いだけでなく、慰安婦・強制動員・歴史教科書・靖国神社問題など、対立要素は依然として存在します。
未来志向のパートナーシップ構築へ
日韓関係の持続的発展のためには、以下の3つの要素が重要であると考えられます。
- 国民的支持の確保と全分野での実質的協力: 両国国民がお互いへの理解を深め、文化交流や経済協力など全分野で実質的な協力を推進し、信頼関係を醸成することが不可欠である。
- 過去史問題の戦略的管理と学界・市民社会の地道な対話努力: 過去の歴史に関する認識の相違は根深く、感情的な対立を招きがちである。学術界や市民社会レベルでの地道な対話を継続し、互いの立場を理解する努力が求められる。
- 変化する国際情勢と両国の戦略的利益共有に基づく未来志向的パートナーシップの推進: 国際情勢が常に変化する中で、両国が共通の戦略的利益を見出し、安全保障、経済、地域協力など、多岐にわたる分野で協調していくことが、未来を見据えた関係構築の鍵となる。
日韓国交正常化60周年を迎える今年、1998年の金大中ー小渕宣言を継承する「日韓パートナーシップ宣言2.0」構築に向けた議論を開始することが、両国関係を次の段階へと進める上で極めて重要です。この宣言は、過去の困難を乗り越え、共通の未来を築くための羅針盤となるでしょう。
李元徳(イ・ウォンドク)/国民大学日本学科教授