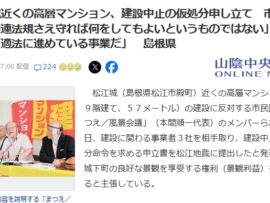敗戦から急速な復興を遂げ、世界有数の先進国となった日本。一方、1949年の建国後、21世紀に世界第2位の経済大国へと躍進した中国。両国は国交正常化した1972年以降、日本からの円借款や技術供与が中国の経済成長を強力に後押ししてきました。しかし、50年の歳月を経て、日中間の力関係は大きく様変わりし、今や世界各地で両国企業が激しく競合する時代を迎えています。
日本からの支援と中国経済の飛躍的成長
かつて、日本の支援が中国経済の基盤作りに貢献したのは紛れもない事実です。1990年代に中国遼寧省瀋陽へ進出した愛知県の機械部品メーカー元幹部は、当時の中国の経済急成長と、インフラ未整備や頻発する停電といった課題を振り返ります。中国は安価な人件費を武器に生産拠点を誘致してきましたが、経済成長と共に人件費は高騰。同社も2017年には工場をベトナムに移転せざるを得なくなりました。現在も中国の日系自動車メーカーへ製品を供給していますが、近年は中国現地の部品メーカーの勢いに押されていると語ります。
中国市場における日系企業の苦戦と撤退動向
帝国データバンクの調査によると、中国に進出した日系企業数は2024年時点で1万3034社となり、ピークだった2012年から約1割減少しました。この背景には、米中貿易摩擦の激化によるサプライチェーンの分断や、中国経済の成長鈍化が指摘されています。しかし、北京に駐在する日系自動車大手の幹部は「それは単なる言い訳に過ぎない。もはや日本企業は中国で勝てなくなっている」と厳しい現状を強調。中国市場の競争激化が、日系企業にとって大きな試練となっている実態を示しています。
 中国安徽省合肥にある最新の電気自動車(EV)生産ラインの様子。中国の経済成長と製造業の競争力を象徴する光景。
中国安徽省合肥にある最新の電気自動車(EV)生産ラインの様子。中国の経済成長と製造業の競争力を象徴する光景。
低下する日本の存在感と外交関係の変化
国交正常化時、日本の3分の1に過ぎなかった中国の国内総生産(GDP)は、2010年には日本を追い越し、2024年には約5倍近くまで拡大しました。このような経済力逆転に伴い、中国における日本の存在感は明らかに低下傾向にあります。中国外務省は2015年に対日関係を担当する「日本課」を廃止し、朝鮮半島やモンゴルを担当する部署に統合。また、経団連などの日本の主要経済団体は1975年以降ほぼ毎年、北京へ大規模代表団を派遣していますが、2008年に胡錦濤国家主席(当時)と会談したのを最後に、中国最高指導者との面会は実現していません。「中国はもはや米国以外をそれほど重視していない」と北京駐在の日系インフラ大手幹部が語るように、日中間の経済的優位性は過去のものとなり、関係性の再構築が求められています。
変化する日中関係の展望
かつて経済発展を支援し、友好関係を築いてきた日中両国ですが、50年の時を経てその力関係は劇的に変化しました。日本企業は中国市場での競争激化に直面し、日本の対中経済的な影響力も低下の一途を辿っています。今後の日中関係は、もはや「援助と被援助」の関係ではなく、世界経済における主要な競争相手として、新たな戦略と対話が不可欠となるでしょう。
参考資料
- 時事通信
- 帝国データバンク