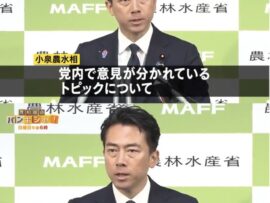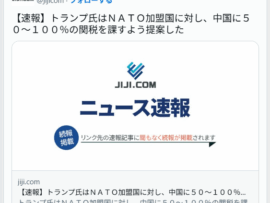長寿化が進む現代において、「投資はいつまで続けるべきか」「シニアになったら投資は引退すべきか」といった疑問は、多くの高齢者やその家族にとって無視できない重要なテーマとなっています。老後の資産形成と運用は、個人の生活だけでなく、社会経済全体にも深く関わる問題です。本記事では、資産運用の専門家である井出真吾氏の提言を基に、シニア世代の投資の必要性とその賢い活用術、さらには資産に対する日本人の意識について深く掘り下げていきます。実質的な資産価値の維持、インフレへの対策、そして次世代への資産承継のあり方まで、多角的な視点から「生涯投資」の意義と実践方法を探ります。
シニア期における投資の必要性と「生涯投資」のすすめ
「何歳まで投資を続けていいのか?」という問いに対し、専門家は「無理に投資を続ける必要はないが、シニアになってもできる限り投資を続けるべきである」と提言しています。投資は年齢や性別、国籍に関係なく、正しい知識と冷静な判断力があれば誰でも行うことが可能です。特に、人生100年時代と言われる現代において、「生涯投資」の概念はますます重要性を増しています。
現役時代に築き上げた投資資産をすべて現金化し、預貯金として保有し続ける場合、名目上の元本は減少しなくても、インフレが進行すれば実質的な購買力は目減りします。税引き後の預貯金金利がインフレ率を上回らない限り、この目減りは避けられません。もちろん、元本割れのリスクを避けるためにあえてインフレによる目減りを受け入れるという考え方もありますが、「シニアだから」という理由だけで投資を完全にやめる必要はないというのが専門家の見解です。
自分が生きている間に確実に使う予定のある資金は、株式などのリスクに晒さず、低リスクから中リスク程度の安定的な運用方法を選択するのが賢明です。しかし、すぐには使う予定がない、あるいは使わずに済む可能性のある資金については、ある程度のリスクを取って株式などで長期的に有利な運用を続けることが推奨されます。これにより、インフレによる実質的な資産の目減りを防ぎ、将来的な選択肢を広げることが可能になります。
ただし、ご自身で冷静な判断が難しくなってきたと感じたり、投資詐欺や悪意のある人物からの搾取といったリスクが懸念される場合は、思い切って投資から身を引くことも非常に重要です。自己防衛の意識と適切な判断が、安全な資産運用には不可欠です。
 シニア世代がタブレットで投資情報を見るイメージ画像。老後の資産形成と運用について考える高齢者の姿。
シニア世代がタブレットで投資情報を見るイメージ画像。老後の資産形成と運用について考える高齢者の姿。
「資産を使い切りたい」日本人の意識と欧州の資産承継観
日本では、「自分が生きているうちにお金を使い切りたい」と考える高齢者が多い傾向にあります。内閣府の経済財政白書によると、高齢者の遺産に関する考え方で最も多かったのは「使い切りたい」という回答で、全体の34%を占めています。これは、自ら築いた財産を自らの手で有意義に使いたいという当然の欲求や、高い相続税への意識が影響していると考えられます。
しかし、自分が何歳まで生きるかを正確に予測することは誰にもできません。また、貯蓄を取り崩すことに対する抵抗感も相まって、日本人は諸外国と比べて死亡時の財産額が最も多いという調査結果もあります。国税庁の調査によれば、2022年の日本の相続財産は21.8兆円余りにも達し、2013年の12.5兆円からほぼ倍増しています(相続税が発生したケースのみ)。
このような現状は、資産を「使い切る」という意識と、結果的に多くの資産が残されるという現実との間にギャップがあることを示しています。一方で、ヨーロッパの貴族社会では、個人のお金という考え方を超え、「家系のお金」や「自分が生きた証としてのお金」という発想で資産が捉えられ、世代を超えて受け継がれていく文化があります。この異なる資産観は、私たちに資産の持ち方や次世代へのつなぎ方について、新たな視点を提供してくれます。
結論:変化する時代に対応するシニア世代の資産戦略
シニア世代の資産運用は、単なる老後資金の確保にとどまらず、インフレへの対抗、そして人生の満足度を高めるための重要な戦略です。専門家が提唱する「生涯投資」は、現在の長寿社会において、実質的な資産価値を維持し、より豊かな老後を送るための現実的な選択肢となり得ます。
もちろん、投資は自己責任であり、自身の健康状態や判断能力の維持、そして詐欺リスクへの警戒も不可欠です。無理のない範囲で、自身の状況に合わせた最適な運用戦略を見つけることが重要です。また、「資産を使い切りたい」という個人の願望と、実際に多くの資産が残されるという現実のギャップを理解し、次世代への資産承継についても長期的な視点で考えることが求められます。
変化の激しい時代の中で、シニア世代が経済的な安定と精神的な豊かさを享受するためには、従来の価値観にとらわれず、柔軟かつ戦略的に資産と向き合う姿勢が何よりも大切だと言えるでしょう。
参考文献
- 井出真吾『井出真吾の投資相談室 63のQ&Aでわかる安心運用』日経BP 日本経済新聞出版
- 内閣府 経済財政白書
- 国税庁 統計情報