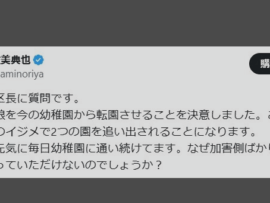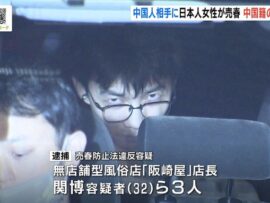現在放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」では、ヒロイン・柳井のぶの夫である嵩が漫画家を志すも、手嶌治虫の漫画を見てその天才ぶりに愕然とする描写があり、大きな話題を呼んでいます。この手嶌治虫のモデルこそ、「漫画の神様」と称される手塚治虫さん。彼が19歳で発表した革新的な作品『新宝島』は、いかにして戦後の日本漫画に衝撃を与え、その後の表現に多大な影響をもたらしたのでしょうか。
 漫画界の巨匠・手塚治虫氏の姿
漫画界の巨匠・手塚治虫氏の姿
若き手塚治虫の衝撃作『新宝島』とは
手塚治虫氏は1928年大阪生まれ、1989年に逝去しました。「あんぱん」のモデルとなったやなせたかし氏よりも9歳年下でありながら、その才能は当時から圧倒的でした。作中で嵩が読み、衝撃を受けたのは、手塚氏が19歳の1947年に発売された『新宝島』です。当時の手塚氏はまだ大阪帝国大学附属医学専門部の学生であり、その若さで生み出された作品に、嵩だけでなく、後の漫画界を牽引する巨匠たちが次々と打ちのめされました。『サイボーグ009』の石ノ森章太郎氏、『ゴルゴ13』のさいとう・たかを氏、そして『ドラえもん』を生み出した藤子不二雄氏(いずれも故人)もその一人です。彼らが共通して衝撃を受けたのは、それまでの漫画の常識を覆す、全く新しい表現がそこに凝縮されていたからに他なりません。
1988年、逝去前年の手塚治虫氏の貴重な写真
漫画表現に革命をもたらした『新宝島』の革新性
『新宝島』は、ピート少年が父親の遺品から見つけた地図を頼りに宝探しをする物語です。その物語の冒頭、ピートがスポーツカーを走らせて波止場へ向かう場面から、手塚漫画の革新性はすでに示されていました。
映画的な「カメラワーク」の導入
手塚氏は、ピートと車を斜め、横、後ろなど、様々な角度から繰り返し描くことで、車が実際に疾走しているかのような躍動感を表現しました。これは今では漫画の基本的な技法ですが、『のらくろシリーズ』や『冒険ダン吉』といった戦前の作品には見られなかった手法です。加えて、車や登場人物を大きく描いたり、小さく描写したりと、まるで映画のカメラがアップからロングへと切り替わるような視覚効果を多用しました。この「映画的表現」により、2次元である漫画の世界に立体感と奥行きが生まれ、さいとう・たかを氏は『新宝島』を読み、「紙の中で映画が作れる」と感銘を受けたと語っています。
「コマ割り」の常識を打ち破る
当時の漫画は、1ページを4コマ、6コマ、8コマ、12コマなど、ほぼ等分割することが一般的でした。しかし、手塚氏はその常識を打ち破り、大小様々なコマを自由に配置しました。これにより、車や人物などを大きく描くスペースが確保され、表現の幅が飛躍的に広がったのです。
「絵と言葉のズレ」による表現の奥行き
さらに手塚氏は、あえて絵とセリフ(言葉)が完全に一致しない場面を作り出しました。これにより、言葉による説明調を避け、読者に想像の余地を与え、より深い立体感を生成しました。現代の漫画では当たり前の手法ですが、絵と言葉が常に一致していた戦前の漫画とは一線を画し、その後の漫画表現の可能性を大きく広げました。
「赤本」として大ヒット、そして共同制作の背景
『新宝島』は、本屋には並ばず、主に玩具店などで販売される子供向けの「赤本」(表紙が赤いことからこう呼ばれた)として世に出ました。限られた販売網にもかかわらず、その革新性と魅力は多くの子供たちを惹きつけ、発売部数は驚異の40万部に達する大ヒット作となりました。
一方で、一部に誤解がある点として、『新宝島』は手塚氏の単独作品ではありません。ストーリーは23歳年上の漫画家であった故・酒井七馬氏が考案し、版元である大阪・育英出版の判断によって二人の合作として出版された経緯があります。
結論
手塚治虫氏が19歳で世に送り出した『新宝島』は、その若さにもかかわらず、従来の漫画表現の枠を大きく超える革新的な技法を導入しました。「映画的カメラワーク」「自由なコマ割り」「絵と言葉のズレ」といった表現は、当時の読者や漫画家たちに強烈な衝撃を与え、「紙の上で映画が作れる」という新たな可能性を示しました。限られた環境の「赤本」でありながら、その内容が多くの人々に届き大ヒットを記録したことは、手塚治虫が真の「漫画の神様」と呼ばれる所以であり、現代の日本漫画の礎を築いた記念碑的作品であることを改めて物語っています。
参考文献
- Yahoo!ニュース: 19歳の漫画に唸る (デイリー新潮 2025年8月10日掲載記事)