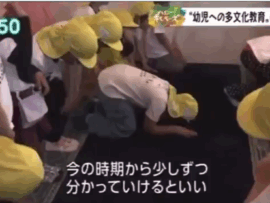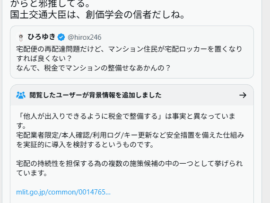80年前、日本の敗戦によって幕を閉じた第二次世界大戦中、日本の軍人や医師による生体解剖が密かに行われていました。公になったのは戦犯として裁かれたごく一部のケースに過ぎませんが、実際には他にも知られざる事例が存在したと言われています。一体どのような状況で、どのような人々が、どのような意図のもとにこれらの行為に手を染めたのでしょうか。そして、そこから見えてくるものは何なのか。この記事では、特に広く知られることになった「九州大学医学部事件」に焦点を当て、当時の新聞記事を基にその実態と歴史的意義を探ります。
九州帝国大学医学部事件の概要
日本の戦時中に行われた生体解剖事件の中で、最もよく知られているのが九州帝国大学(当時、以下「九大」と表記)医学部で発生した事件です。この事件については、上坂冬子の著書『生体解剖―九州大学医学部事件』(1979年単行本化)などによっても詳しくドキュメントされています。生体解剖が行われたのは、敗戦が目前に迫った1945年(昭和20年)5月から6月にかけての短期間に、計4回にわたって実施されたとされていますが、その全容が明るみに出たのは終戦後のことでした。
連合国軍総司令部による逮捕命令
この事件が公に報じられたのは、終戦後の1946年(昭和21年)7月18日付の地元紙・西日本新聞の1面トップ記事によってです。同紙は以下のように報じました。
「荒川元九大総長・石山医学部長ら 戦犯五氏に逮捕命令 マ(マッカーサー)司令部は12日付で日本政府に、元九大(九州帝国大学)総長・荒川文六博士、同大医学部の石山福二郎教授(外科部長)、平光吾一教授(解剖学)、石山外科の助教授2人の計5氏を戦犯容疑者として指名、逮捕のうえ第8軍に引き渡すべきと命令した。」
ここで言及されている「マッカーサー司令部」とは、終戦後の日本占領・統治を担った連合国軍総司令部(GHQ)のことであり、「第8軍」はその指揮下で実際に日本に駐留したアメリカ軍の部隊を指します。新聞記事には、逮捕命令が下された5名の顔写真が添えられ、「捕虜虐殺の容疑」という衝撃的な見出しが挟まれていました。
 第二次世界大戦中の医療と兵士の関連を示すイメージ画像
第二次世界大戦中の医療と兵士の関連を示すイメージ画像
日本の学園史に残る汚点
西日本新聞の記事は、逮捕命令のニュースに続き、この事件が日本の学園史にいかに拭い去ることのできない汚点を残したかを厳しく指摘しています。
「さきに学園民主化運動を起こし、好ましからざる教授の追放その他、新しい学園の在り方について苦悶を続け、最近ようやく波乱が収まったかに見えた九州帝大からついに戦犯容疑者を出すに至った。かつて学の自由を標榜した大学、最も民主的であり、進歩的かつ人道的とされていた大学において、野蛮極まる捕虜虐殺の容疑で数名の幹部が逮捕命令を受けたことは、戦時中軍閥が学園に加えた圧迫がいかに甚だしかったとしても、日本の学園の歴史にぬぐい去るべからざる汚点を印したといえる。」
記事は、学問の自由を掲げ、民主的かつ人道的であるとされてきた大学が、このような野蛮な行為の舞台となったことへの強い非難を込めています。また、戦時中の軍部による学園への甚大な圧力があったとしても、この事件が残した負の遺産は大きいと論じています。さらに、「学園民主化運動」の一環として医学部幹部の進退問題が議論された際、「捕虜に対して言語に絶する残虐行為が同学部の一部職員と西部軍との共同の下に同大学の解剖台上で行われた」という流言が伝わったことにも触れ、この流言が民主化運動に少なからぬ影響を与えた事実を想起させています。今回の戦犯容疑者逮捕命令は、九大が再び民主化への新たな出発点に立たされたことを意味すると記事は結んでいます。なお、「西部軍」とは、当時の中国、四国、九州の部隊を指揮・統率した旧日本陸軍の軍組織で、本部は福岡市に置かれていました。
歴史の教訓としての生体解剖事件
九州帝国大学医学部における生体解剖事件は、第二次世界大戦末期の混乱と、軍部による学術機関への圧力、そして倫理観の欠如がもたらした悲劇的な出来事です。この事件は、戦争が人々に及ぼす極限状況と、それに伴う倫理の麻痺、そして学術機関がその独立性を失った際にいかに危険な道を歩むかを現代に問いかけています。歴史の暗部を直視し、二度とこのような行為が繰り返されないよう、その教訓を深く心に刻むことが求められます。
参考文献:
- 西日本新聞 1946年7月18日付記事 (荒川元九大総長・石山医学部長ら 戦犯五氏に逮捕命令)