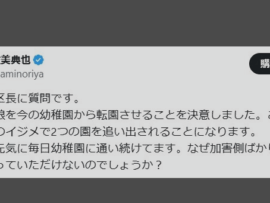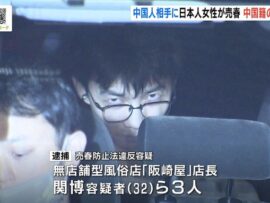今年の6月11日、政府が推進する現金給付政策の非効率性と、それにより地方自治体が疲弊している状況を訴えるX(旧Twitter)の投稿が大きな話題となりました。この発言は、元千葉市長の経験に基づくものとされており、長年にわたり現場を熟知する専門家の声として注目を集めています。日本政府が度々実施する現金給付は、国民への直接的な支援策として期待される一方で、その実務を担う地方自治体には多大な業務負担を強いるという現実があります。
 疲弊し、頭を抱える自治体職員の様子。積み重なる書類が給付金業務の負担の重さを物語る。
疲弊し、頭を抱える自治体職員の様子。積み重なる書類が給付金業務の負担の重さを物語る。
「特別定額給付金」に見る、給付業務の具体的な負担
給付制度の設計によって内容は異なりますが、2020年のコロナ禍で実施された「1人一律10万円」の特別定額給付金を例に取ると、自治体業務の負担の大きさが明確になります。このケースは比較的シンプルな部類に属するものの、まずは基準日時点の全対象者のデータを抽出し、さらに政府から個人への給付が「贈与契約」にあたるため、全員に受け取りの意思確認を行う必要があります。具体的には、申請書を郵送し、必要事項や口座番号を記載したものを返送してもらう作業が発生します(郵送申請の場合)。その後、返送されてきた大量の申請書の確認と入力作業を一つずつ行い、金融機関へ引き渡すまでが一連の大きな流れです。
これらの事務作業と並行して、コールセンターの設置も不可欠です。問い合わせが殺到するため、想定されるQ&Aマニュアルの作成、そして問い合わせ対応業務を民間事業者に委託するなどの事務処理も発生します。これらはすべて、膨大な人員と時間を要する作業であり、地方自治体の限られたリソースに重くのしかかります。
条件追加による複雑化と人手不足の深刻化
一律給付のケースでもこれほどの負担が生じるにもかかわらず、制度に「非課税世帯は追加給付」「子ども1人あたりいくら」といった条件が加わると、業務はさらに複雑化します。対象者の抽出、資格確認、支給額の計算などが複雑になり、作業量は飛躍的に増大します。
現状、市区町村に現金給付を専門とする部署は存在しません。そのため、各部署から知識や経験のある職員を臨時に集めて特別チームを編成するのが一般的です。しかし、昨今では自治体職員の採用が難しく、むしろ民間企業への転職が増えるなど、そもそも人手が余っている状況ではありません。このような中で、本来の通常業務から職員を離れさせて対応させるため、現場が疲弊するのは当然の結果と言えるでしょう。この状況が毎年繰り返されていることに、多くの自治体関係者が強い疲労感を抱いています。
岸田政権下での「最悪」の政策と石破政権の新提案
特にひどかったのが、昨年6月に岸田政雄政権下で実施された「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」です。給付と減税を同時に行うという複雑な政策は、対象者ごとに極めて複雑な計算を要求しました。さらに、昨年10月の衆院選までに「減税感」を出すことを優先したため、自治体は極端に急かされ、処理作業は混乱を極めました。結局、減税を先行させ、過不足を後で調整する形となりましたが、その処理は今なお終わっていない自治体も多く、現場からは「最悪の政策」との声が上がっています。
そして今回、石破茂政権は参議院選挙の公約として「一律2万円給付」を掲げました。これに加え、住民税非課税世帯の大人にはプラス2万円、18歳以下の子どもにもプラス2万円といった複雑な条件が付加され、さらに状況を悪化させています。参院選後に臨時法案を成立させ、補正予算を組んで年内には配布するという、あまりにも無計画で無理のある日程が示されているのが現状です。
政策再考を求める地方自治体の悲鳴
毎年のように繰り返される現金給付政策は、地方自治体の業務負担を際限なく増加させ、現場の疲弊は限界に達しています。コロナ禍以降、国民への迅速な支援は重要視されるべきですが、その実務を担う地方行政機関の現状を無視した形での政策実施は、かえって行政サービスの質を低下させかねません。政府は、給付金政策を立案する際、その効果だけでなく、地方自治体の負担と能力を十分に考慮し、より効率的で持続可能な制度設計へと転換するべきです。現場からの悲鳴と怨嗟の声に、国が真摯に耳を傾ける時が来ています。
参照元: Yahoo!ニュース