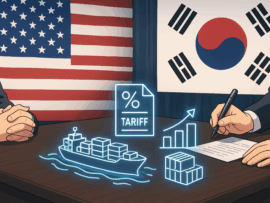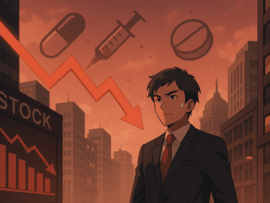1945年8月9日、長崎に投下された原子爆弾は、一瞬にして街を焦土と化し、多くの尊い命を奪いました。その凄惨な光景を15歳の少年として目の当たりにし、救援活動に奔走した一人の男性がいます。長野県の旧四賀村(現・松本市)で村長を務めた中島学さん(95)は、当時、海軍特別少年兵として長崎に赴き、「生き地獄だった」と当時の体験を振り返ります。この記事では、中島さんの貴重な証言を通して、二度と繰り返してはならない戦争の悲劇と、平和への切なる願いを深く掘り下げます。被爆体験の語り部として、若い世代にその記憶を伝え続ける中島さんのメッセージは、現代社会においてかけがえのない意味を持っています。
15歳で長崎原爆後の救出活動へ
全国で公開中の映画「長崎ー閃光の影でー」は、実際の手記に基づき、原爆投下後の長崎を看護学生の視点から描いています。この映画で描かれるのと同時期、廃墟と化した長崎の街に足を踏み入れた少年がいました。それが、当時15歳だった中島学さんです。彼は傷ついた人々を救うため、言葉を絶する惨状の中で活動しました。
中島学さん(95)は当時の状況を次のように語ります。「がれきを少しずつ手で片付けて段々、段々深くしてって、『今、助けてやるからな』と言って。その惨めな凄惨な状況がね、目に入るわけですね」。焼け爛れた大地と、死と隣り合わせの救出劇は、中島さんの心に深く刻まれています。
 長崎原爆の被爆体験を語る元海軍特別少年兵の中島学さん
長崎原爆の被爆体験を語る元海軍特別少年兵の中島学さん
貧困が誘った海軍特別少年兵の道
現在の松本市にあたる旧中川村の農家に生まれた中島さんは、1944年(昭和19年)、14歳で海軍特別少年兵に志願しました。家が貧しかったため、松本の旧制中学へ進学することができず、様々な選択肢の中から、当時華々しく宣伝されていた特別少年兵に憧れ、航空隊へと進んだのです。彼の決断は、当時の社会情勢と貧困が背景にありました。
厳しい訓練を乗り越え、終戦の年である1945年(昭和20年)6月、中島さんは長崎の北約20キロに位置する大村市の海軍航空基地に配属されます。間もなく迎えた初の実戦では、最新鋭の戦闘機「紫電改」の操縦席の後ろで敵機を見張るよう命じられ、被弾し、額と左手に軽い負傷を負いました。幸い大事には至らなかったものの、戦争の過酷さを身をもって知る経験となりました。
「運命の日」:青白い閃光と轟音
そして「運命の日」が訪れます。1945年8月9日、基地の壕で湿った服を乾かそうと外に出た中島さんは、南へ向かう一機の機影を目撃します。それは、第一目標の小倉への原爆投下を視界不良で断念し、第二目標である長崎へと針路を変えたB29爆撃機でした。中島さんはその機体がゆっくりと大村上空を通過し、長崎へと消えていくのを見送ったと言います。
午前11時2分、歴史に刻まれる長崎への原子爆弾投下。「十数秒間、青白い閃光がピカーッと光ったんですね。それからちょっと間をおいてものすごい爆発音が鳴った」と中島さんは鮮明に記憶しています。広島に続く二発目の原爆がもたらした熱線と爆風は、長崎の街を一瞬で壊滅させ、その年だけで7万人以上もの尊い命が犠牲となりました。
壊滅した長崎、浦上地区での過酷な救援活動
中島さんの部隊が長崎市内に救援に赴いたのは、原爆投下から3日後の8月12日でした。かつての賑わいを知る彼らは、変わり果てた街の姿にただ茫然とするしかありませんでした。木造家屋だけでなく、鉄筋コンクリートの建物までもが全て崩れ落ちた惨状は、想像を絶するものでした。被害状況から、中島さんが活動したのは、原爆が投下され最も甚大な被害を受けた浦上地区周辺だったと推測されています。
彼らに下された命令は、「既に死んでいる人は一切見てはいけない」というものでした。がれきの下からは「助けてくれ」と蚊の鳴くようなか細い声が聞こえ、中島さんは「今助けるからな、頑張れ」と声をかけながら、一つ一つ手作業でがれきをどかしていきました。ジャッキなどの道具は何もなく、ひたすら素手で人を救い出す過酷な作業。「頭が出てくれば『さぁ、頑張れよ』って、脇の下に手をかけて引っ張り出してあげて」と、当時の緊迫した状況を語ります。
戦争の記憶を未来へ:中島学さんの平和への願い
中島学さんの証言は、長崎原爆の悲劇を単なる歴史的事実としてではなく、生々しい人間の苦しみとして私たちに伝えます。15歳の少年が目の当たりにした「生き地獄」は、戦争がもたらす究極の破壊と悲惨さを浮き彫りにしています。
中島さんは、自身の被爆体験を若い世代に語り継ぐことの重要性を強く訴えています。彼の言葉は、平和の尊さを深く認識し、二度とこのような悲劇を繰り返さないための強いメッセージとなります。戦争の記憶が風化することなく、未来へと受け継がれていくことで、私たちは平和な世界を築くための教訓とすることができるでしょう。彼の証言は、平和を求めるすべての人々にとって、かけがえのない指針となるに違いありません。
参考文献:
Source link