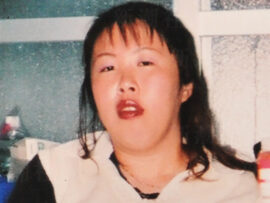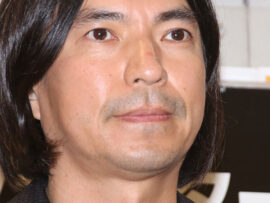25年以上にわたり多くの読者に選ばれてきた人気の大学案内『大学図鑑!』が、今年もさらに内容を充実させて発売されました。現役生やOB・OGら5000人を超える「生の声」に基づき作成された本書は、大学選びにおける貴重な情報源として信頼されています。本記事では、最新版『大学図鑑!2026』(2025年1月時点の執筆内容に基づく)の出版を記念し、立命館大学に関する内容の一部を抜粋・再編集して、その魅力と特徴を深く掘り下げてお届けします。立命館大学は近年、教育課程や学部の再編など様々な改革を積極的に推進し、注目を集めています。カリキュラムは変化に富み、落ち着かない印象を与えることもありますが、どの学部でも専門分野に加え、幅広い学問領域を横断的に学べるのが大きな特徴です。特に2026年度からは、デザイン・アート学部の新設が予定されており、新たな教育の可能性が広がっています。
 立命館大学の活気あるキャンパス風景、学生が行き交う
立命館大学の活気あるキャンパス風景、学生が行き交う
立命館大学の主要学部紹介と学習内容
法学部:専門性を深める多様な特修プログラム
立命館大学法学部は法学科のみで構成されていますが、2年次進級時に「司法特修」「公務行政特修」「法政展開」という3つの特修に分かれ、学生は自身の関心や将来の目標に応じて専門性を深めることができます。「司法特修」には、5年間で司法試験への挑戦を目指す「法曹進路プログラム」が設置されており、法曹界を志す学生を強力に支援しています。「法政展開」では、さらに5つの専門化プログラムから選択が可能。他学部と比較して単位取得は少し大変だとされていますが、その分、高度な専門知識と実践力を養うことができるでしょう。
産業社会学部:アクティブ・ラーニングと多様な学生層
産業社会学部は現代社会学科を擁し、「メディア社会」「スポーツ社会」「子ども社会」「人間福祉」「現代社会」の5つの専攻が設けられています。特筆すべきは、他の専攻の講義も受講できる「クロスオーバーラーニング」制度がある点と、アクティブ・ラーニングを重視した教育が行われている点です。学生の間では単位取得が比較的容易であるとの声も聞かれ、他学部生からは羨望の眼差しで見られることもあります。この学部には、個性豊かで派手な学生が多いという特徴があり、「パラ産」という通称で親しまれています。スポーツ推薦で入学する学生も多く、「現代社会やスポーツ社会の女子はインスタグラムで活躍するタイプが多く、福祉や子ども社会、メディア系の学生は真面目な人が多い」といった、学部内の多様な学生層をうかがわせる声も寄せられています。
国際関係学部:関西初の国際関係学と国際連携教育
関西で初めて設置された国際関係学部には、「国際関係学科」と「アメリカン大学・立命館大学国際連携学科」の2学科があります。国際関係学科では、国際問題を多角的に学ぶ「国際関係学専攻」と、すべての授業が英語で行われる「グローバル・スタディーズ専攻」のいずれかを2年次に選択します。後者のアメリカン大学・立命館大学国際連携学科は、その名の通り両大学が連携して教育課程を編成しており、連名で学位が授与される画期的なプログラムです。学生は両大学を行き来しながら国際関係学の専門分野を深く学びます。学部生の間には高いプライドを持つ者が多く、自身のプロフィール欄には必ず「立命館(IR)」と記載するというエピソードからも、その意識の高さがうかがえます。
文学部:人文科学を深く探求する多様な学域・専攻
文学部は人文学科のみで構成され、「人間研究」「日本文学研究」「日本史研究」「東アジア研究」「国際文化」「地域研究」「国際コミュニケーション」「言語コミュニケーション」という8つの学域と、さらにその中に18もの専攻が設けられています。学域は入学時に、専攻は2年次に選択します。男女ともに真面目な学生が多く、語学の授業や基礎演習などを通じて、似たような関心を持つ者同士が友人になる傾向が見られます。近年は「京都学」と「デジタル人文学」のクロスメジャー制度も導入され、伝統的な人文科学と最新の学術分野を融合した学びの機会も提供されています。
まとめ:『大学図鑑!2026』が照らす立命館大学の真の姿
『大学図鑑!2026』を通じて、立命館大学が推進する多角的な教育改革、そして法学部、産業社会学部、国際関係学部、文学部それぞれの学部が持つ独自の魅力や学生生活の様子が浮き彫りになりました。5000人を超える学生やOB・OGの生の声は、公式のパンフレットだけでは知り得ない、大学のリアルな側面を伝えてくれます。これから大学選びをする高校生にとって、立命館大学が提供する多様な学びの機会や、活気ある学生生活は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。本記事が、皆さんの進路選択の一助となれば幸いです。
参考文献
- Yahoo!ニュース – 25年以上愛されてきた『大学図鑑!』から、立命館大学の評判を抜粋
- 『大学図鑑!2026』(2025年1月執筆内容に基づく)