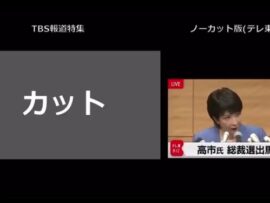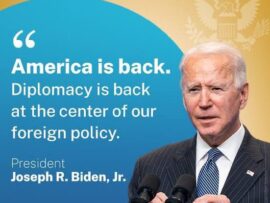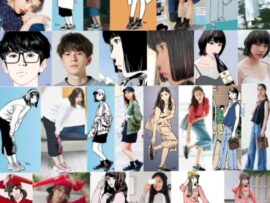日本社会が抱える「入管」における病死、餓死、自殺といった痛ましい出来事、そして「現代の奴隷制」とまで揶揄される「技能実習制度」。これらの問題は、国際社会だけでなく日本国内でも深刻な議論を巻き起こしています。本稿では、安田浩一氏と安田菜津紀氏の著書『外国人差別の現場』(朝日新書)から一部を抜粋し、日本の外国人差別がはらむ実態に迫ります。特に、夢を抱いて来日しながらも過酷な労働環境に直面し、希望を失っていく外国人技能実習生の姿を通して、制度の根本的な問題点を浮き彫りにします。
夢と現実の乖離:カンボジア人実習生の悲痛な声
私は以前、あるシェルターでカンボジア人女性の実習生(33歳)から話を聞く機会がありました。彼女の言葉で特に印象的だったのは、「富士山を見たい」という願いを何度も口にしたことです。彼女にとって富士山は、日本の象徴そのものでした。「カンボジアにいた頃、テレビやインターネットの写真で幾度もその姿を目にしました。あの美しい山のある国で働けると思うと、心が弾んだんです」と彼女は語りました。来日すれば必ず見られるものだと信じていた富士山ですが、岐阜県内の工場で働くことになった彼女は、結局一度もその姿を目にすることなく、シェルターで鬱屈した日々を送っていました。
 外国人実習生からの相談に応じる甄凱さん、日本の技能実習制度問題の現場
外国人実習生からの相談に応じる甄凱さん、日本の技能実習制度問題の現場
「なぜ、職場から逃げてきたのですか?」と尋ねる私に対し、彼女は通訳を介さず、つたない日本語で「仕事、たくさん。お金、少し」と答えました。彼女は地元のブローカーに6千ドルの手数料を支払い、技能実習生となりました。その際、「高度な技術を学び、日本人と同等の給与が保証される」と説明を受け、さらに「富士山の国」という行き先に大きな期待を抱いていました。しかし、彼女の期待と希望は「日本」によって裏切られ、念願の富士山はあまりにも遠い存在でした。
過酷な労働実態と「現代の奴隷制」の構造
彼女が働いた縫製工場の仕事は朝8時半に始まり、ミシンを踏み、アイロンをかけ、完成品を収めた段ボール箱を積み上げていく毎日でした。これが「高度な技術」なのかという疑問はすぐに消え失せ、休む暇もなく働き続けるうちに、そのようなことを考える余裕すらなくなっていきました。
仕事を終えるのは深夜に及ぶことが常で、時には明け方近くまで働かされることもありました。毎月の残業時間は200時間を超え、基本給は月額6万円。残業の時間給は1年目が300円、2年目が400円、3年目にしてようやく500円という低水準でした。さらに、毎月の給与から4万円が強制的に預金させられ、その通帳は経営者が預かったままで、自身が管理することはできませんでした。「このまま働き続けては倒れてしまうと思った。もう限界だった」と彼女は語り、手荷物だけを持ってシェルターに身を寄せたのです。
制度の根本的欠陥と専門家からの提言
それぞれの夢を胸に日本へと渡った外国人実習生たちは、その少なくない数が失望し、落胆し、やがて小さな憎悪を抱くようになります。いつまで経っても「豊かさ」にはたどり着けず、もちろん富士山を見ることも叶いません。
こうした現状に対し、外国人実習生の相談に日々応じている甄凱さんは、「だから、こうした制度はやめたほうがいいんですよ」と指摘します。彼は続けて、「違法が常態化した制度は、おそらく誰も幸せにしない。経営者だって綱渡りしているだけで、いつかは破綻するのですから」と、制度の根本的な欠陥と将来的な破綻を警告しています。日本の国際的な信用にも関わるこの問題は、早急な見直しと改善が求められています。
参考文献
- 安田浩一、安田菜津紀(2023).『外国人差別の現場』.朝日新書.
- Yahoo!ニュース.「病死、餓死、自殺が相次ぐ「入管」、“現代の奴隷制”といわれる「技能実習制度」――日本社会における外国人差別の現状に迫った『外国人差別の現場』より、一部を抜粋してお届けする。」 (2025年8月31日).https://news.yahoo.co.jp/articles/d794fe03285cbd6a3ecfbf68e94e548764e81f70