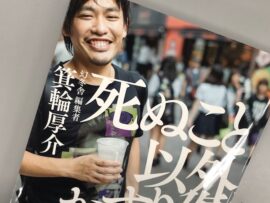中国・武漢発の新型コロナウイルスの国内感染の拡大を受けて、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が現実味を帯びてきた。
西村康稔経済再生担当相は3月31日の会見で「(宣言は)現時点では必要ではない。ぎりぎり持ちこたえている状況だ。少しでも気を緩めれば(感染が)急拡大してもおかしくない」と指摘した。
宣言は新型ウイルスを封じ込める有力な手段である一方、経済・社会活動を大きく冷え込ませる副作用もある。対象地域の活動が減速しても人々が暮らしていけるよう政府や自治体、社会は態勢を整えておかねばならない。
≪「都市封鎖」はできない≫
それにはまず、宣言時にどのような施策をとるのか、国民や企業の行動はどのように制約されるのかを政府が分かりやすく発信していくことが欠かせない。
現時点での日本の感染者・死者数は欧米や中国ほどではない。宣言を出さずに持ちこたえられればそれに越したことはないが予断を許さない状況である。大阪府の吉村洋文知事や政府の諮問委員会メンバーである日本医師会幹部、野党の一部から宣言を求める声があがっている。
政府は感染者・死者数の推移や医療機関の対応能力を見ながら、宣言なしでは感染爆発に至ると判断すれば時機を逸せず発出してもらいたい。最後は安倍晋三首相の政治決断にかかっている。
気になるのは宣言に関わるデマが飛び交ったことだ。インターネット上で先週末から「首相が4月1日に宣言を出す」「4月2日に東京ロックダウン(都市封鎖)」といった誤った情報が流れた。
首相は3月30日の自民党役員会で「明後日(1日)、緊急事態宣言をして戒厳令まで出すといったデマが流れているが、全くない。デマやフェイクニュースに気を付けなければならない」と述べ、明確に否定した。
新型ウイルスをめぐっては、デマに端を発してトイレットペーパーの買い占め騒動も起きた。デマを防がなければ政府や自治体のメッセージが国民に届かなくなる。緊急事態宣言の場合でも人々に正確な情報を伝え、それに基づいて行動してもらうことが重要だ。
感染が拡大した中国・武漢や欧米各国での「都市封鎖」の報道をみて、宣言後の日本を想像している国民は多い。
東京都の小池百合子知事は3月25日の会見で「何もしなければロックダウンを招いてしまう」と語った。首相は同27日に国会で「仮にロックダウンのような事態を招けば、わが国の経済にも甚大な影響を及ぼす」と語った。人々に危機感を持ってもらう意図なのだろうが、言葉が独り歩きして、諸外国のような大規模な都市封鎖が行われると印象付けられた人もいたのではないか。
だが、都道府県知事に認められた権限では、宣言があっても諸外国のような都市封鎖はできない。諸外国がとった罰則を伴う外出禁止令の規定はなく、できるのは住民に対する「外出自粛の要請」である。商店や飲食店の営業禁止の制度もない。
≪人工呼吸器の増産図れ≫
日本では宣言下の地域をどのような姿にして新型ウイルスを封じ込めるのか、特措法の規定にない営業自粛などを合わせて求めるのか、方針を明らかにすべきだ。
多くの人々は知事の要請や指示を尊重し協力するだろう。ただし、食料品や生活必需品の供給や電気・ガス・上下水道・インターネットなど基幹インフラが機能することが前提だ。物資の供給は生産・保管・輸送・販売に多くの人手がかかる。宣言に伴う企業活動の停止で一つでも輪が欠ければ供給が途絶する。政府は民間と事前に調整しておくべきだ。
医療態勢強化は極めて重要だ。宣言が出れば、知事は臨時医療施設のため土地や建物を強制的に使用できる。感染が急増すれば重症でない人を専門病院に入院させられなくなるが、自宅に戻せば家庭内感染を招く。イスラエルや韓国のように、重症でない感染者を待機させる臨時施設の確保を宣言にかかわらず取り組んでほしい。
人工呼吸器が不足する国では死者が増えている。西村氏は3月29日、メーカーに働きかけ人工呼吸器や人工心肺装置の増産に努める考えを示した。機器を操作する医療従事者の教育も急ぐべきだ。