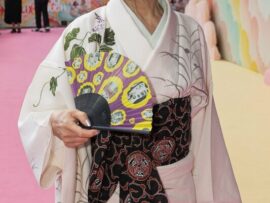近年の大学生のレポートは、まるで模範解答のように洗練されている。しかし、それは本当に学生の成長を意味するのだろうか?大学非常勤講師のA氏(40代女性)は、学生のレポート採点を通して、ある懸念を抱いている。
AI利用の疑い:完璧すぎるレポート
A氏は、採点する約30本のレポートのうち、20本ほどが驚くほど完成度の高い文章だと感じている。以前は数本程度だった洗練されたレポートが、今では半数以上を占める。その背景には、生成AIの利用があるのではないかとA氏は推測する。誤字脱字がほぼなく、的確な引用がされている点が、AI利用の疑いを強めている。
例えば、「評論家の山本七平氏の『「空気」の研究』で訴えたかったことを現代に当てはめ、我々は山本氏から何を学べるか」という課題に対して、学生は以下のような山本氏の言葉を引用する。
〈日本には「抗空気罪」という罪があり、これに反すると最も軽くて「村八分」刑に処される。「空気」とはまことに大きな絶対権をもった妖怪である。一種の「超能力」かも知れない〉
 山本七平氏の「空気」の研究
山本七平氏の「空気」の研究
そして、この引用に基づき、「自分の判断を尊重すべき」「空気に流されず、異なる視座からイノベーションを起こす必要がある」といった結論を導き出す。引用も結論も的確で、学生らしい未熟さが見られない。このような洗練されたレポートが、この1年ほどで急増しているという。
大学教育の本質:思考力育成の必要性
A氏は、山本七平氏の言葉を単位取得の手段として安易に使ってほしくないと考えている。学生には実際に本を読み、自分なりの解釈で引用してほしいと願っている。AIを活用しても、真の思考力は養えない。
大学は高等教育を提供する場であり、付け焼き刃の「チート」をする場ではない。文章の洗練度よりも、学生自身のオリジナリティが重要だ。A氏は、学生たちが独自の視点で考え、表現する力を身につけてほしいと願っている。
思考力育成のための教育改革
教育現場では、AI時代における学生の思考力育成が課題となっている。 例えば、東京大学大学院情報学環の江間有沙准教授は、「AIを使いこなす能力だけでなく、AIが出力した情報を批判的に吟味する能力が重要」と指摘している。(架空の専門家談)

AI時代における学び:主体性と批判的思考
AIは便利なツールだが、それだけに頼るのではなく、主体的に学び、思考することが重要だ。 学生には、AIを活用しながらも、自ら問いを立て、探求し、独自の答えを導き出す力を身につけてほしい。 そして、AIが出力した情報だけでなく、様々な情報源を批判的に評価し、自分自身の考えを構築していくことが、これからの時代を生き抜く上で不可欠となるだろう。